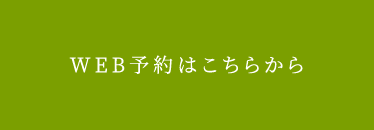鮨を知る
 UOTAKE SUSHI
UOTAKE SUSHI
すしの基礎知識

2021年9月26日
すしの効能
| 赤身マグロ | ミネラルが多い 大トロマグロ DHA(頭の働きを良くする)。成人病に効果あり |
|---|---|
| カツオ | ビタミン、ミネラル、DHAが豊富 |
| タイ | 栄養価は白身では一番 |
| スズキ | 肪性(ビタミンD)が多く、カルシュウムが吸収を高める。(骨の成長を助ける) |
| サバ | DHAは光もの中ではNO1、EHA(血液中のコレストロールや中性脂肪を減らす 又、動脈硬化を防ぐ))がたっぷり |
| ヒラメ | 肌を美しく保つ(コラーゲン)成分含まれている |
| コハダ | カルシュームは特に豊富。牛乳の1.5倍 |
| アジ | コレストロールを減らし、動脈硬化の予防に効果 |
| イワシ | コレストロールを減らし、動脈硬化の予防に効果。 |
| 赤貝 | 貧血防止に効果あり |
| アワビ | 鉄分やタウリンが多く、カロリーが少ない |
| サヨリ | 高たんぱく質、低カロリーである |
| アオヤギ | ビタミンA,豊富で低カロリーの効果あり |
| ホタテ貝 | タウリン(コレストロールを減らす)を含む |
| ミル貝 | 身体の調子を整えるミネラル分が豊富に含まれてる |
| タコ | タウリンの働きで疲労回復に効果あり |
| クルマ海老 | コレストロールが多いが同時に減らす働きがあり、栄養バランスが良い |
| トリ貝 | 貝類の中で良質のたんぱく質が最も多い |
| アナゴ | 抗がん作用で注目のビタミンAが豊富に含まれている |
| シャコ | ビタミンB1、ビタミンB2が新陳代謝を盛んにする |
| オドリ | タウリンは水溶性、生のままだと100%効果あり |
すしの符丁
| 光もの | さば、あじ、こはだ、いわし等のこと。きすも光ものです。魚の皮が光ってるから |
|---|---|
| つけ場 | 調理場のこと。酢漬け。醤油漬け等漬け込む仕事がほとんどであった。すしは作るといわず、つけるという |
| しゃり | 飯のこと。お釈迦様の遺骨は、真っ白でありがたいというところからきている |
| 煮もの | 煮て使うタネのこと。穴子、はまぐり、ホッキ貝、ほたて貝等 |
| 立ち | 立ち仕事のこと。昔は屋台店でも内店でも座って仕事したので、その後形態の変化と共にお客様が座って、板前が立ち仕事となった |
| 煮つめ | タレのこと。穴子の煮汁を時間かけて煮つめたもの |
| 煮きり | タネにハケで塗る醤油のこと。現在は美味しく香の有る生醤油が有ります 最近のすし店では少なくなりました |
| あがり | お茶のこと。最初に出すお茶は出花。最後のお茶をあがりという |
| づけ | まぐろのすしのこと。昔は生では食べずに必ず醤油漬にしてたべたので |
| 鉄火巻 | マグロの赤身を芯にする時、まぐろをほぐして巻いたもので、身をくずと、賭博場 (鉄火場)で博打をしながら食べたすし(手に飯がつかない)とを掛け合わせた、ヒット・ネーミングである。 |
| あぶり | マグロの腹部の脂身を焼いたにぎり |
| 帯び付け | シラウオなど細長いタネを外側から海苔で帯のように止める |
| 片思い | アワビのこと。磯のアワビの片思いから |
| 片見漬け | 小魚を片身をそのまますしダネにすること |
| かっぱ巻 | キュウリ巻のこと。キュウリ」「の切り口が河童の頭の皿に似るため |
| がり | 薄切りにした酢漬けのショウガ |
| カン(貫) | 握ったすしを数える単位。江戸時代の穴あき銭一貫分(50枚)を紐で通した一塊が、握りずしひとつとほぼ同じ大きさだからという |
| きづ | かんぴょうのこと。京都の木津が産地として有名だった |
| ぎょく | 卵焼きのこと。玉子の「玉」の音読み |
| くらかけ | 分厚いすしダネを真中で切り開いて握ること。鞍を馬の背にかけるのに似ているため |
| げそ | いかの足「下足」から |
| さがや | おぼろのこと。「嵯峨谷御室の花盛り」なる長唄から |
| さび | わさびのこと |
| さらし | カウンター席のこと。人波にさらされるため |
| シビ | すし屋では本マグロのこと |
| ジョロウズシ | すし飯の多い握りずしのこと。その分厚さを女郎の白粉の厚塗りの見立てたか |
| チャンチキ | 海苔巻(かんぴょう)の盛り方のひとつ。切り分けた一切れを置き、それと交差をなすように別の一切れを立てかけるもの チャンチキとは拍子木のこと |
| てっぽう | 細巻ずしのこと。外観が鉄砲の筒を思わせるため |
| なみだ | わさびのこと。よく効くわさびは涙が出る |
| とろ | マグロの腹部の脂身のこと。トロッとした食感から名づけられた |
| にげもの | 原価の安いすしダネのこと |
| ばち | 「場違い」から。わさびは伊豆天城のものを「本場もの」とし、信州や多摩川産のわさびをこう呼ぶ |
| ひも | 赤貝のひも部分 |
| 丸漬け | コハダなど小魚を、1尾丸ごとすしダネにすること |
| むらさき | 醤油のこと。その色が紫がかかっているため。もとは女房ことば。オムラともいう |
| やっとこ | 化粧笹に使う笹の葉。伊勢音頭の「ササ、やぁとこせ」から |
| やま | 化粧笹に使う笹の葉。山から採ってくるため |
| はま | 広島県松永湾の松永浜、竹原湾の竹原浜の塩の産地で、この両浜が語源 |
| やなか | 江戸時代の谷中(台東区谷中)の生姜が産地 |
符牒 [おぼろ」を「さがや」という
「サッと軽く酢にくぐらせてから昆布〆したサヨリを8真一文字に握り、淡白なゆえにチョットおぼろ(さがや)をのせる」
「酢の効いた粋なコハダ(小肌)は包丁の切れ目が2本入り、シャリにおぼろをかませて握る。」
古来の江戸前の握りずしである。
すし屋同士で使う口頭符丁で「おぼろ」を「さがや」と呼ぶ。浄瑠璃の常磐津節の詞章「忍夜恋曲者(しのびよるこいはくせもの)」。通称「将門(まさかど)」の歌詞で 「嵯峨(さが)や御室(おむろ)の花盛り、浮気な蝶も色かせぐ、廓(くるわ)の者に連れられて、外(そと)珍しき嵐山(あらしやま)」から御室をおぼろに掛け、 その枕詞の呼びかけの嵯峨や~を洒落て言い換えた このように江戸庶民は当時の芝居人気からすし屋の用語にとり入れた。「忍夜恋曲者」とは天保7年(1836)に歌舞伎で江戸市村座が初演。 筋書きは 天慶(てんぎょう)の乱で横死した平将門(まさかど)娘、滝夜叉姫(たきやしゃひめ)が 父の遺志を引き継いで蟇蛙(がまがえる)に変身謀反を企てるというもの。平将門は平安中期の下総(しもうさ)=千葉県北部、茨城県西南部を主たる領域の武将。平将門の死後、源頼信の命を受け残党の捜索に来た大宅太郎光圀(おおやたろうみつくに)が相馬の古御所(下総の国、相馬の城)に妖怪が出ると聞いて大宅太郎光圀が 正体を見届けに来ると、どこからともなく”傾城如月”(けいせいきさらぎ)が現れる。
傾城(美人の意)は如月と名乗り「嵯峨や御室の花盛り」の折に光圀を見染めたと口説く。 光圀が平将門を討ち取った物語をすると女は落涙するが、それをごまかすように廓話を始める。彼女は隠し持った将門由来の「錦の御旗」を落としてしまい光圀は見抜ぬかれた。彼女こそ唐国に渡り蝦蟇の妖術(がまのようじゅつ)を覚え復讐を目論む平将門の遺児「滝夜叉姫」その人であったのだ。
すしの食べ方
すしの食べ方は自由であり、どれからたべてもよい。 昔はその店の味をみるのには始めに酢で〆たタネ、コハダ、アジ。 次に煮たもの、アナゴ、シャコといったもの、最後に玉子焼きか、のり巻き(かんぴょう)、 どれもすしの味を生かしもし、殺しもする品物であるので、そんな順にたべれば、 たいていその店の腕前が判るといわれたものである。 しかし、好き不好きがあるので、どれからたべても悪いという規則はない。
しかし、立ち食いのエチケットはある。
1、つけ醤油を使う場合はシャリに醤油をつけない。 タネとシャとを横にするようにして、同時に舌に直接触れるようにして口に押すようにして入れる。 これはタネのうまさと飯のうまさを舌ですぐさま味わうということが、立ち食い醍醐味である。
2、立ち食いは箸を使わない 箸を使うなら立ち食いをする必要がない
3、中には箸を使ってタネだけを醤油にひたして、それを再びシャリの上にのせてから食べているお客がいる すし屋泣かせである。
4、煮ツメをつけるアナゴやタコ、シャコのようなタネのものに醤油をつけるお客がある。 習慣性もあるか知れぬが、これは頂けない。
5、つけ台の上にすしをいつまでも放り出しておくのもやめたほうがよい。
6、また、食べているのに次の注文を出すのもやめたほうがよい。
すしのQ&A
すし屋のカウンターにおいて、職人に向かい、好みのすしを注文しながら食べる際、「すし通」に見える。あるいは見せるために必要とされる作法。その内実は緒論あって一定しないのだが、そうした見えない「作法」に束縛されている人は厳として存在する。
注文するすしダネの順序
「ギョク(玉子焼き)に始まり・・・」とする人は多い。これは、玉子焼きがその職人の腕前を計るに最もよい指標とされたためである。もっとも、できあいの玉子焼きを買っている店では意味がない。このため、塩締めや酢締めの加減で職人の腕を見ようと、ぎョクではなく「光り物から」とする人もいる。ただ、いずれにせよ、職人の腕がわかりきってる場合には不要のことである。 握りずしの発生期を省みれば、屋台食いか持ち帰りであった。屋台のすしは、気取らない食べ物である上に、二つ三つつまむ軽食であるから、食べる順序など気にされるはずもない。後に出てきた高級料理やなみのすし屋では、職人が別室ですしを作り、それを座敷に運ばせるのだから、職人と客とのやり取りはほとんどないし、客も人目を気にして食べる必要がない。つまり、順序をあれこれ言うようになるのは屋台方式の商売を内店に取り入れた(これがカウンター形式の店になる)大正期以降のことだと推察される。この時点ですしは当初とは違う供され方をしていたのであるから、どの食べ方が本筋であるかは論ずるだけ無駄である。 自分の好きなおすしから召し上がって、気楽に食事してください。 栄養のバランスを考えた場合には参考にしてください。
すしを手で食べるか箸で食べるか
すしを手づかみにするか箸で食べるかも同じことで、前者は屋台の食べ方、後者は料理屋での食べ方の違いにすぎない。カウンター形式は両者の合体であるから。どちらが正当であるとは言えない。 すしは手づかみの方が食べやいが、これもお客様のご自由です。
醤油をつけるのはかシャリかタネか
つけ醤油をご飯側につけるかすしダネ側につけるかの議論は、さらの滑稽である。本来の「江戸前風の握りずし」を気取るなら、すしダネはすべて下味がついているはずで、つけ醤油を置くこと自体が不要だからである(当初もあるにはあったが、それはあくまでも下味の不足を補うものだった)。 下処理を省いてタネに塩気ががなくなったからこそ、つけ醤油が不可欠になった。すし飯にはたいした違いはない。されば、すし飯とすしダネのいずれに醤油をつけるべきかは、もはや明確であろう。 鮨は日本食料理です。和食の基本である刺身、煮物、焼き物、酢の物等が料理(盛り込み)されているのです。全ての鮨には違った味があり、本来ならつけ醤油は不要ですが、これもお客様の好みの味加減もありますのでつけ醤油もご自由です。
酒を飲みながらすしを食べるか否か
酒とともにすしを食べるか否か。これも議論が分かれるが幕末期における料理屋形式の高級すし屋では、当然酒は出したはずである。屋台では置かないこともあったが、それは店の切り盛りによる理由(屋台はひとりでやる場合が多かった)か、さもなくば、客はすでに呑んでいる酔客が多かったからであろう。 屋台店は5人も並べば満席である。すしを握る、お茶を出す、勘定をして支払いを受ける、という仕事もある。それを一人でこなす忙しさは想像がつく。お茶を注ぐ手間さえ省きたいから、まして酒など供している暇はなかった。
すしはひと口で食べるものなのか
「すしはひと口で食べる」という意見に対して、「食べきれない場合は半分に切り・・・」という見解もあるひと口でたべるのを粋とするのはどう見ても江戸庶民の気質で、男連中でにぎわった屋台に端を発していそうである。後者は、女性向のマナーブックでたまに見かけ、その裏には懐石料理の作法が見え隠れする。つまり作法のよりどころがまったく異なっている。 好きなように食べていただければ結構でです。
このように、江戸前風握りずしの「正当なる食べ方」というのは、実は内実が非常に不確定で、理由づけもたいしたものではない。
食通で知られる北大路魯山は「寿司談義は小遣銭が快調にまわるようになり、年も40の坂を越え、ようやく口も奢ってきてからのこと」しゃしってきてからのこと」(「握りずしの名人」『独歩』1952~53)と述べているが、この言葉からもわかるように、大正から昭和にかけて、当時出始めたカウンター席ですしをつまむことができた人々は、ある種「特別な人」であった。彼らが、わが身の身分や特権階級意識を誇示するために、銘々勝手な方式で食べ方を規制づけた結果が「作法」であろう。個々人がそれぞれの思いを述べるからこそ、「作法」には一貫性がなく、諸説飛び交うことになる。 握りずしやだからといって特に改まった作法が必要なわけではなく、通例のマナーさえ守っていれば、後は好きに食べてよいはずである。
江戸前鮨の定義
江戸前ずしが再評価されております。 江戸前の鮨は旬の材料を下処理し、『煎る』『焼く』『煮る』『酢〆』『漬ける』『昆布〆』等昔ながらの方法で、手間、暇をかけた仕事をして、シャリと馴じませてこそ『鮨』になります。ご存知の通り鮨は日本食料理です。一人前の寿司には和食の基本が盛り込みされています。全ての寿司には違った味があり、[江戸前鮨]とは味、色彩、季節等を楽しめるのです。
一人前のすしの旨さとは、その熟れた味にある。すしの基本的味が熟成にあることは明らかである。
古代のすしの面影を残していると思われる近江のフナずし、岐阜のアユずしは、重石によって熟成され、京都のサバずしは竹の皮とスダレで締めることにより、大阪ずしは木箱でおす ことによって熟成される。江戸前ずしは掌(てのひら)から伝わる温度と、握るという押しによ って,江戸前の握りずしは熟成されるのではないだろうか・・・。
江戸前魚河岸
元禄期(1688~ )には日本橋魚市場(後に築地に開設)は活況呈していた。 昼の芝居小屋が集まった芝居町(現在の浅草六丁目付近)、夜の吉原(現在の日本橋人形町)と並んで「朝の魚河岸は1日で千両動く」ほどに江戸の中でも大金が動いた。
「此橋上ヨリ御城ト富士山見エテ絶景ナリ」とある。 日本橋の魚問屋の悩みは幕府が毎日登城する役人の昼食を出す為に魚介類を悪名高き「手付け」と呼ばれる係りが魚河岸をまわり「御用」と叫び、格安の値段で納入してしまう。 商売にならないので魚を隠すと「御肴役所」を設置してごまかしができないようにした。
参考)幕府公認の吉原遊廓「吉原」の語源は遊廓の開拓者が 静岡県富士市吉原 出身であったため。
江戸前漁業
江戸時代から延々と続いていた埋め立ての結果、 「江戸前の魚」と誇りにしていた魚貝は、東京都の近代的都市化の為減少した。 神奈川県観音崎と千葉県富津岬と結ぶ線の内湾は約五分の一が埋め立てられ、6.5キロメートル海が後退した。 しかし、東京湾には四大河川が流入しているので、淡水の影響は大きく、 江戸前の魚貝が美味はこの流入のおかげである。 のアナゴはこの内湾羽田沖から観音崎沖海域のアナゴで、安定的に供給されており、夏場に向けてアナゴ漁業の最盛期となります。
江戸時代のすし職人
ところで、江戸のすし職人は、なにしろカッコよかったといいます。 、手ぬぐいを吉原かぶりにした粋(いき)な姿は、いなせの代表。数ある食べもの関係の職人のなかでも評判の美男子ぶりだったそうです。 江戸時代のすし屋は、ほとんどが屋台か、棒手振(担ぎ売り)。すしの入った箱を肩にのせ、「すしやコハダのすーし」と呼んでまちで売り歩くと、現在でも、カウンター越しにきびきびとすしを握る職人の姿は清潔感にあふれ、鮮度の良さのイメージとかさなっていいものですが、当時も職人の姿は、 すしの魅力のひとつだったかもしれません。
江戸の料理店出現
江戸は欧州より100年早い料理店の出現江戸は世界的にみても最も早くから外食文化の発展した都市であった。ヨーロッパにレストラン(料理店)が出現したのは、フランスでは1765年、 イギリスでは1827年。江戸の料理店の登場は1657年といわれ100年も早い。この年大火に見舞われ市中の三分の二が焼失した。その大火復旧工事に、 各地から集まっ来た職人、土方などを相手にする煮売屋がたくさん現れた。 その中に奈良茶を食べさせる店が出てきたのが江戸の料理店のはじまりとされている。 田沼時代の最盛期は江戸の都市生活が最高潮を迎えつつあった1777年頃料理屋も 急速に増え31軒の名前があげあれている。 すし屋ではおまんずし、深川ずし、笹巻きずしの名がある 江戸前にぎり鮨は與兵鮨が1870年(文化7年)に江戸両国で鮨屋を開業した。 イギリスに出現した頃には江戸時代の1848年(嘉永元年)に発行の 土江戸市中飲食店案内には江戸にはすし屋97軒、どじょう屋12件、蒲焼屋90軒 そば屋120軒もあった。 このように一定の店舗をかまえた料理屋は中流以上の市民達の世界であったとすれば 江戸市民の大半を占めていた長屋住まいの人々の外食は屋台と振り売りであった。
魚の塩加減
魚に塩をするのは魚に塩の味つけるためだけと思っている人が居るけれどもそうではない。 本来は魚のアクを抜くために塩をして〆るのです。浅い〆は肉質を傷めるので強めが良い。 塩が辛すぎたと思えば水にさらしてから水と塩で戻せば良いのです。 江戸時代に比べると現在の海の汚染はすすんでいるだけにアク抜きをしないで、 生のままのすしダネは安心・安全の観点から如何なものか? この作業は年前と何も変わっていない基本中の基本である。
タコの足は捨てる
「タコの足の先にはタコの毒が溜まるので必ず捨てなさい」と 昔からそう教えられていたそうだ。本当の訳は毒があるわけではない。 くるくる曲がっている足先は商品価値が無いからである。 アワビのワタ(青い肝臓)もしかり、しびれる毒があるからださない等々。 「夏場になればアワビ以外の赤貝、平貝類はうかつには出さなかった」 昔は8月に使える魚介類が少なく商売にならなかったとか。現在は設備が良くなり旬がなくなっている故に多種類のタネを注文されると、それが無いと言うわけはいかなくなっている
江戸と上方の違い
経済感覚
江戸の庶民は頻発する火事のおかげで、明日の仕事が保証され、日銭が入ってくるので、銭をためる必要が無いから、「宵越の銭はもたない」といい、 「初かつお一本に二両もの金を払うごとく」と食いだおれの点では大阪をしのいでいた。 上方は江戸の人を「明日の活計を知らざるうつけもの」ときめつけた。
魚・貝類
江戸はあさり、はまぐり、ばか貝、さるぼう貝等の貝類は多い 上方は大阪湾、瀬戸内海をひかえており、沿岸漁業の発祥のであり、多彩な魚がとれ、 境、尼崎から市場に来る。
漁法や魚の処理、加工技術等上方起源のものが多いので 魚に関しては大阪のほうが恵まれていた。貝類はとれないので少ない。
刺身
江戸は赤身のまぐろ、かつおを使った。 上方は白身の魚が使われ、たい、さわら等安く、味も良い
寿司
江戸はにぎりずし、巻きずし。 上方は押しずし、箱ずし、ちらしずしに類別される。
笹きり
江戸はすしには熊笹をはさむ 上方は葉蘭を用いる シャリ 江戸は人肌ほど程度の時が食べ時。合わせ酢は塩と酢で砂糖は使わない。 上方は冷めても旨いように昆布、みりんを加えて炊き上げる あわせ酢は酢には塩と砂糖を混ぜる。
あなご・うなぎ
江戸は背開き 上方は腹から開く 干物の魚の開き方 江戸のあじ、さば等は腹から開き、頭を割る。 上方は背開きで、頭は割らない。
たこ
江戸は茹でる 上方は煮る(桜煮)
すしの売り方
江戸ではぼて振りや重ね箱に入れて肩にかけて売り歩いた 上方は自店や屋台で売った。
立食の醍醐味
仕込みには一日かけ、食べるのは一口3秒とはなんとも 贅沢な食べ物だろう・・・。
すしは基本的には客の前で握るライブであり、リアルタイムで供する からこそ、その一貫にかけるのである。 そのためには職人として気の遠くなる様な丁寧な仕事が 求められる。
お客様がのすしをほうばる顔の表情も味覚のライブです。 江戸前の鮨の一貫は料理であり、それぞれの握りに違った味がある。
すしの変遷
何気なしに すしを「江戸前すし」と言う。では「どのようなすしなのか・・」とただすと「東京湾で漁獲された魚介類で握ったすし」「昔のすし」「握りずしの代名詞」等々の答えが返ってくる。間違いではない。 すしに定義づけが必要か否かはさておいて、世界のSUSHIになっている現況を考えると本来「江戸前鮨」とはどんなすしなのか後述してみる。
「鮓」「鮨」「寿司」の意味 「すし」には「鮨」「鮓」「寿司」の3つの表記がある。 鮨のつくりの旨には物を熟成させるという意味がある。 鮓の作は物を薄くはぐという意味です。 鮓は関西地方 鮨は関東地方のすし店で多く使われている。 「寿司」は当て字ですが、江戸末期ころから「寿司」「寿し」の表現が最も親しまれ使われてきた。 寿詞=じゅし ヨゴトと読みます。天皇に捧げる祝い詞で言編を除いたのが司。 すしの文字の違いはあれども、古代のすしは重石で押し、上方は箱・布巾・巻す(スダレ)で押し、江戸前は手で握って押すことで、馴じませるを基本とした点では同じである。
すしはいつの時代からあったのか
●1200年前の奈良時代の近江のフナずしは魚・塩・飯のみで、重石で自然に熟成発酵させて飯をこそげ落として、1年後に魚だけを食べた。
●800年前の鎌倉時代にはアユずし、サバの馴れずしなどは腹にすし飯を詰め、重石をして漬けられていたが糀の作用で発酵を促進され 米の無駄はせず飯が少し酸っぱくなり、魚も乳酸の味が移ったら、それがなま なましいうちに食べる早ずし化が始まった。これをナマナレといいホンナレの対語である。 ナマナレにしたことで、すしはもはや長期保存の意図を欠落させた。 同時にご飯料理になるのもこの時代からでこれも又、すしの歴史の中では特筆されるべき出来事である。
●600年前の室町時代になると南蛮貿易が開幕し、生活様式が変化し食事も2食から3食になり、京都・伏見の米酢は高価ではあったが素材の味と色をなにより大事にする京料理のために、まろやかでやわらかな酢の味わいの酢ができた。米酢は日本ではもっとも歴史が古い酢であり、庶民に普及したのもこの時期であった。
●400年前の安土・桃山時代でもアユずしを豊臣秀吉は朝鮮征伐時に糀の作用で発酵を促進させ製造から10日後の丁度食べ頃に届けさせたとも記されている。 昆布で巻いて、上を竹の皮で包み、布巾で巻き締める京都のサバずしができたのもこの時代。
●350年前の江戸時代には箱に詰めて押し、箱から抜き出して切り分ける手法は大阪では「こけらずし」と称しており米酢により2日間という短時間で食べられる押しずしの完成をみた。
江戸前鮨の考案者は御殿医で順天堂病院の先祖
●340年の江戸初期に町医者の松本善甫(まつもとよしいち) が考案の早鮓は箱や重石に詰めて押すといった従来の方式を改め、手で握る「握り早漬け」の方法である。 世間では待つこと無く直ぐに握れたので「待ちゃれず」と言われた。 松本善甫が御殿医になる十数年前のことである。 この握り早漬けは酢酸臭を混じえており、食酢をうまく使ってすしの熟成期間を早めたのではと考えられる。
松本善甫家は代々れっきとした医者であったのではない。元来が会津天満宮の神官で、争いで人を切り、名を変え大阪へ逃れ、後に江戸へ出た。 この者器用な男で、身すぎ世すぎに医書を何冊かかじっただけで開業したところ、運良く当たって大評判になり繁盛する。 ついに幕府に召し出され第5代将軍綱吉に下級武士として仕えへ元禄6年(1693)には、ついに幕府の御殿医に召し出された。
御典医松本善甫は今日の順天堂病院の先祖にあたる。
松本善甫の会津藩(福島県)藩主保科 正之は第2代将軍徳川秀忠の四男。第3代将軍家光(1623~1651)とは異母兄弟。正之は有能な人物で、さらに家光に忠勤一筋だった。 正之は家光から第4代将軍家綱(1651~1680)の行く末を頼まれ補佐し、 その後、大老にまで上り詰め、幕府の中枢に参画。
保科氏は3代目保科正容のとき松平に改姓し、徳川将軍家親族の名門として名実ともに認められるようになった 会津藩の保科氏の後押しもあり会津藩の松本善甫の子孫は 五代松本興世(1762~1792)天明6年(1786)改易になるまで奥医師(歯科) として仕えた。
江戸前鮨開祖の華屋与兵衛
●200年前の文化・文政年間江戸時代、握り鮨の考案者は松本善甫であるが、 それも酒造メーカーのミツカン酢が「米酢を粕酢にすることができたら、もっとおいしくて手軽なすしがつくれるはずだ」と開発したのが酒粕原料の安価な「赤酢」(あかず)。結果、時間のかかる箱ずしではなく短時間で作れる握りすしが江戸では主流になっていく。
握り鮨を本格的に採用して、繁盛店にしたのが両国回向院前の「與兵衛ずし」の主人華屋与兵衛と深川六軒ぼりの堺屋松五郎「松が鮓」であり、優れた商才、その超繁盛ぶりがすし業界に与えた大きな影響も想像がつくのだが、握りずしの創案者かどうかは明らかでない。しかし、「與兵衛」は「松が鮓」「毛抜き鮓」と並んで江戸の三大すし屋と評判をとり、明治の末まで続いた名店であった。
古い與兵衛鮨の仕事を知るための資料として、與兵衛鮨4代目主人の弟でもある小泉清三郎「俳人小泉迂外(こいずみうがい)が明治43年に記した「家庭の 鮓のつけ方」という本があります。この本の口絵の部分には、明治10年頃、実際に「與兵衛鮨」で握られていた鮨を日本画家の川端玉章が写生した15種類の絵が描かれている。イカの印籠詰め・太巻き(のの字巻)きす、こはだ等のサイズは現在の2倍~3倍の大きさである。
江戸前鮨とは
日本に来る外国人の多くは日本食=和食のイメージとして、スキヤキ、テンプラ、すしを挙げる。しかし、スキヤキは明治の文明開化の産物であり、テンプラは南蛮由来の料理である。すしは奈良時代から魚の保存食から始まり、江戸中期には上方では箱寿司、江戸後期には江戸で握りずしとして、日本の独自の食べ物として生まれている。外国人のイメージとしてこのなかで和食は、と質問すれば何よりすしを挙げるだろう。
お客様に美味しく喜んでもらえる鮨をつくるための、この洗練された加工技術を「江戸前の鮨」といふうに理解して頂けたら良いのではと思います。
江戸時代から大正時代には確かに鮮度保持が難しいという理由で発達した加工技術とはいえ、生では味わえない美味しさが今日いまだに数多く残っている加工技術があるわけです。
江戸前の語源 江戸前という言葉を最初に使ったのはうなぎ屋だった。 徳川家康は江戸の街づくりに取り組み、江戸城の前の浅い海を埋め立てて土地を造成した。その後この沼でたくさんのうなぎが取れるようになった。 武家屋敷の一隅の長屋にいた下層の武士たちは、中間・駕篭かき・槍持ち・奴などである。 生活に困窮していたので内職にも精を出さざるを得なかった。殿様が江戸城に参内すると「下馬先」でたむろしながら待っていなければならなかった。初めは、お茶、麦茶を商った。派手に商売をすれば何時おとがめがあるかわからないので、目立たないよう売りさばいていた。このうなぎに目をつけた下馬先人が、うなぎに味噌をつけてブツ切りにして竹串にさし、焼いて売り大儲けした。江戸(城)前のうなぎの蒲焼の誕生である。
そのうちに、「江戸前」の呼称は江戸の前の海で捕れる魚介類の呼称となった。
「江戸前」という言葉は江戸寿司に象徴されるように威勢のよさや新鮮さを感じさせる即ち「江戸の前の海」を指しています。
佃煮も同様で江戸前の海の小魚を煮て、佃煮とする話しは天正18年(1590年)徳川家康公が江戸へ移り住むようになった頃からといいますから、400年以上もの歴史がある話です。
江戸の漁業と家康 江戸幕府の祖・徳川家康公が生涯忘れることのできない苦難に遭遇した時、佃村の庄屋・森孫右衛門、伊賀の忍者服部半蔵正成、堺の呉服商人茶屋四郎次郎清延3人が家康公を助けた物語は逸話として伝えられています。 そして天正10年(1582年)6月2日の早朝、明智光秀の謀反により本能寺の変が起こり、信長が自刀したのです。
家康は5月に安土城を訪れた後、堺を見物していた。本能寺の変が起こると、堺の朱印船貿易商茶屋四郎次郎清延からの知らせで直接の退路が阻まれていることを知らされ、少人数の武装のない家康一行が、土民が落ち武者にとっていかに脅威にとなるか知り抜いていた。家康は岡崎城へもどることができるか。三河への最短距離である伊賀越えの間道を行くことにしました。
家康は、何度も、「もはやこれまで。腹割さばいて、信長様の後を追う!」とわめいたそうです。その間堺の商人茶屋四郎次郎(大阪府堺市)は土民に金を恵んだり、時には脅したりして、服部半蔵を頭とする伊賀の忍者部隊(三重県伊賀市)にも助けられながら三河へと急いだのである。
一行が、神崎川(大阪市住吉区)にさしかかった時、渡る舟がなかったので焦りました。その時、近くの佃村の庄屋・森孫右衛門は、手持ちの漁船と不漁の時にとかねてより備蓄していた大事な小魚煮を道中食・兵糧として用意しました。一行にとって、佃煮の始まりともいえる佃村の人たちから受けた小魚には、日持ちも良く、体力維持にも素晴らしい効果を発揮しました。佃煮の祖形ともいえる貝や小魚を塩ゆでし干物にした忍者食も伊賀衆と一緒に食べた家康は、佃煮のありがたさを身にしみて感じたのだった。山越えし、やっとのことで三河岡崎城にたどりついたのです。
以来、家康の佃村の人達への信任は、特別強いものになったのです。その後、漁民30余名も、徳川家の御肴役として江戸に移住をさせ、江戸幕府の台所にも自由に出入させ、江戸前の新鮮な魚介類を献上。主として白魚を献上魚とした。残った雑魚を江戸市中で商いし、暮らしを立てていました。当時の佃島は離島でしたから、海が荒れて漁業が出来ない時のために、昔からの生活の知恵で伝承してきた雑魚の保存を醤油炊きしておきました。やがて雑魚だけでなく江戸前の新鮮な白魚やハゼ、小海老などのいろいろな小魚を醤油で煮込み始めました。 佃の漁師は、将軍家の御肴役だけではなく、江戸の人口の激増に伴う町民の食生活を支える大事な漁業者だったのです。
幕府は増え続ける江戸住民のお魚確保のために、従来の漁業者を保護してきましたが、漁獲方法が大変素朴でしたので、需要に追いつきません。そこで幕府は、漁業技術のすぐれた関西の漁民を優遇して、どんどん移住させたのです。この孫右衛門は魚河岸の元となる日本橋魚市場(後に築地に開設)開いたとも言われている。「朝の魚河岸は1日で千両動く」ほどに江戸の中でも大金が動いた。
浅草の海苔 江戸の中期までは江戸の味覚といえば上方(大阪)から「下りもの」で江戸中~後期にかけて江戸の独自のものが、江戸で生まれた。当時は海に近かった浅草を物資の流通拠点としたことから浅草と海苔の関係が生まれる。 上方(大阪)に流通した最初の商品が海苔である。しかし、埋め立てが進むにつれて浅草では海苔の採集ができなくなった。 その後、葛西浦中心に海苔採集がなされた。
寛延2年(1749の263年前)海苔の発生に不可欠な貝類が江戸川の氾濫で埋まってしまい漁具や浮遊物に付着する海苔を採取する漁法はできなくなる。 それ以降の享保ころから始めていた品川に生産地は移る。このころからノリヒビ(木の枝や笹竹を海中に建てて海苔を付け養殖するもの)による養殖が始まり生産量が増大した。 江戸時代末期になると品川の養殖は衰退し中心は大森に移る。生産者の大森の生産者は日本橋ののり商と取引を拡大したので、浅草ののり商人は凋落し、浅草は「あさくさのり」の名前だけを残して脱落する。 需要が庶民に浸透していく手助けは江戸市中を天秤棒で担いで売り歩く「振り売り」であった。
地方に売りに出る「旅師」も、長野県諏訪の人達であった。 山国の諏訪の人たちは厳しい冬を江戸に季節的出稼ぎで海苔を売り歩いた。 のり養殖の技術を地方に持ち出したのも諏訪の人達であった。
江戸式製法が始めて箱根を越えたのは文政2年(190年前)のことであった。(握りずしが考案された時期に重なる) 遠州舞阪の旅籠で始めて生のりを食べた旅師諏訪の百姓、森田屋彦之丞は大森ののりと同じだったので地元に養殖をすすめた。 その後、森田屋は大森から製造法をもらしたと村八分にされ、その後の消息は知る人はいない。
叉、同じ文政2年(190年前)に田中孫七は大森(東京都)の海苔養殖業者で駿河江尻の旅籠 (静岡県静岡市清水区)で三保海苔をたべたところ、大森ののりと同じと判り三保村にまねかれる。同地の遠藤兵蔵らを指導し、文政9年「そだひび法」による海苔の養殖に成功。天保(179年前)年間には清水、江尻にも海苔養殖がひろまった。大森の田中孫七宅は留守宅を壊される仕打ちを受ける。
それほどに江戸湾ののりは閉鎖的な生産、流通のもとで成長してきた。 舞阪、三保の境内で現在も碑が建てられております。
初夏から夏にかけての鮨
江戸前技術で極上の鮨を仕立てる
鮨の握りに「伝統、伝統とこだわりすぎても如何なものか」と思う方がおられることは承知している。鮨も伝統や古い仕事だけでは成り立たなくなっていることも事実です。
歌舞伎役者故18代目中村勘三郎さんは古典的演技を身に着けたうえに現代風歌舞伎を演じ若いフアンの掘り起こしを成し得たからこそ価値があるのです。
鮨屋もある程度は現代社会のニーズに合った技術も必要であり、シフトも必要である。 しかし、根底にある古典的な正統派技法の部分がなおざりになっていたら、それは江戸前鮨とは呼べないのではないか。
お客にしてみれば新鮮だけが売りの店で「美味しい!美味しい!」とたくさん食べても飽きがきて何か物足りなさを感じ取られるのも事実で江戸前の技でこの新鮮な魚介類を食べたら最高の至福ではないか。
「シャリの味付け」「魚介類の締めと漬けの技術」の一体化 「すべてのすしダネに合うシャリ」というものはないでしょう。シャリの味は店それぞれに個性があります。
初夏から盛夏にかけての登場するトロマグロ、アナゴ、シャコ等脂がのった魚介類に相性が良いのは「酢と塩の効いた強めの味」の古典的(東京)なシャリ。
静岡県の鮨屋のシャリは「砂糖を少な目に酢と塩の味」で昆布〆のスズキ、シマアジ、カンパチ等の白身魚やコハダ、アジ、カスゴ、キスなど酢〆の魚に合います。
古典的な技法 5月、6月はすしダネの端境期である。春の魚は旬を過ぎ真夏まではまだ早い。この間のすしダネを取り揃えて「ああッ 旨いなッ!」と声を出させることは難しい。 冷蔵庫がない時代、夏の鮨屋は魚、貝類が少ないので商売にならなかった。
静岡県はマグロを看板にしている鮨屋が多い。マグロの醤油漬けは「ヅケ」と呼称し、古典的な方法としては湯霜(熱湯を表面にかける霜降りのこと)にした後、漬け汁に数時間(店により差異あり)漬け込むのです。ヅケは生とは一味違います。
アナゴには二通りの煮方がある。 東京の高級店では「メソッコ」(小さなアナゴ)を「さわ煮」と呼ばれている煮方で尾尻を折り込むように一本丸ごと一貫づけで握る。 一方、普通の店では一尾を三切れくらいに切る大きさのアナゴをとろけるくらい柔らかくなるまで煮込む「漬け込み」がある。
シャコは水温上昇で江戸前から消えました。蒸し器で少々蒸し、鰹のだしを引いて、そばつゆ程度の「漬け込み汁」に一晩漬け込みますと「こんなに美味しいのか!」と古典的な鮨となる。
江戸時代から千葉県大原で獲れるマダカアワビが最高と呼ばれ現在は幻のアワビとなっているのでクロアワビがすしダネとし主流。蒸したアワビを厚く切らずに薄く切りつける方が香もあり味も良く、生より蒸しアワビの方が好まれ美味しい。
光物の魚と言えば9月~2月までコハダ。3月~4月サヨリ。初夏の5月~6月はキス。真夏の7月~8月はアジであったが最近は季節感が崩れている。 江戸時代コハダ握りは秋から冬の味で夏にコハダを漬ける鮨屋は無かった。 脂がない夏のコハダを冬のコハダのごとく旨みを引き出す古典的な技術・手法を守って包丁目を細やかに入れて、口の中で皮目が柔らかく感じられるように漬けてある鮨屋があること自身珍しくなっている。 現在、皮つきの小アジを酢〆にして甘味のオボロをかませる鮨屋は少なくなった。アジは生で握るのが主流なのでゼンゴを取る技術を今は必要としない。これも時代のニーズであろうか。
クルマエビは茹でたてを甘酢に漬け込み、尾殻は「化粧する」と言い、切り落として握る。
玉子焼きには柏餅のように「かしわづけ」という形でシャリを包んで握る。一方、白身魚や海老、山芋などをすり身にして「カステラ風」に焼き上げて鞍掛けの形で握る玉子焼きがある。
かんぴょう巻は戦前までは三つ切りが普通であった。これを江戸ッ子は遊び言葉でチャンチキ(馬鹿囃しの太鼓の撥になぞられて)と呼んだ。
かっぱ巻、おぼろ巻は合間に食べるお茶うけ代わりの巻きずしで一本を八つに切る(八つにおろす)と約束事になっていた。
技術の発展に貢献は「部屋制度」 昔、鮨屋の調理方法は門外不出で情報が開示されることがなかった。 鮨職人は十歳くらいで丁稚奉公という形で修業に始めた。そして、十年くらい修行して二十歳くらいで一人前の鮨職人になれた。 戦後、兵役を終え職業につけない職人を明治生まれの先駆者たちが今で言う人材派遣会社的な「部屋」制度をつくり職人を必要とする鮨屋に斡旋した。 鮨屋から鮨屋へと職人同士が交流されたことにより技術の伝承と進歩が一気に全国的に広がったのである。
現在でも老舗で名店と言われている鮨屋の先代たちはかってこの部屋に所属をしていたので、江戸前鮨の古典的な正統派技法を今でも正確に守り続けているのである。
歴史から学ぶ基本的姿勢
鮨の伝統と商売とのバランス お客さんが「今日はなにがあるんだい?」「今日はヒラメにタイ、スズキも・・・」「スズキ?時期がはずれているよ」そんなお客が昔はいた。
今はマグロ、アナゴ、アジ、コハダなどは定番タネとして一年中タネケースに置いておかねばならないのは一般的である。
江戸時代コハダ(江戸方言)は下魚であったが酢締めの技術で握りずしの代表的タネになった。コハダの質がいまひとつだったとしても仕入をやめるわけにはいかない。微妙な違いをどこまでも追及し、一年を通じていろいろな漬け方がある。それを決める技術でコハダの鮨を作り続けなければならないのは職人の大切な仕事なのである。
江戸の道具作りの職人は「自分を名指しで注文してくれる人に対して仕事をする」という客へのスタンスや独特なスタイルが今でも根底にある。商人は手広くいろいろな人を相手にするので世辞も愛想も使う。職人と商人の価値観や職業意識は異なるのも事実である。
しかし、現在は伝統一筋ではいけない。職人も伝統を残すために対価を頂き商人(あきんど)としてもお客様が感動する仕事とのバランスをとらねばならない。社会の環境が変わろうとも自分に課せられた仕事を大事にやることの積み重ねが商売の継続であり自分の伝統を築き上げることにもなり得る。しいていえば江戸前鮨の継承にもなる。
江戸前鮨ができる以前の光り物
駿国雑志とは駿河国(静岡県中部)の地誌で旗本阿部正信が江戸時代、文化14年(1817)に駿府に1年間の赴任中に駿河国中を見て回り、調べた資料を元に編集したものである。 鯵(あじ)について「有渡郡廣野村(静岡市駿河区広野 用宗の隣村)の浜には、小鯛、大鯵、雑魚数多かゝる・・・。當國。?(コノシロ)喰ふ者少し、故に多く鯵を鮓(すし)にす・・・。すべて鰹、鯖、鯵等鉑と號て、雲母の如きも皮上にあるは、必毒ありて酔事あり・・・」と記述がある。
海面上層を泳ぐコノシロ、アジ、サバ、イワシ等は水圧を強くうけないので、肉質中に多量の水分が含まれている。陸揚げすると腐敗菌が急激に繁殖する。表面はみずみずしく、新鮮らしく見えても内部は腐り始めている。 すなわちキラキラと光る魚は皮上に毒があるので腐敗し易く腹下しすると言って刺身にして食べることを厳しく戒めている。米酢は高価なので村人は梅酢に漬けたと父から聞いた。
その後、江戸前鮨が始まった文政年間(1818~1830)コハダ、アジ、サバは振り塩、二番酢、本酢で細菌、臭みの除去、たんぱく質を変性させて生とは違った食感となる鮨を作り上げたのである。
ヅケと言えばヒラメかタイ 「駿国雑志よれば文化15年3月(1818)有渡郡下島(静岡市駿河区下島。安倍川の東側)村邊に鮪寄事数百尾、故に生肉を捨て、田間のこやしとせり。是百有餘年の大猟也。云々。」とある。 握りずしがすでに生まれていた、天保年間末(1844)江戸でも鮪(マグロ)の大漁が有り、保存方法が無かったので路上に野積みされた。 そこで馬喰町の屋台店恵比寿鮓が試みたのが生魚に用いていた醤油漬けの調理方法をマグロに試みたまでのことである。
今日、ヅケ(醤油漬)と言えば赤身マグロに限ったように思われていますが「これは甚だ不見識・・・」と「こみあいて待ちくたびれる与兵衛すし客ももろとも手を握りけり」と川柳にもたびたび詠まれた江戸前鮨の開祖華屋與兵衛の晩年の当主は俳人でもあった小泉迂外(清三郎)が明治43年刊「鮓のつけかた」に記述がある
当時、生魚に限っては醤油漬したのでヅケ(漬け)と言えばヒラメとかタイなどであった。これは保存、流通が確立していない時代の話。
「明治期までは、生魚はみな原則として一度酢にくぐらせて、更に醤油をくぐらせたが私見では賛成しかねる。これでは、せっかくの味に傷がつこう・・。」と吉野鮨本店(日本橋)三代目 吉野曻雄氏
その後、古典的仕事としてヒラメやタイ、カレイを薄塩にし、板昆布にはさみ軽く重石をかける。これは空気にふれさせないための工夫であった。それがいつのまにか「こういうふうにすれば美味しいんだ」といっそう美味しく食べるための手段として派生的に昆布締めにかわってきた。
尚、付け加えておきますと「江戸にては、大きなる物をひらめ、小いさなる物をかれいと呼ぶ・・」ヒラメは江戸方言である。 また、マグロも江戸の方言であり、関西地方は奈良時代からマグロ(キハダ)をシビと言った。
切り漬けという仕事 古い調理法の仕事で切りつけしたタネを、醤油、甘酢、生酢などで洗うことを切り漬けといい、アジ、エビなど今でもする仕事で「ヅケ」の一種である。
ヅケの調理法には二種ある。 一つはすしダネを切りつけけしてから漬け込む方法。(元来マグロのヅケとは切り漬けして醤油漬けした) もう一つは魚をある程度の大きさに節どりしたものを、そのまま漬ける(サバ、サワラなど酢漬けが多い。最近はマグロを湯引きする方法がある)
煮きりとつけじょうゆ 江戸時代から「煮キリ」といいまして生醤油に味醂、酒、かつおだし汁などを加え、煮たてて醤油の臭みを飛ばした「煮きり」がよく用いられている。 すしダネの上にぬって「しょうゆはつけなくてもいいですよ」というときに使われているのが「煮切りじゅうゆ」で、マグロのヅケにも使われる。
いまは、握りずしはしょうゆをつけて食べるものとされているが、これは食べ方としても、おかしな話である 全てのタネに手を加え、旨味を引き出す鮨を漬ける日本食の基本である十色の味を一色に近づけて食べるということになり感心できない。 そのことの良し悪しは述べることは出来ないが、江戸前鮨の基本的技術から比較してみますとおろそかになりかけていることが寂しくもある。
食べる人それぞれ好みもあるでしょうが、しょうゆはたっぷりつけずにタネにわずかにつけて、すし飯といっしょにひと口でたべると、しょうゆがすしの味を引き立ててくれるのである。
鮨屋の基本的姿勢
鮨屋という商売は「お客様の好みに合うか合わないか」で成り立っており、 それぞれのお客様によって味覚が違いますので、全ての方にお客様になって頂けるなんて到底無理なことです。 江戸前鮨はこの道の先駆者の方々や、親方、先輩などが試行錯誤の結果出来上がった鮨なのです。 勿論、自分自身はこの習い覚えた古典的な技術、知識が絶対とは申しませんが少なくと、ごひいきになさっていただいているお客様がおられる以上ひたすら教えられたことの繰り返しの仕事をして、商いをさせていただいております。 「あの店でしか食べられない鮨」で商いをするという基本姿勢でなければならないのです。 「立ち食い鮨の魅力は一貫食べるたびに別の食欲が刺激されて、次はなんだろうと期待する。江戸前の鮨には工夫がある。これほど底が深い食べ物は世界中さがしても他には見当たらない・・・」と語った某作家を思い出す。 そんな鮨を漬ける幸せは職人冥利につきよう。
江戸の豊かな食文化と食材
「和食」が無形文化遺産に登録
日本人の命と暮らしを支えてきた「和食」がいま危機にあると言われている。 「和食」が無形文化遺産に登録されたということは、主食であるご飯(コメ)を基本に日本人がその環境のなかで築き上げてきた食の知恵や工夫や慣習。それを編み出した人々など、有形無形のすべてを「和食」と呼び、日本人の伝統的な食文化を総称する言葉で、長年に亘って継承されてきたものだ。 衰退しつつある日本の伝統的な食文化を今後どのように次世代に繋いでいくのか重要である。和食には昔からその時代時代に新しい工夫を伝統に加え次の世代に繋いできた歴史があり、日本の伝統文化を見直すよい機会になる。 それだけではなく、海外から訪れる人たちに日本のよさを知ってもらうことに「和食の文化」が役立ってほしいと思います。 (熊倉功夫静岡文化芸術大学学長の談引用)
すし種と酢飯の基本的味
「漬ける」という用語に古さを感じるが創案期からの鮨には欠かせない魚介類と共に基本的味を創り出す原動力は調味料にある。 それ故に江戸、明治、大正時代と今日の調味料の品質差異はあるけれども先人の知恵や技術、歴史を再認識することはこの際必要と考える。
江戸時代の調味料と輸送の歴史
グルメ時代となった江戸後期には、さまざまな料理が生まれた。食材の充実はもちろんだが、すし調理に欠かせない調味料も飛躍的に発展した。 江戸に人口が集中していくにつれ、米、塩、酒、酢、醤油等は天下の台所大阪に求めることになり、大阪から江戸への商品輸送網が発達。 その輸送手段として、菱垣廻船は大阪から江戸間を半月内かかっていたが鮮度が求められる酒は樽回船が登場2日半で走ったという。 コメの輸送には、利根川の河口の銚子から大川(隅田川)の水運が利用され船によって浅草御蔵に出納された。 醤油の産地は銚子と野田どちらも水運に恵まれていたが江戸まで大量に輸送するのに、銚子は利根川さかのぼり江戸川を下る順路で10~20日かかるのに対し、野田は江戸川を下れば1日で日本橋に着くので差は歴然だった。
江戸時代の米
給金や税金でもあった米は政治経済の根幹としての役割を担っており、大名の身分は米の単位である石高で表されていた。 寛政12年(1800年)に中菰野村(現三重県こもの町)に生まれた佐々木惣吉は、当時の農家の稲作に、この土地に適した稲を作ろうと品種改良に取り組みました。苦心の結果、嘉永元年(1848年)にできあがった関取米は、茎が丈夫で倒れにくく、質も良くおいしい米として受け入れられ、利根川沿いの洪水による凶作に悩まされていた関東平野一帯に関取米を栽培するようになった。とくに東京の「江戸前鮨」では、関取米のにぎりが大好評を得ました。 小売専業の米屋は搗米屋(つきごめや)と呼ばれ、問屋から卸した玄米を精米して一般庶民に販売していた。当時のすし屋も同様に仕入していた。 江戸末期には農業技術が進んだことで生産性も高まり、庶民も「白いお米」を日常的に口にできるようになった。
すし米も二等米、三等米でも炊き方によっては、それなりにいいすし飯になる。 大阪のすし屋は、飯炊きは薪炊き、江戸(東京)は炭炊きであった。 炭炊きの場合はやわらかい炭で火の口の閉じ加減、つまりふかす度合いにより、釜底に焦げ飯ができる位のまでふかしたほうが、うまい飯に仕上がる。 現在の調理器具の目覚ましい進歩と生活環境を考えればいまどき薪で飯を炊くなんて理想的で非能率でもある。ガス釜を使って薪で炊いたのと同じコメを炊くことの研究は日進月歩成果を上げている。 すし職人の多くはすし米の産地、品種にこだわり、考え方を持ちあわせていると聞いている。 私などは長い付き合いの米穀店に任せて、意見はあまり言わない方である。 産地は富山県入善、品種はコシヒカリで古米と新米をブレンドしたすし米だけをお願いしてお任せしている。
新米だけよりも古米を混ぜたほうが握ったときは硬さが保たれ、粘りもあるので、タネとしっかりと馴染む。 又、口の中に入れるとパラパラとほぐれて、旨いすし飯ができる。 TPP参加問題であるが日本のグルーバル戦略を考えるとこの大きな動きは無視することはできないながらもすし屋が必要とする品質条件に見合うすしコメを提供してもらえるのか。 近年、我が国のコメどころで温暖な気象条件により品質に影響が出ていることも事実として受け止めなければならない。 国産米の一辺倒だけが良いのか。時代の変化にシフトしながら店の独自の味というものへの挑戦が商売の基本だけにすし屋のコメに対するこだわりは続くのである。