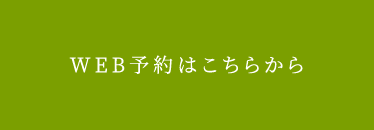鮨を知る
 UOTAKE SUSHI
UOTAKE SUSHI
すしダネの古典的知識

2021年9月18日
かつお下魚扱い
元来すしダネにならない魚として江戸時代から昭和 40年ころまで扱わなかった。 何故だったのだろうか? 江戸っ子好み魚。初カツオを一尾2両(15万円~20万円)でも買ったのにすしダネに用いなかったのは不思議であった。 握りすしが創案された当時は、魚介類は全て塩で〆て、酢、醤油にくぐらせていたので、カツオは変色が早いので無理してすしダネにする必要がなかった。 まぐろと似たカツオは下魚であったからである。
煮いか
ヤリイカ
現在は生で用いられることが多いですが、昔は煮イカをすしダネにした。煮イカのすしダネとして珍重したのはヤリイカです。 弾力のある歯ざわりと、口から鼻に抜ける小イカ独特の香りと味は煮イカの握りずしとしては逸品でした。煮イカに煮ツメを塗って食べるすしは格別美味しいものであります。
残念ながら、すしダネの貯蔵法が不完全なころのすし店の知恵として生まれたもので、現在は冷凍や冷蔵の技術や設備が進み、鮮度の良い状態で貯蔵できる現在では生のイカがすしダネになってしまったのは、時代の流れでしょう。…
スルメイカ
昔はスルメイカ(ジルマイカ)を切りつけた後、甘酢に漬けた酢イカが定番であったが、嗜好の変化でメニューから消えてしまいました。 適度の堅さ(歯応え)が「すし通」には応えられない旨さである。
酢〆キス
縦に幾筋も切り込みをいれて、オボロをはさんで握る。 昔の仕事である
カスゴ
カスゴは光ものとして扱われております。チダイの幼魚である。 カスゴとはカスッコ=末っ子と呼び江戸での方言であり、地方により呼び名はいく通りもあります。 酢〆の中では品の良い魚とされている。
スルメイカとアカイカ
スルメイカ(呼び名ジルマイカイ)
昨今は茹でたイカのご注文が少なくなりました。 当店ではご年配のお客様には根強い人気商品です。 耳タブの硬さ程度に茹でた(茹で過ぎると硬くなる。後に煮立てた煮汁にイカを入れ、 箸でころがして味を整える。 甘い煮ツメをぬって食べる煮いかのすしは格別に美味しい。 スルメイカの場合、生よりも煮たときに味がぐんと増す。 叉、昔は甘酢に漬けた酢イカが定番であったが、嗜好の変化でメニューから消えてしまいました。 当店では酢イカのご注文があれば供します。
江戸のイカ印籠づけ(当店は赤イカも使う)
イカの胴の中に酢飯に甘く煮た五目を混ぜ、詰め込むのである。
五目飯の具(かやく)
椎茸、人参、いなり、昆布、ゴマ、かんぴょうの刻んだものである。 一般的には殆んどみられなくなった仕事である。 関西方面でも印籠ずしと呼んでいるが、江戸では「印籠づけ」 戸細工ずしの一つにで、それなりの評価があった。 作り方は煮イカと同じように煮る。煮立てた煮汁にイカを入れ、箸でころがして味を整える。 丸のイカの胴の口を少し切り、姿を整える。 イカにすし飯を詰める。イカがパンパンに張り切れる位になるまできっちり詰める。 甘い煮ツメをぬって食べるアカイカのすしは柔らかくて懐かしい江戸の鮨です。
節分と恵方巻
節分と巻きずし 恵方巻は当時沢庵を巻いていたとは?
四十四年の節分の日、日本風俗史学会食物史分科会の月次例会の席上、大阪市立博物館の平山敏治郎館長から「ここに来る途中、阿部野橋のすし屋の表に本日巻きずしありという広告を見たが、何のことか知らん」という質問があり、美登利鮓の久保登一氏の返事に、節分に巻きずしを食べる風習は大正の初めにはすでにあった。おもに花街で行われ、ちょうど新こうこうがつかる時期なので、その香の物を芯に巻いたノリ巻きを、切らずに全のまま、恵方のほうに向いて食べる由。老浪華人の塩路吉兆老も今日まで知らなんだ、と言われる。もちろん私も初耳だ。普通の町家ではあまりやらないようだ。全国ではどうであろうか。
恵方巻は当時沢庵を巻いていたとは?篠田統『すしの本』昭和45年6月30日初版より
注)こうこうとは「香の物」の「香」を重ねたもので、この時期の香の物は沢庵漬けをさす。
江戸時代のマグロは下魚
天保の末(西暦1842年)にマグロの大漁があって、そのころまではマグロは魚の中では上等のものとして扱われていなかったので、そのマグロの処置に困って捨てようにも場所がなかった。
そのとき日本橋馬喰町の恵比寿鮨が試みにマグロをタネに使ったところ、江戸ッ子の気風にあって流した。 馬喰町というところは、名のごとく馬喰が大勢いた土地であり、馬喰がいなくなってからは、地方人相手の宿屋が多かったので、諸物の安いものが歓迎され多く売れたため、安しいすしとして恵比寿鮨の主人が売り出したものであろう。
この時代は冷蔵庫の設備がないので鮪の色が変わるので、切りつけしてから醤油の中につけて、亀甲色にして用いたので、鮪のことをヅケ(漬けるの略)という名が出た。
当時、上流家庭に納める鮨には鮪を用いない。御膳ずしと看板をだした店は鮪に代わってタイ、ヒラメの白身の魚を用いている。 ?注)馬喰とは牛を鑑定・見極めて市場へ売りに行く牛の鑑定人、仲買人のこと
注)江戸の魚河岸は日本橋 元禄期(1688~)には日本橋魚市場(後に築地に開設)は活況呈していた。
昼の芝居小屋が集まった芝居町(現在の浅草六丁目付近)、夜の吉原(現在の日本橋人形町)と並 んで「朝の魚河岸は1日で千両動く」ほどに江戸の中でも大金が動いた。
注)江戸時代は、別名で「「シビ」と言う。「死日」に通じることから、いつ命をおとすかもわから ない武士にとって、この名は禁句であった。それゆえにマグロは下賤な食べ物として食べなかった。
湯ぶりと霜ふり
摂氏60度から70度ぐらい熱いと感じる程度の湯をかけるのを「湯ぶり」という。 湯ぶりは少し古い魚、例えばタイ、ヒラメ、スズキといったものでもこれをすると 色艶も格段と良くなり身もしまって味も上がる。 霜ふりは同じ方法だが、これは古くなった魚、マグロ、カツオ、サバといった 類の香の臭いを抜く為に用いられる。
蛤と江戸の海
蛤は形の類似から浜の栗と言い、庶民の馴染みの深い食料でした。
7代将軍家継時代1713~1715年)泉州堺の浦(大阪府堺市)、参州(愛知県東部)、勢州桑名(三重県)が産地として有名であった。 婚礼の蛤の吸い物は実を食べないと言い、婚礼の吸い物は必ず蛤を用いる。
この習慣は8代将軍吉宗(1716~ 1735年)が制定した。「蛤貝は参千世界尋ねても、外蛤貝とは合わぬ者也とかや。他の蛤に合はざるは、外の夫に心かよはさぬ 貞女、両夫には見えざる戒。」とある 蛤の二枚の殻を外しても、他の殻とは絶対合わないから「貞女、両夫にまみえず」といういみになる
当時から江戸の海は浅い為に、蛤、あさり、ばかがい等の二枚貝の潮干狩りの場であった。浅い為に埋め立ての対象となり、嘉永6年(1853年)の黒船騒ぎの結果、台場工事、砲台設置工事に着手し、浅い海域の漁業は影響を受け、海の公害第一号となった。
このように徳川入府以来、江戸の海は埋め立ての歴史であった。
クロアワビの蒸しアワビ
生食用や蒸したりするにはクロアワビやエゾアワビですがすし屋では一般的にはアワビといえばクロアワ ビを指します。 クロアワビで殻が青黒く身が硬い方をアオガイ、殻が赤っぽく身の軟らかい方をビワガイといいます。 すし屋では生食にはアオガイ、酒蒸しにはビワガイを使います。
江戸時代から房総の大原のビワガイは絶品で蒸しアワビには大原おこだわり続けているすし店があります。 すしダネとしては生より仕事をした蒸しアワビの方が好まれるのは昨今同じです。
新子とコハダの語源
漬けかたは200年も変わらず 1、塩と酢で決まる 2、振り塩 3、水洗い(塩出し) 4、二番酢で酢洗い 5、本漬けは一番酢で 。
学問上ではコノシロでコハダは江戸の方言。 出世魚シンコ(新子)は4cm~5cm位 コハダ(小鰭)は 7cm~10cm ナカズミは12cm~13cm位 コノシロは15cm以上 と言われている。
新子 握りは江戸時代には秋の味だった。最近では静岡県の浜名湖から夏には入荷が始まり、 東京湾ものが出始める初秋には初物食いでは無くなって来ている。
コハダ(小鰭)の言い伝え 魚体の表面が柔らかくて光沢があり美しい、子供の肌から子肌(コハダ)と呼ばれた。 又、小さな魚体の表面が江戸時代の江戸火消しや鳶などが浮世絵に描かれている刺青文化の 粋な肌に似ていることから小肌(コハダ)と呼んだ。
学問上の名称はコノシロ(この城) 語呂合わせ、「コノシロを焼く」「コノシロを食う」を「この城を焼く・食う」で武士は 縁起が悪く、「腹切り魚」といって切腹のときに供える魚。 江戸幕府のお膝元ゆえ、江戸の方言のコハダ(小肌・小鰭)にした。
海苔の養殖
江戸中~後期230年前にかけて、江戸の隅田川よりで浅草海苔生まれた。 それ以降の生産地は品川そして品川がが衰退し大森に移る。浅草は「あさくさのり」の名前だけが残った。(ヒビに付いて9月末頃から成長していく)
江戸に季節的出稼ぎで海苔を地方に売りに出たのは長野県諏訪の人達であった。
淡水湖であつた静岡県浜名湖は500年前の明応6年(1498)の大震災以来海とつながり、その頃からすでに、「あさくさのり」が採取されていた。 遠江舞阪の旅籠で始めて生のりを食べた旅師諏訪の百姓、森田屋彦之丞は大森の生のりと同じだったので文政2年(1819)192年前遠江舞阪に養殖をすすめた。 天保年間(1830~1843)181年前には清水、江尻にも海苔養殖がひろまった。 今日のようなにぎりずしになってくる始まりは徳川氏が天下を取ってから、主として駿河(静岡県の遠江・府中地方)、三河(愛知県の岡崎地方)といった家康の権力範囲の東海地方からで、そのころは今日みるような「稲荷ずし」と「巻きずし」とほぼ同じ形のもので、旅行者の携帯用便利食として重宝されていたと伝えられています。
大森の海苔は荒川と多摩川と江戸川という3ツの川の真水が入って、淡水の影響は大きく、それと塩水との混じり具合がいい海苔が繁殖するのに丁度良い条件となっていた。 江戸前の魚貝も美味はこの流入のおかげである。 現在も“本場ブランド”を守り続けている産地は江戸湾千葉県富津岬の内房地区で、上総海苔として人気が高く、香りの点では全国一とも言われます。
魚食文化の歴史
飛鳥時代に「肉食禁止令」がだされ、淡水魚のあゆ、ふなが尊ばれる。奈良時代も水産物の中心は淡水魚であった。海水魚のたい、あわびは重宝された。 魚(な)と菜(な)両方の意味から、酒を飲む時の魚や菜の“つまみ”を呼ぶようになった。最も需要が強かったのは塩さけやさけの卵(イクラ)・氷頭(さけの鼻先の軟骨)で役人の給料として与えられていた。 鎌倉時代でも平安時代と魚食には大きな変化はなかった。 かつをが武士にとっては「勝つ」という語から戦場の門出の魚として縁起が良いとされた。室町時代になると米を常食とする食生活の基本が形成された時代。この時代でも「魚は一番で鳥獣は後。魚の中では鯉が第一。次はすずき」と記されている。 江戸時代初期にはまぐろは下魚(げうお)とされていた。慶長年間(1596~1614)のことを記した『慶長見聞録』に。「シビ(まぐろ)は味わいよからずとて、地下(じげ)の者もくらわず、侍衆は目にも見給わず、 そのうえしびとよぶ声のひびき、死日と聞こえて不吉なりとて祝儀などには沙汰せず」 と書かれている。 江戸時代中期にはくじらが本格的に漁獲され庶民の魚としてはかつお・いわし・にしんが食されていた 江戸時代後期になると海水魚の沿岸漁業が主軸となり、すしダネのひらめ・あなご、小だい・さば・ しらを・こはだ・車えび・あかがい等江戸前鮨には欠かせないすしダネとして漁獲されるようになった。
昔の吹き寄せちらし
明治37年5月刊の「御講汁及馴鮨」に(すし研究に欠くことのできない資料として有名) 「すしとはすべて馴れた味覚の育成を基本として、その製法がなされるべきだ・・・」 明治生まれのすし職人は 「単に鮨飯のうえに具(飯のうえに並べるタネを昔は「 上 ( うわ ) ぶき」といった)をならべるだけの現在のようなちらしに対して、すしか否かの論がでてくるのは当然ともいえる」 すなわち鮨として生まれながら鮨らしからぬものへ変わってしまったことということである。 「やはりちらし類もすしだ、と確信を持って加工材料のタネを散らす(上ぶき)ちらしを創案 されることを願う」 「シャリというものはそのまま食べても美味しくなくてはいけない」魚をのせて美味しいんじゃいけない」
稲荷ずし
稲荷ずしは天保(1830年代)頃名古屋方面で発明された。 棒ずしの変形ともいわれ最初はシャリの上に油揚げをのせたもので、後に袋詰めになった。
当時の発明品で江戸では細長い稲荷すしを包丁で8ツ切りして、ワサビ醤油で食べるという行為は、 魚の姿ずしや棒ずしに通じるところがある。
稲荷ずしの形は東西で違う。東の長野、新潟、静岡、愛知県は中央線で半分の切り、 枕型に飯を詰めるが、西の京都、大阪、奈良、岡山県は対角線に沿って三角形に切り、富士山型に詰める。
四角形の栃木県では「稲荷とは稲の荷物、すなわち米俵の形に仕上げるもの」だという。カンピョウの 産地(昔は大阪難波の木津地方)であることが影響してか、いなりずしをひとつひとつカンピョウで縛った 「俵ずし」である。 すし飯も東は白い飯が普通で、ゴマを入れる。西は五目ずしが混ぜてある。