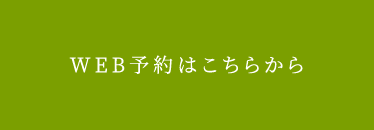鮨を知る
 UOTAKE SUSHI
UOTAKE SUSHI
すしの材料

2021年10月5日
米
すしが作られてきた時代の大半は、おおかたの人にとって米は貴重品であった。それゆえ、多種の米を吟味し、「すしに適する米」を選択するなど行為は、相当時代が下がってからのことである。 文献的には、享和2年(1802)の『名飯部類』が「金谷米または粟野米」とブランドを指定しているのが古い部類に属する。 明治42年(1910)の『家庭 鮓のつけかた』では、「世上でいふやうな鮓米」という表現があり、このころまでには「すしに用いるための米」が成立していることがわかる。ただ、同書は、家庭においてはそのような「鮓米」を用いる必要はなく、「なるべく粒の揃った」ものであることが望ましいけれども、「2等米ないしは3等米でも炊き方によっては用うことができる」と説いている。下準備としては「糠をよくとぎます」ことだと『名飯部類』は説明する。 炊き方 とにかく水加減が大切で、『名飯部類』は「米1升につき水1升、やわらかめのを好む場合はさらに水1合を加える」とある(同書では「塩1合も加えて炊く」と記されているものの、現代、塩を入れてご飯を炊く事例はほとんど確認されない)。『家庭 鮓のつけかた』の方はさらに具体的な解説があり、「新米ならば米1升に水1升、古米ならば水1升1合」とする。また、とぎ置きの場合は水1合を減らすともある。 米の質 好まれる米の質は、すしによって異なるようだ。米は、その水分含有量で硬質米(水分13~14%)と軟質米(水分15~16%)に別れる。時間をかけて相当な圧力を加える箱ずしなどは、軟質米では粒がつぶれてしまうため硬質米が好まれ、逆にわずかな圧力でふわりと仕上げる握りずしなどは、硬質米ではうまくまとまらず、やわらかな軟質米が好まれる。 古米がよい 握りずし屋など早ずしを商う店で「すしにするのは古米がよい」と言われるのは、ひとつにはその方が酢の吸収がよいから。いまひとつは、感想途上の新米では適量の水が一定せず、商売屋ではすっかり乾燥した古米の方が水加減が一定していて都合がよかったからであろう。民間ではそこまでの心遣いが不要だったか、さほど気にされない。むしろ、秋祭りのご馳走として作られる場合は、新たに収穫された新米ですしを作ることで、神への感謝を表現したりその年の恵みを祝ったりしている。 燃料は薪 『家庭 鮓のつけかた』の記事をさらに続ければ、燃料は薪、それも堅い木の薪(常陸産のクヌギの寒伐)がよく、湯炊き(熱湯に米を入れて炊く)法を勧めている。当時(明治末期)は炭炊きカマドガ出てきたらしいが、それならばよけいにに湯炊き法がよいとし、この場合は水をさらに1合増やして(米1升に水2合)、炭は固炭でなく土釜(やわらかい炭)だと焦げにくいという。 今昔、すしご飯の炊き方 各地のすしのご飯は、発酵ずしも早ずしも「普通のご飯どうりに炊く」というのが圧倒的に多く、続いて「やや水を控える」という声が多い。また、黒コンブ(出しコンブ)を入れて炊く人も結構ある、以前ははあまりなされたことではない。 昔の酢合わせ 早ずしであれば、炊き上がったご飯に合わせ酢をうつ。ただ、これも当初のやり方ではない。『名飯部類』では、「酢は飯に混ぜ合わせるものではない」のであって、成形したすしの上からふりかけるものであった。 現今の酢合わせ もちろん今ではご飯に混ぜ合わせることが普通で、これはご飯が炊き上がってすぐの、熱いうちがよい。高温で酢を混ぜたものは飯粒への酢の浸透が活発で、酢の味がいつまでも残りやすい。逆だと酸味が抜けやすい上に、味にムラが生じる。したがって、よく見かける団扇でご飯をあおぐ光景は、あるていどご飯に酢がなじんでから行うべきで、酸味を含んだ熱いご飯を急速に冷やすことで、米粒に艶が出るなどの効果が現れる。
砂糖
昔は砂糖は用いず
本来、合わせ酢には砂糖は用いなかった。早ずしに先んずる発酵ずしが、基本的に塩味だけだったことを考えれば、砂糖は不要のはずで、『家庭 鮓のつけかた』でも、合わせ酢に砂糖の記述はない。合わせ酢に砂糖が入るのが一般的になるのは昭和の戦後のことだとされるが、明治36年(1903)の『食道楽』には、砂糖入りの五目ずしの記事があるから、家庭では甘いすしも出まわっていただろう。 種類や分類に定番なし このように、砂糖の使用自体がさほど長い歴史を持っていない状況であるから、合わせ酢における砂糖の種類や分量には確たる定番がなく、むしろそれは作り手や食べ手ごとの好み委ねられているのが現状である。 現今の関西と関東 関西と関東で味比べするならば、関西のほうがやや甘めであるし、精進物のすしは甘めに、生ぐさ物を使う場合は砂糖は控えるという全般的は傾向はある。 砂糖の効果 砂糖には、すし飯に粘りや艶を与えるという利点もあるし、これを使うことで保存性も高くなる。さらに、砂糖の持つ保水力で、酢をご飯粒につなぎ止めておくという効果もある。
塩
塩が唯一の調味料
発酵ずしの時代から、すしの調味を左右する最大の調味料だった。とくにホンナレや古式ナマナレの場合は、塩だけが唯一の調味料である。同時に、発酵ずしにおいては腐敗防止作用を発揮する。塩分が薄いと腐りやすい上、発酵が進みすぎてすぐに酸っぱくなってしまう。逆に塩分が多いものは、発酵は緩やかであるが、その分、過度の発酵を抑え、それゆえ「食べごろ」の期間が長く持続する。 昔の酢における分量 早ずしの合わせ酢における分量は、『家庭 鮓のつけかた』に「米2升に対し、酢1合、塩1合弱とある。(砂糖は不要)が、これも作り手によって様々であろう。品種は、同書は「ありあわせでよいが、選ぶとするならば新斎というのがよい」としている。「新斎」とは、苦汁の落ちた新しい塩のことで、魚には弱く、ご飯にはよく効くという性質があるという。
醤油
すしの材料としての醤油
すしの材料としての醤油は、混ぜずしの具を煮つける時などに使う場合と、握りずしのつけ醤油として使う場合が考えられる。前者の場合は、ほとんどが家庭料理であるので、品質やブランドはあまり問題にはされないようだ。概して、その家の煮物を使う醤油がそのまま使われる。
つけ醤油
握りずし屋では、つけ醤油は客の舌に直接触れるため、相当の気を使う。『家庭 鮓のつけかた』では「亀甲萬・山サ・ヒゲ田・山十」などのメーカー名を挙げている。かっての醤油はカビが生え、そのため使用前にこれを漉して取らねばならなかったが、現在ではまずその要はない。また、クセが強かったためか、生醤油のままつけさせるよりは、味醂やカツヲのだし汁等ともに煮て醤油の臭みを飛ばした「煮切り」がよく用いられた。
酢
古来の酢の製法
「名酢」
一部の改良型ナマナレを除いては、酢は発酵ずしには使用せず、基本的に早ずしの調味料である。すしに酢を使用するのは、文献上で江戸時代初期の『料理塩梅集』(寛文8年<1668>)あたりまでさかのぼれる。そこには酢によって酸味を補助しようとする発酵ずし(改良型ナマナレ)の記事がある。 当時の酢は、日本酒をさらに寝かせて酢酸発酵をさせたものであった。これが古来の製法であるが、時間がかかる上にコスト高でもあった。「名酢」の誉れ高かった相州中原の中原は熟成に1年を要したと記録がある。
「万年酢」
そこで後には、酒と酢と水を合成して酢を作っておき、抜き取った分だけ酒を補充して全体が酢になるのを待つという「万年酢」(これならば1週間~ひと月で酢ができる)が考案された。 江戸後期の需要 酢は食用ばかりでなく医療用・産業用(染め物の定着剤)にも使用され、その需要が上がった。さらにそのころから都市部でのグルメ化が始まり、食用としての酢も不足がちになる始末であった。皮肉なことに、発酵ずしは相当に廃れ、すしに酢を使うことがあたりまえになっていた時代のことである。
中埜の「粕酢」
享和3年(1803)、それまで見過ごされていた酒の副産物である酒粕を利用して酢を作ることに成功し、これを大々的に売り出したのが尾張半田の中埜又左衛門である。中埜の粕酢は、それまでの酢が非食用へと流用されたために手薄となっていた食用酢の供給をカバーするかたちで市場に出まわった。独特の甘味があり、「赤酢」の名でも親しまれた。当時出始めていたさまざまな種類の早ずしは、当然ながらこの粕酢の供給に後押しされろかたちで世に現れた。したがって、「早ずしには粕酢」という評判が出るに至る。それからしばらくして、江戸前握りずしが売り出され、好評を得た。このことが粕酢の生産発展に拍車をかけたことは言うまでもない。こういう理由で、握りずし職人の中には今も「中埜粕酢」の信奉者は多く、「すし飯がほんのり赤いのが本来のシャリ」という人もいる。 近代は合成酢が台頭 こうした事情であるから、「すしに相性のよい酢は?」と問われば、「当初からなじんできた」という理由で「粕酢」と答えざるを得ない。けれども、実情はなかなか簡単にはかたづかない。これら酒や酒粕を元に作る醸造酢に対して、近代になって台頭したのが、木材乾溜で生ずる酢酸を水で希釈した合成酢である。自然発酵に頼らず科学的に作り出すことができるため、できあがりはすこぶる早く、それゆえ安い。この合成酢の普及は著しかった。時代的なものもあるだろうが、「氷酢酸(合成酢の結晶)を水で薄めるのが『正統』な酢だ」と思っている人すらある。 本醸造酢より合成酢に軍配? 舌の慣れとは恐ろしいもので、ひとたび慣れてしまうとなかなか別の味になじめない。合成酢は香りも味も醸造酢とは格段の差があるのだが、その合成酢の馴れ化した人には醸造酢の味が気に入らない。どんなに高価な本醸造の酢をもってしても、「この方がおいしい」と合成酢に軍配を上げる人もいるのである。
「酢ごろし」「酢にごし」
酢はご飯に合わせるのみならず、魚身を締める時にも用いられる。魚を酢で締めることを「酢でころす」「酢ごろし」という。その酢をご飯に混ぜ合わせる場合は「酢にごし」とも言う、魚の旨味が出て、さらに美味しいすし飯になると喜ぶ地方もある。
海苔
昔は江戸湾産の浅草海苔
全国の海苔巻ずしに使用される海苔の大半はウシケノリ科のアマノリで、俗に言う浅草海苔である。浅草海苔は江戸湾の品川・大森で採り、浅草で漉き(すき)上げたのでこの名がある。すしにはこの江戸湾産が極上であり、季節は冬場が旬で、12月の新海苔は若干薄いので、1月・2月の海苔が最も美味だと「通人」は喜んだ。中でも旧暦の正月15日と26日に採った海苔は、香りが最もよいとされていた。 現今は養殖と輸入品 もっとも現在では東京湾産の海苔など幻の品で、もっぱら輸入物に頼っていることは周知の事実であろう。養殖が進んでおり、海苔の旬を肌で感ずる人もいなくなった。 海苔の良否 海苔選びは、まず外見で判断する。艶のないものは1日でサッと干し上げなかったもの、表面に傷のあるものは干し上げの途中で雨に打たれたものだといい、とにかく黒くて艶のある海苔が最上の条件である。紫がかかったのは湿気ている証拠であるし、手にザラつくのもよくない。また、透かしてみて漉き(すき)ムラのないことも大切である。 香りを重視する職人 江戸前の巻ずしは、海苔を焼いて香りをたたせてから使う。この場合は、2枚の海苔の裏面を重ねあわせ、炭火で、両面を、最初は遠火で、だんだん近火にしてあぶるとよい。海苔の香りを重視する職人は、むろん、客の注文を受けてから焼いたものであった。
わさび
わさびと握りずしの出会い
1820年つまり文政3年ごろ江戸に華屋与兵衛という人が、コハダや海老などをにぎり、そこにわさびをちょっと入れてみたところ評判になったというのです。それが握りずしとわさびの出会いとすれば、その歴史は184年しか経っていないのです。 それも20年ほど後の天保年間(1830~1844)の改革時期に姿を消しました。 徳川幕府の財政改革などで評判の高かった華屋与兵衛のわさび入り寿司は贅沢品として取締りの対象になり、華屋与兵衛は軟禁の刑に処されました。そしてわさび入りの寿司は明治維新後に復活して全国的に広がったのです。姿ずしにワサビ入れ大評判 文化文政のころの狂歌に「伊豆わさび 隠しに入れて 人までも 泣かす安宅の 丸漬けのすし」というのがある。「安宅」とは江戸深川の地名で、そのあたりにあった「いさごずし」(浄瑠璃の「安宅の松」と店主松五郎の名にちなんで「松がずし」と通称された)のこと。「丸漬けのすし」とは姿ずしであろう。同店でワサビを入れた姿ずしが評判になっていたことがうかがわせる。しかしながら、一般には姿ずしにワサビを使うことはほとんどなく、ワサビはもっぱら江戸前握りずしで使われるものとなっている。 生魚の毒消し ワサビは元来は不可欠なものではなかった。
『守貞漫稿』(嘉永2年<1849>は、幕末の握りずしのうち、刺身(マグロ)とコハダを乗せる時のみワサビをはさむと注釈している。ともに生の魚で、他のすしダネが魚と言えど加熱加工してあったことを考えると、ワサビには生魚には毒消しとしての作用が担わされていたことが憶測される。ワサビ選びと使い方 握りずし屋のワサビは伊豆甘木のの山河由とされてきた。また、俗に言う「すし屋もワサビ3年」とは、もちろんワサビ選びや使いこなしがいかに難しいかを示すものであるが、すしには3年もののワサビがよく使われてきたことをかけてもいる。春花が咲く前の冬採れワサビが最も辛味が勝ると言われ、黒シミのないものを、首の方から、細かなおろし板でおろすとよい。ねっとりとしたクリーム状になったものをさらに包丁でたたくと香りも辛味も倍増する。 ワサビは醤油に溶かさず 「すし通」(昭和5年<1930>)では、「よいものをうまくおろしたワサビは、醤油に入れてもなかなか溶けない」と論じているが、ワサビは醤油に溶くと香りも辛味も失せてしまう。したがって、刺身を食べるときでも、身の片側にワサビを、反対側に醤油をつけて食べる。江戸前握りずしのワサビ すしダネ内側にワサビをしのばせた握りずしは、実に理にかなった体裁をしていると言える。 粉ワサビが主流 大正のころから、ワサビダイコン(ホースラディッシュ)を使った粉ワサビが登場した。辛味は本ワサビに負けないものの、辛味の質が違っていて、まろみに欠ける。また香りは比較にならないほど乏しい。けれども、その手軽さから一躍時代の寵児となり、今や握りずしの辛味はほぼこれが主流を占める。その味に慣らされた結果であろうか、握りずしには本ワサビよりむしろ粉ワサビの方がよいとする声すらある。 本ワサビはすしの味に邪魔 本ワサビでは香りが立ちすぎて、すし本来の味を楽しむに邪魔になるというのがその理由である。