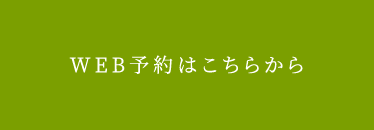鮨を知る
 UOTAKE SUSHI
UOTAKE SUSHI
すしの種類

2021年9月28日
馴れずし
日本最古の近江のフナずし
滋賀県琵琶湖岸一円、ことに湖東、湖北に多いのが、鮒ずしである。
滋賀県「の琵琶湖周辺で漁獲されてたニゴロブナが最近ではめっきり数が減った。
ニゴロブナをはじめとする湖魚が減った原因のひとつは、護岸工事である。
高度成長期、岸辺に茂るヨシの群生はなぎ倒され、冷たい近代的人工岸になり変わっていった。
このヨシ地の根元で魚が産卵し、稚魚が育つ事を忘れていたか、あるいは知 っていながら無視したか。
ともあれ、湖岸はコンクリートで固められ、それとともに湖魚の数は激減した。
無リン洗剤を使うなどして、県民あげて、汚れきった琵琶湖水を浄化した実績はよく知られているが、ヨシ地への関心はでおくれた感がある。 事態を重視した滋賀県が、遅まきながらようやくヨシ地の復元に着手したのは最近のことである。
何十年か後、琵琶湖もかってのように湖魚が群れをなすようになるかもしれない。そうなれば、フナずしも今のような贅沢品ではなく、それこそ以前と同じく「ドーンとつくって、来客にふるまう」ことができるようになるだろうと見る人がいる。昨今の値上がりが原因か、独特の風味を持つフナずしを食べられない(嗜好に合わない)県民が増えているのである。食べ慣れてないからであろう、それは、とくに若い人に多い。
ひとたびフナずしを忘れてしまった人、あるいは、フナずしを知らずに育った人が、琵琶湖にニゴロブナが戻ってきたからといって、急にフナずしを食べるようになるだろうか 味覚嗜好というのは、そうゆうものではなかろう。
「人々の生活から 乖離しかかってるフナずしの伝統を守るためには、次代を担う子供たちにこの味を好きになってもらわねばならない。
学校給食でこれを出したらどうか」あるシンポジウムでこんな発言が出た際、会場から少なからぬ失笑がわいたが、私は真面目にうなずいていたものである。
鮒ずしの漬け方
前処理
うろこをこそげる。ついでにえらをとり、えらぶたのところから太い針金を差し込んで ワタ、浮袋、胆嚢などをからめるようにして抜き取る。
塩切り
ワタを抜いた腹の中へえらのところからギュウギュウ塩を押し込み、ついでに、すし桶に塩、魚、塩と交互に詰め、強く重石する。塩切り期間は十日から一ヶ月というのが普通。 すし飯は硬めがよい。経済の許す限り飯は多い方がいいらしい。昔は白米のほかに玄米や種々の雑穀、ことにアワがよく用いられた。戦時中は米が不自由だったので、もち米、アワ、麦、馬鈴薯などを試みだが、尋常の米の場合と比べて、すしの出来ばえには大して差はなかった。
塩出し
本漬に先だち塩鮒を十五分から二時間ほど水に漬けて塩出しをする。
本漬け
すし桶は口から底までまったく同じひろさの木桶で、中蓋に重石をすると、水が上がるに従って蓋はまっすぐ下へしたがってゆく。 すし桶に飯を敷き、その上に魚、また飯、魚と交互に漬けてゆく、魚同志が接触しないように、しかも出来るだけ沢山詰めるようというのだから、漬け込みにも相当の技術が要る。
最後に、最上層部には厚い目に飯を敷き、竹の皮をかぶせ、わらで作った帯を巻きつけた中蓋をキチンとはめ、出来るだけ重い重石をする。一日押して落ち着いたならば、蓋の上に淡水や塩水を張る場合が多い。
水を張る代わりにすし桶全体を池や川の中に沈めてしまう場合もある。一つには上がってきた生臭い水を洗い渡すためであり、一つには空気を遮断して好気的な酪酸発酵をおさえ、嫌気性の乳酸発酵を助けるためである。
桶に水を張らないでも、日がたてば重石は次第に桶の中に沈み、蓋の上に水が上 がってくる事は尋常の漬物と同じ理屈だ。ただ、この水はいわば米と魚肉とのエキスなのだから、いい加減生臭いうえに、季節が夏の土用とくるので蝿がつく、蛆もわく、 腥臭、酸臭、腐敗臭が混じりあって何ともいえない異臭を発散することになる。結局、はじめから張り水をして、水は何度も変えるのが安全、ということになる。
漬込期間
小型のガンゾだと七月に漬けて十月にははやくも食べられる。220gから300gのも> のでも正月には骨まで軟らかくなる。
年がかりでつくる近江のフナずし
魚・飯・塩のみを発酵させて酸味を得、飯は除いて、魚だけを食べる。これをホンナレ という。古代日本のすしがそういう形態とすれば、その当時の姿をとどめているのは、滋賀県の琵琶湖周辺でつくられているフナずしである。
米原や大津など滋賀県内の主要駅の売店で、フナずしを売っているのを見かけることがある。昼食に食べようとこれを買い、車中で包みを開けたところ、中から出てきたはおよそすしのイメージとはかけ離れたもの。周囲は強烈なにおいが充満し、あわてて「腐っている」とばかりに、窓からこれを投げ捨てた人がいるという笑い話が伝わっている。むろん、腐っているわけではない。これがフナずしなのである。
春、琵琶湖の水もぬるむころ、人々はこぞってニゴロブナなるフナを捕る。フナとはいいながらコイと見まちがうような大きさニゴロとは「五郎(=コイ)に似ている」ところから名ずけられたという説がある。
腹の中にも、エラからしっかり塩を詰める。これを桶に入れ、重石をかけること約3ヶ月。フナは塩漬けにされてコチコチになる。夏、土用の頃、塩きりされたフナをよく水洗いし、さらに水に浸けて塩出しする。このときの塩気の残し加減が、フナずしの仕上がりの味を決定する。長年の勘がモノをいう世界である。
フナに、こんどは飯を詰め、桶の中に並べてゆく。フナとフナのあいだにも飯を置き、 フナはまさに内外両面から飯ではさまれる。 桶にフナがいっぱいになると、落としぶたをし、しっかり重石をかけ、念入りにする場合は落しぶたの上に水を張って桶の中と外気とを遮断する。
こうして、桶を涼しいところに置いて、フナと飯を発酵させる。どうにか食べられるようになるのは、年末。正月用に蓋を開けるので、つくってからたべられるまでに1年近くかけているわけである。
同じ滋賀県内でも、地域によって漬けるフナの種類には若干の違いがある。 しかし、味といい見栄えといい、やはり主流はニコロブナだ。そのニコロブナが、最近ではめっきり数が減った。かっては土用ともなれば、どこの家庭でもすし桶を洗う光景が見られたものだが、フナそのものが貴重となってしまった今日は、なかなかそうもいかない。昔を思い出してつけたはいいが、フナずし一桶にかかった費用は10万円。一尾あたり、数千円の原価となる
生成
鮒ずしが完全に馴れるには一年近くもかかる。世の中が忙しくなると、とうていそれまで待ちきれないし、それに米の無駄があまりにも多いのは、米食い虫の日本人にはちょっと我慢できかねる。かくて、飯がある程度酸くなり、魚にもソコソコ乳酸の味が移ったら、まだそれがなまなましいうちに食べる。ということが始まった。室町の中期かと思われる。室町人はそれを生成と呼んだ。生ま馴れの当て字である。
和歌山県有田、日高両郡、および熊野地方に行なわれる馴れずしで、サバが主である。また滋賀県の〆ずしは、湖南に多く、材料としてモロコ、小アユ、オイカワなどを使う。兵庫県西部で行なわれるているツナズシは、他見にも少々見受けられる。アユずしは全国的に行なわれており漸次早ずじ化しつつある。
中世も室町時代になると、すしに関する文献が多く残っているすしという食べ物に大きな変革があったことを伝えてくれる。例えば、文明 5年18(1473)年に記された「蜷川親元日記」に数件見られる「生成」。ナマナレもしくはナマナリと訓ずるこのすしこそ、古代のすしの概念を一変させるものであった。ナマナレとはナレ(発酵)がナマナマしいところから命名されたのであろう。発酵が浅いすしのことである。
ナマナレがもつもうひとつの特徴として、飯を食用とすることがあげられる。 ナマナレを発生させたものは、いったい何だったのであろう。 ひとつには、長期間の発酵を待ちきれなかったのが、発酵を浅くした理由であろう。
しかしそれ以上に大きい要因としてはたらいたのは、飯を捨てる事への抵抗感ではなかっただろうか。平安期の荘園開発、鎌倉期の農具農法改革を経て、この時期、食料生産はかなり向上を見ていた。コメなる食べ物も、一部貴人から、より下層な階級へと普及した。それらの人々が米を無駄にする事をためらったのであろう。飯もいっしょに食べるためには必要以上の臭気が付されることは望まれない。
ナマナレの世界
そこそこの酸味が出ればそこで発酵を止め、結果、ナレのナマナマしいすしを食べるようになったのではないだろうか。 以上、馴れずし、生成を通じ、すし飯の硬さは、あるいは硬めといい、あるいは軟らかめと伝えている。馴れの過程において異常発酵を防ぐには米粒間の間隔が少ない方がいいはずだ。漬け込み期間の短い場合は軟らかめが多く、十分時間をかけ得る場合は(飯のおいしい)硬めとなっているようにみえる。 中世も室町時代になると、すしに関する文献が多く残っている。 すしという食べ物に大きな変革があったことを伝えてくれる。
例えば、文明5年~18年に記された「蜷川親元日記」に数件見られる「生成」。
ナマナレもしくはナマナリと訓ずるこのすしこそ、古代のすしの概念を一変させる ものであった。 そこそこの酸味が出ればそこで発酵を止め、結果、ナレのナマナマしいすしを食べるようになったのではないだろうか。
以上、馴れずし、生成を通じ、すし飯の硬さは、あるいは硬めといい、あるいは軟らかめと伝えている。
馴れの過程において異常発酵を防ぐには米粒間の間隔が少ない方がいいはずだ。漬け込み期間の短い場合は軟らかめが多く、十分時間をかけ得る場合は(飯のおいしい)硬めとなっているようにみえる。 ナマナレとはナレ(発酵)がナマナマしいところから命名されたのであろう。 発酵が浅いすしのことである。
ナマナレがもつもうひとつの特徴として、飯を食用とすることがあげられる。 そこそこの酸味が出ればそこで発酵を止め、結果、ナレのナマナマしいすしを食べるようになったのではないだろうか。
ひとつには、長期間の発酵を待ちきれなかったのが、発酵を浅くした理由であろう。 しかしそれ以上に大きい要因としてはたらいたのは、飯を捨てる事への抵抗感ではなかっただろうか。 平安期の荘園開発、鎌倉期の農具農法改革を経て、この時期、食料生産はかなり 向上を見ていた。コメなる食べ物も、一部貴人から、より下層な階級へと普及した。
それらの人々が米を無駄にする事をためらったのであろう。 生成を通じ、すし飯の硬さは、あるいは硬めといい、あるいは軟らかめと伝えている。馴れの過程において異常発酵を防ぐには米粒間の間隔が少ない方がいいはずだ。漬け込み期間の短い場合は軟らかめが多く、十分時間をかけ得る場合は(飯のおいしい)硬めとなっているようにみえる。
いずし
滋賀、岐阜、福井三県の山間から、富山、新潟方面で行なわれているねずし、大根ずじ加賀の蕪ずしなどがこれにはいる。このほか、秋田地方のハタハタずし、青森から北海道へかけてのいずし、備後因の島のしばずしがある野菜を混ぜる発酵ずし
1. 発酵ずしの中にはダイコンやニンジンなどの野菜をいっしょに漬けるものがある。「魚・飯・塩・糀・野菜」の材料をもつ発酵ずしは、北海道から東北地方で使われる名称をとって、すし研究においてはイズシと呼ばれる。 イズシは、わが国の発酵ずしの中では比較的明確な分布領域をもっており、それは北海道から東北地方の日本海側を経て北陸地方にまでおよぶ。 また、日本海を隔てた対岸・朝鮮半島の東海岸にも魚と飯と塩と野菜と香辛材に発酵促進剤(糀ではなく麦芽)を加えてつくる、まさにイズシと酷似した材料構成をもつ「シッヘ」なる発酵食品がある。イズシは、いわば「環日本海文化」と呼びたくなるような広がりをもっている。
2. これらの地域で見られるイズシには、材料構成だけではなく、もうひとつの共通点がある。 正月料理を中心とする冬場の料理であるということだ。シッヘもまたしかりである。
3. 厳寒の冬の日本海のイメージが強いためか、イズシは寒いところの料理という印象がもたれている。そしてそのことは、ひとつの仮説(俗説)を生み出した。
すなわち、寒い地域においては古式ナマナレの製法・材料で十分な発酵を得ることはできず(低温だと発酵は抑制される)、これらの地域に伝播する過程で、発酵促進剤を加味するようになったのがイズシだというのである。 しかしながら、この説にもウィークポイントがあり、残念ながらイズシの製法を記した中世以前の文献がなく、その成立時期すらわからない状態なのである。
北陸のすし
1. 蕪ずしは正月用に家庭では漬けるし、市場にも出る。あまり長く漬けておくと「酸くなるからいけない」という。酸くないすしなんてあるのだろうか。とにかくブリのだし、糀の甘味、蕪の香り、それにほんのりと酸味が加わり、すこぶるおいしいものではある。
2. 加賀の蕪ずしの作り方
大ぶりの蕪を塩に漬け、ついで水をよく切る。厚さ1cmぐらいに輪切りにし、さらに平たく包丁を入れ、薄く切った塩ブリの身をはさみ、糀に漬ける。色どりに、花型に切った人参や昆布、ヒジキなどをそえる。
秋田のハタハタずし
1. このいずしの系統で有名なのが秋田のハタハタずしである。これには全ずし(まるずし)と切りずしとがあり、前処置が若干違う。
2. ハタハタ全ずしの作り方 近江の鮒ずしのように魚のえらをのぞき、針金でワタを引き抜いた後、全魚のまま4,5日水に漬けて(毎日3回水を替える)血を出し、糀、飯、塩と一緒に漬け込む。
重石して1カ月置く。正月用だ
3. ハタハタきりずし ハタハタを四つ切り、血出しして、右同様1カ月押す。だいたい、魚一貫目につき糀、 米おのおの八合から一升、塩一合。短冊に切った蕪か大根を150匁から200匁。
花形にぬいた人参600匁。そのほか好みにより唐辛子、生姜、昆布、青海苔など も混ぜる。すし桶につける際、一重ごとに笹の葉で区切りをつける
姿ずし・棒ずし
京都を中心に、中国の山間部、四国方面へと広く分布しているサバずし、その変形である大阪のバッテラがある。また、大阪、和歌山の小鯛ずじ、吉野の釣り瓶ずしもこれにはいる。結局、生成に似ているが、魚、飯、またはその両方に酢を当てて一両日漬け込むもの、ないしは即席にも用いるものをさす。古風な馴れずしから近代的な早ずしへ移る最初の群であって、時には生成同様馴れずしとも呼ばれている。一般に、各地のアユ、ツナシの生成は、今日大方この姿ずし、棒ずじの形になってきている。
サバずし
サバずしは京都のシンボルだ。だいたい、サバの一番おいしいのは申すまでもなく秋で、夏には脂が抜けるからアジのすしの方がおいいしいのに、7月の祇園会までも、京都人はサバでないと承知しない。
サバずしは京都の業者ならどこでも作っている。寺町二条の「末広」も老舗だが、ここには他国にも名が通っている祇園富永町の「いづう」の漬け方を紹介しよう。
京都のサバずしの作り方
昔は若狭の浜で塩をしたサバを使ったが、今日は生サバが自由に入るのでこれを昔の加減に塩きりする。季節や魚の大きさによりその時間は2時間から7時間と区々だ。夏分は若狭ものが脂がのりすぎるので静岡県焼津ものを使う。200匁くらいのを3枚に卸し、毛抜きで小骨を抜いて、酢で締め、身の厚いところをはいで尾のところへ添え、細長く長方形に形を整える。米は良質の江州米、酢は米酢の桜戸を用いる。昆布と鰹節のダシで飯を(サバ1本につき2合の割で)硬めに炊いき、熱いうちに酢、塩、砂糖(氷砂糖をシロップにしておいて)を合わせる。
「いづう」ではふきんでギュッと締めるだけだが、普通の家庭ではこれをすし箱に並べ、重石をして少なくとも一夜は置く。古風な家庭なら4,5日はつけておいたものだ。近頃は世の中がせわしくなったのか、即座に食べるのもはやっているようだが、やはり、一夜は押さないと本当の味が出てこない。
バッテラの由来
明治27,8年ごろ、大阪湾でツナシ(コノシロの1年子)が沢山とれたことがある。これを順慶町の「鮓常」というのが安く仕入れ、2枚に卸して全身をつけたが、尻尾がピンと張ってボートに似ていたのでお客がバッテラ(オランダ語でボートの義)と名づけた。のち、ツナシが値上がりしたのでサバに変えたのが今日大阪名物となったバッテラである
バッテラの作り方
新しいサバ100匁から150匁くらいを3枚に卸し、腹骨を去り、強い塩に7,8時間あて、水洗いする。酢で締め、中骨や薄皮をはいで薄く4,5枚にそぐ。バッテラ型に入れ、1本につき7,8勺の飯をのせ、上から押して下へぬく。普通バランを添える。
アユずし
岐阜のアユずじサバずしにまけず古い姿ずしにアユずしがある。中でも有名なのが、大和下市の釣瓶ずしで、歌舞伎の義経千本桜で先刻おなじみの品である。
だいたい、吉野のアユずしは古く延喜式にも見え、早くから京都に貢納されている。降って戦国期の歌人三条西実の日記にも吉野ずしの名は見え、明応5 (1496)年の「書言字考節用集」にはじめて釣瓶ずしの名が出てくる。
現在吉野下市に「宅田弥助」という店がある。現当主より約20代前、徳川3代将軍の寛永まではさかのぼれた。 近畿の在方の旧家でも元禄までたどりつくのは珍しい。それが寛永とは、おそろしく古いすし屋である。
釣り瓶ずしの作り方
アユは腹で開き、えらや中骨を除き、30分ほど塩切りする。水洗いして身が白くなるまで酢につける。腹にすし飯を詰め、桶に笹の葉を敷きつめて笹で覆いして重石する。別に板ではさんで籐つるで硬くしめる方法もある。板締めの締め方は相伝で、それを覚えるのが子供のときの「悩み」の一つだったと言う。酢と重石のとの関係で指定の日時に馴れるようにするが七日、十日という長いのはあまり作らない。この鮓桶の形から釣瓶ずしの名が出たわけだ。
大阪の雀ずし
大阪の雀ずしも古い。本来は江鮒、すなわちイナで作り、腹に飯をいっぱい詰め、ヒレをちょっと張ったところが雀の飛ぶ形に似ていたので、この名がある。 今日、小鯛雀ずしで売り出している「鮨萬」はもとは魚屋で、天明元 1781年仙洞御所御用をつとめることになった折、江鮒は生臭く、かつ皮が硬いので、初めて小鯛で漬けだしたのだという。「鮨萬」で苦労しているのは、鯛の赤さを残すことだそうだ。今日は昔のように小鯛はそうそう手に入らず、中鯛をコケラに使っているわけだが、知られている通り、酢が十分きけば身は白くなる。きかなければ腐る。苦労の甲斐が合って現在色はよく残っている。 料理屋で三代続くのは珍しいが、すし屋では長く伝わるのが多い。商売が小さいから儲けが少ない代わりに大きな穴もあかんからだろう。筆頭がこの「鮨萬」で、吉野の「弥助」ほどにはいかないが、魚屋を始めたのが承応2( 1652年、すし屋に転向してから現当主で七代になる。何も古いばかりが能ではないが、一つの商売で長続きするのはよそにない何かがあるのだろう。
北陸のマスずし
富山のマスずしは駅売りもあり、近年非常に有名になった。元来享保のころ藩主吉村新八の考案と伝え、旧幕時代は藩公の贈答用品として重宝がれたそうだ。
マスすしの作り方
初夏に神通川の盛りのマスをとり、三枚に卸し、薄い切り身にして2,30分塩切りする。水洗いして、酢に10分から15分当てる。酢が長すぎると身が白くなって薄きたない。
白米(もち米一割くらい混ぜる人もある)を硬めに炊き、扇風機で冷ましながら酢をうつ。うち酢は米一升につき酢を丼半分(1.3合くらい)、砂糖、食塩を共に大きく一つまみ(20匁余)および味の素少々合わせたものである。土用にとっておいた笹の葉のかわいたのを5分ばかり熱湯を潜らせて戻し水につけて冷ます。折に笹、魚、飯と重ねて詰め、はみ出している笹の葉を飯しの上に折返し、中蓋をする。7,8貫の重石をする。
小鯛の場合と同じく酢で魚肉が白っぽくなるのには閉口とみえ、「現在神通川のでは到底足りなし、江州醒ケ井の養殖ものは色が浅くて駄目だ。身の真っ赤なマスを求めている。
飯ずし
「御湯殿の上の日記」に時々見える「ならのすもじ」、すなわち奈良の飯ずしはどんなものだったろう。毎年藤の花が咲くころの本願寺から禁裏rへ献上したという六条(本願寺は六条通りに面している。京の人は、だから、本願寺をば六条サンと呼んだものだ)の飯ずしも詳しいことはわからない。
しかし其角の句
◆飯野の鱧なつかしき都かな
でもわかるように、すし飯を主体に、上に魚肉を貼ったものであることは想像される。 今日の大阪風の箱ずし、和歌山のコケラずし、鏡ずし各地の魚ずしの類とほど近いものである。
大阪の箱ずし
大阪の箱ずしは、四角な木の枠にすし飯を詰め、具をのせて中蓋をはめ、手で押さえるもの。飯、具の一部、飯、上置きと四段に押す場合もある。この枠の現在の標準の大きさは8.5×8.5×4.0立方センチメートル。
これを六つに切ってサーヴする。昔の枠は現在の二倍もあり、京都の「いづう」では今でもその古風なのを使っている。 具は、中間にはさむのは椎茸や干瓢などのミジン切りが普通だが、上置きは魚介、肉、玉子焼、キクラゲなどを色彩効果を考えて手ぎわよく並べる。
大阪風に上置きを凝らないで一種類の魚やあるいは野菜、香の物などを使うのなら方々にある。神戸の「青辰」のアナゴずしは有名。京都なら「其角」のハモ、四国坂出のサワラ、信州佐久郡ドジョウなど、それぞれ名を売っている。
ざっこずし
小指大で卵を持っている切目ドジョウを塩っぽく煮て飯にのせ、箱に入れて押す。
和歌山のコケラずし
和歌山でいうコケラずし、鏡ずしなどもこの一類で、ただ標準一箱を四つに切ったほどに大型である。和歌山でいうコケラずしは錦糸玉子やエソの崩しが、鏡ずしにはカレイそのほかの白身の魚がある。身の切り方は非常に薄く、本を読んだ昔のコケラずしそのままだ。同地方の婚礼には欠かせないすしだという。
岸和田を中心に泉南地方の押しずしも、このコケラずしとは似たりよったりで、大きな飯塊の上に薄い魚肉がチョコンとのっている。 このような押しずしの簡単なのは日本全国で作られており、押し型も真四角や長方形のほか、扇形、花形、いちょう形など体裁のいいのが家庭用に売られている。
具はその地で手に入る魚介ならば何でも、山手では乾物や缶詰、野菜類と、いろいろ用いられている。料理というよりも副食物を添えたお弁当という感じが強い。それだけすしが日本人の生活に食い込んでいるわけだ。
三重県志摩地方の民謡「すしづくしよいこの節」にすしを読み込んだのがある。 箱ずしの種類がまことによく読み込まれているから付記しておく。
◆一に鰯すし 二に煮込みずし 三にさいらずし 四にしま鰯ずし 五にいなずし 六にむつずし 七つになにかを取り寄せて 八つ山川香魚のすし 九つこうやずし 十で豆腐屋のおからずし
東京の握りずし
東京風の握りずしというものは、周知のごとく酢飯を握って上に魚介(その多くはなまのまま)の切り身をのせるのである。それは、もちろん、刺身も立派な料理なのだから、握り飯の上に刺身をのせる東京ずしだって日本料理には違いはない。しかし、私が不審にたえないのは、その握りを論ずるに当たって、すし職人も、お客も、また本書きのエライさん方も、調理としてのすしが相手ではなく、上に貼る魚介のことだけを問題にしているのは、何故だろう。
握りとゆうものは文政初年(1820年代)両国の「華屋与兵衛」から始まった。というのが定説になっている。詳しく当時の文献を見ていくと必ずし「与兵衛」に始まったものではなくせっかく江戸前のピチピチした魚がてにはいるのにわわざ塩切りするのももったいない、というところから、誰やら彼やらが試作したの彼が大成した、と見る方がよさそうだ。lいずれにせよ握りずしの歴史はこの195年くらいの、ごく新しいものである。
この短い間にも握りずしはどしどし変化をしている。たとえば安政(1855年)のころ、近海でマグロがとれすぎて江戸中マグロのダイビングが始まった。これを見たさるすし屋がだぶついているマグロを安く仕入れ、少々プンとくるマグロを醤油に漬けて(いわゆるズケという代物)ごまかし、これを握って「徳用品」として売り出したのが大いに当たり、明治以後次第にもてはやされ出したという。実際、握りの本家の「与兵衛」では「オレンところであんな下司魚が握れるかい」といって、大震災(大正年)前まではいっさい握らなかったという。 それが世の中の食生活が変わり、おいおい油脂に慣れて来ると共に、その下司魚が滅法高級品になり、南洋でとれた冷凍物のトロでも高価になってしまった。
だいたい、これほど握りずしが日本全国に広がったのは、戦争中の統制のおかげなのだ。戦前の統制が終わったのに、今なお握りずしが盛行するのは何故だろう。それは冷凍工業の発達のおかげである。海岸に近くてよほど魚に恵まれている所か、それとも飛びぬけた高級店でないかぎり、これからは冷凍品を無視してやっていくには難しいだろう。
散らしずし
最も家庭的なものとして、全国に広がっているが、特に有名なのは岡山の備前ずし、長崎県の大村ずしである。また志摩の手こねずじのように、五目ずしを押す型のものもある。
散らしずし、またの名をばらずし、五目ずし、起こしずしともいった。一番家庭的なすしだ。もっとも、具と飯を混ぜるのが五目で、上置きするのが散らしだと区別する人もあるが、必ずしもそうは言い切れない。二、三の具を混ぜた上に上置きを散らす場合もあるからむしろ方言的に関東が五目ずし、関西がばらずしといった方がいいかもしれない。
瀬戸内海沿岸は魚が豊富だから、何かといえば魚味豊かなばらずしを作る。 中国筋ならばアナゴ、香川でサワラ、愛媛で小鯛と、それぞれ自慢の種がある。
岡山散らしずし
この散らしずしの中でも最も有名なのは備前岡山ずしだ。藩政時代、お上から来た下々だけへの倹約令に対する庶民のレジスタンスとして生まれたとか。 数々の具を限りなく入れた豊麗なもので、すし一升金一両とまでいわれた豪華を誇った。
しかしながら、一口に「備前と申しましても広うござんす」し、戦前、戦後と時代によって相当の差も出てきている。
主に具に使われる魚
春
ハモ、鯛、ブリ、マグロ、カツオ、ニベ、サヨリ、ホソ、ママカリ、コノシロ、鰻
ボラ、チヌ、ヒラゴ、ヒラメ、アジ、シイラ、メバル、アユ、ハエ、アサリ、モガイ、ハイガイ
夏
鯛、シクチ、マナカツオ、サワラ、サバ(山手のみ)、シイラ、ツナシ、ボラ
ホソ、アジ、サヨリ、ママカリ、鱸、サケ、マス、タラ、アユ、鯉、タコ、アサリ、モガイ
秋
ハモ、ヒラ、ブリ、カツオ、タチウオ、サンマ、ハマチ、アジ、シイラ,鰯、ニベ、アカメ、コヤ、チヌ、ハネ、ヨコワ、鰻、イナ、アユ、タコ、イカ、アサリ、モガイ、カニ
冬
アナゴ、ハモ、サワラ、ボラ、ブリ、ヒラ、ノセ、ホソ、ハマチ、マウロ、アカメ、ツクチ、アジ、サンマ、鯨、サケ、イカ、アサリ、牡蠣
つまりとれる魚は何でもすしに入れていることになる。 乾物、加工品のうちで圧倒的にどこでもどの家でも使われるのは、玉子を筆頭に高野豆腐、干瓢、椎茸で、特に高野豆腐が多いところ、さすが上方風だ。
山手では魚が少ない代わりに蒲鉾、竹輪に人気が出、カステラ(厚焼きの類)が、湯葉、切干大根なども。野菜は季節のものなら一通り並ぶが、山手ではワラビや芋がら(ずいき)というのも出てくる。
岡山市内のいずれの家庭でもその家のお得意の具を使い、お得意の盛り付けをするので一見共通点はないようだが、結局
①具が非常に多く使われていること。
②なかんずく、魚味が特に豊富なこと
③盛り付けが誠に美しいこと
などに落ち着きそうだ
都会式の作り方
鯛、その他白身の魚をできるだけ集め、刺身に作り、酒酢に一夜置く。 干瓢、椎茸、キクラゲ、高野豆腐、湯葉、凍コンニャク、えんどう豆、クワイ、ウド、フキ、 竹の子、ごぼう、人参、、蓮根などを適宜味付けし、全部を酢飯とよく混ぜる。
和歌山のばらずし
散らしずしは本来精進が多い。わざわざ精進にするわけでもないが、自家有り合わせのものを出来るだけ活用するので、自然生臭が入らないのだ。
たとえば和歌山県日高郡の山手での作り方
米一升につき酢八勺から一合、塩、砂糖少々を合わせ、具は、甘辛く煮た干瓢、椎茸、高野豆腐、麩などの乾物、人参、ごぼう(さきがけ)、蓮根、青豆など有り合わせの野菜、それに紅生姜や金糸玉子といったところ。生臭いものはシラス干か竹輪、はりこんだところでサバのそぎ身など。
つまり、上置きにサバの生ずしでも並べたら上等という程度だ。同じく紀州田辺の 東の周参見で聞いた話では、すしに白身の魚を使うものではない。サバ、カツオその他赤身のものに限ると、岡山ずしとはすべて逆だった。
広島のもぐりずし
尋常の散らしずしの異名だが、具はジャガイモ、豆、人参、ごぼう、イリコといった程度 熊本のトサカノリのすし トサカノリを水に漬けて戻し、よく洗い、細切にして酢に漬ける。マンボー(=シイラ)の塩物を白水で塩出しし、刺身大に切り、酢を当てる。ほかに凍コンニャクぐらい。酢飯と よく混ぜる
比叡山の精進ずし
米一升、水一升で、沸騰し始めたら火を弱め、飯の焦げぬようにゆっくり蒸す。 酢一合五勺、砂糖大さじ二杯、塩茶さじ一杯、味の素少々合わせ、釜の中の飯 にうち、そのまま二、三分蒸し、浅いおひつに移して冷ます。 具は椎茸、干瓢、高野豆腐(以上椎茸の漬け汁で甘辛く煮る)、三つ葉(ゆでる) 湯葉、(油でいため、油抜きしておく)など。高野豆腐と湯葉は関西ではフンダン に使われる。 サーヴの仕方でひどくうたれるのは、筑後三井郡小郡在の柿の葉ずしである。 近畿で見なれた柿の葉ずしとは全然違う。皿の上に濃緑色の柿の葉が放射状に並べられ、これを小皿代わりに散らしずしが美しく盛りつけられいるのだ。 干瓢、椎茸の褐色、金糸玉子の黄金色、生姜の紅に山椒の浅緑。それに銀のように輝くすし飯と。これらが濃い緑色の柿の葉の色と実に見事に対比をしていた。 これほど美しいすしの盛り付けは今まで見たことがない。
大阪の蒸しずし
蒸しずしは散らしずしを蒸して温めた冬向きのものだ。この蒸しずしは明治以前に京都で行われていたことは間違いない。 茶碗で蒸すと湯気の通りが悪く、茶碗の真中までなかなぬくまらないのではないかと気になるものだが、実際は15分ぐらいで十分らしい。しかしながら、昔は芝居といえばまだ夜も明けきらぬ五時ごろから始まっていた。その芝居見物の人たちの中食はまずは茶碗ずし(すなわち蒸しずし)と相場が決まっていた。
大勢の見物人がお昼になって一どきにこのすしを注文するとなると、一つの茶碗に15分もかけていたのではなかなさばききれない。 何かうまい工夫があったはずだ。昔の蒸しずし用の茶碗には底に穴があいていて、湯気の通りがよくなっている。
蒸しずしは散らしずしを温めたようなものだといったが、実際散らしずしその物を蒸したら失敗する。熱のために酢がききすぎるうえに、玉子などは容易に変色するから。
大阪風のやり方は次の通りである。 作り方 飯は普通のすし飯の加減、またそれに2,3割白飯を混ぜる。椎茸、焼きアナゴ、すだれ麩、竹の子、ごぼうなどの具を混ぜて、五目ずしにする。酢は必ず関西風の白酢を用いること。上置きはオボロ、豌豆キクラゲ、焼き栗など。蒸し上てから金糸玉子を置く。
押しずし
散らしずしは一名起こしずしともいう。つまり五目ずしといえども本来は重石をかけてある期間熟成させた。それをあらためて掘り起こして食べたので起こしずしといったわけである。 もちろん起こしかえさずに固めたまま切って出しもした。そんななわけで、現在でも散らしずしを数時間ないし数時間ないし数日重石する風は方々に残っていて、時には重石の代わりに手で押さえておく。という簡便型も見られる。中でも有名なのが備前の大村ずしである。
大村ずし
すし桶は大きく、角型(1.5尺1尺5寸)。すし飯は昆布味で、飯1升に酢2合砂糖少し濃い味付けだ。具は、魚味は鯛、ヒラメ、サバ、味、アナゴ、カニ、エビなど。
野菜は人参、ごぼう、竹の子、ワラビ、フキなど。それに椎茸、干瓢が入る。飯と具とを三段に重ね、上置きは金糸玉子。柚を入れるとなおよい。四、五時間押す。
志摩の手こねずし
すし飯は塩、砂糖で調味して硬目に炊き、すしさまし(半きりのこと)に移し、酢を合わせ てさます。米一升に酢二合、砂糖50匁、塩一勺(というから、これも濃い味つけだ)。 魚はカツオ、ヨコワなど赤身のを喜ぶが、人によってはいっさい魚を用いない。里芋、人参、ごぼう、椎茸、さや豆など。飯を二寸に具一並びと交互に詰めてゆき、手で押さえるだけの人もあるし、そのあと重石する人もある。上置きは金糸玉子、アマノリ、青豌豆など。
加賀のおにえずし
飯は硬目に炊き、酢、塩、砂糖で味付けする。魚は鯛、鰯、サバ、シイラなど。一時間から三時間塩きりのうえ、酢に一時間から三時間漬ける。野菜としては人参、生姜、柚(ミカンでもよい)の皮、紺ノリなど。春は木の芽もよろしい。魚、飯と順々に重ねてゆき重石する。
石はかなり重いようだ。ある程度馴らしてあり、尋常の散らしずしとは風味がまったく異なる。紺ノリがいかにも美しい。
丹後の切りずし
質素な方だと丹後熊野郡あたりの切りずしがある。飯は硬目。高野豆腐、竹の子、ワラビ、ゼンマイ、干瓢などを醤油で煮つけ、飯とよく混ぜて四角いすし箱(マツビタと呼ぶ)に詰める。
別にサバを焼き、甘辛く煮しめてソボロを作り、紅生姜をミジンにきざみ、ソボロと一緒 に上置きにして重石をかける。このうち高野豆腐、竹の子、ソボロの三つは欠けてはいけない。
五目ずし
遠州の五目ずし
静岡県西部ではほとんどが干瓢と椎茸で、海苔、人参、蓮根、紅生姜、玉子、竹輪、おぼろ なども少しは使われる。
まれにごぼうや蒲鉾、油揚げ(ことに浜名湖北岸地区)も使われる。遠江は太平洋岸に面しているがろくな漁港がないので、一般に魚は不自由している。(昭和44年時点)
巻ずし
海苔巻は、全国的に行なわれる家庭向きのすしである。巻く材料は、海苔のほか青海苔(和歌山県)、昆布、玉子焼(高知県)などを用いる地方もある。巻きずしは散らしずしと同様に原則として精進である。共に家庭で手っとり早く出来るから広く普及しているが、魚好き、すし好きの日本人が仏事用に、あるいは即席用に工夫したのかもしれない。起源はだいたい江戸中期前かと思われる。
散らしずしを箱に入れて押す際、普通底やへだてに笹の葉、バラン、竹の皮などを敷く。その代わりとして食用になる昆布、湯葉、浅草海苔などを使えば、それも一緒に食べられる。つまり巻きずしになる。
東京人は巻きといえば海苔巻だけしか考えないが、東京でももとは冬には昆布巻を作っていた。高知県へ行けば現在すし屋の店先をにぎわしている。
巻く材料は幅が広く食用になるものでさえあれば何でもよく、今も九州で行われているという湯葉巻も、天明ごろの江戸のすし屋の広告に見えている。薄焼き玉子で四角で包む茶巾ずし、厚焼き玉子で巻けば伊達巻、油揚げで包んだ稲荷ずし、紀州熊野の漬菜の葉で包んだめばりずし(タカナずしともいう)なども広義の巻ずしに入る。
タカナずし
タカナの漬物を二杯酢に漬け、中の芯をとり、この方は細かくきざんでそれを芯にして炊き立ての飯を大きく握り、残った葉でぴったり包む。二杯酢の味が飯にしみこみ、タカナの香りと相まって上乗の効果を与える。中の芯にはタカナのほか、梅干、生姜、オボロ、鰹節などを入れるとときもあり、頃合いに漬かったのがないときはタカナの葉をゆでて、二杯酢に漬けて用いる。急ぐときは塩ゆでの葉でも我慢できる。ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。
卯のはなずし
伊予の丸ずし、広島県西部から山口県海岸部に行なわれるとうずし、石見のおまんずし、出雲のコノシロずし、備後三次や羽前新庄、羽後矢島のアユずしなど。このほか、裏日本の海岸部に広くあり、材料はイワシか、コノシロが多い。表日本でもイワシのとれる所では行なわれている。
蜀山人の歌文化14年に
◆和唐紙にもの書くことは御免酒やはだの酢に豆腐つみ入れ というのがある。
和紙の唐紙に字を書くことなんか真っ平だ。あれは江戸城のご門の外で供待ちしている人足向きの金魚酒やコハダのすしや豆腐のつみ入れ汁みたいなものだから(全部代用品だ)、といった意味である。
◆坊主だまして還俗させてこはだの鮓でも売らせたい
と歌われるほどコハダのすしが粋になったのは寛永ごろ1850年前後)の話で、それだって粋なのはすし売りの姿だけだったかもしれない。元来は人足、陸尺たち相手の安ずしで、飯の代わりにオカラ(卯の花)が入っていたのだ。
もっとも、オカラ入りだから下司だ、とは限らない、イワシやコハダだから下司だったので、もう少し古く宝暦、明和のころ( 1764年ころ)の「東本願寺御膳所日記」見ると、鯛の卯の花漬はしばしば法王の食膳をにぎわしている。
方々で作るのでその方言も多く、おからずし、卯の花ずしなどは尋常だが
からずし 山口県
おまんずし 石見
コノシラずし 出雲
吹雪ずし 富山
とうのすし 伊勢
まるずし 伊予
おかべずし 長崎
などいろいろだ。ことに「おまん」なんか語源の見当もつかない。例をあげると
作り方
画周防吉敷郡のとうずし
アジがが主でセイゴも使う。背で開き、酢飯または酢をしたオカラを詰める。夏祭りや婚礼に使う。
五島のカラずし
オカラをよくすり、醤油と酒を加えて炒り、少量の酢を加えてさます。鮒は酢を きかせ、骨を抜き、右の オカラの上におく。
富山の吹雪ずし
鰯を酢で殺し、骨を抜き、調味したオカラを合わせ、色取りに唐辛子をそえる。
自家でも作るが、都会では滑川、魚津、泊の漁港から送られてくる。石動では頭を落とした鰯の腹にオカラ を詰めるが、富山では押しずしのように固めたオカラの上に魚を貼る。卯の花に味を付けて握りずしのタネ にすることが伊賀で行われているが、比叡山でも作るそうだ。
印籠ずし
印籠ずしは巻ずし系に入れてもよいかもしれないが、 何か幅の広い食品ですし飯を巻くというのではなく、空洞のある天然物の中に詰め込むのだから、考え方によれば姿ずしの延長とともいえる。中でも有名なのは竹の子の印籠ずし。古くは、例年初夏、醍醐理性院と勧修寺とから禁裏に献上されていて。
いかの印籠ずし
昔から、静岡県中西部では五目ずし(干瓢、椎茸、人参、油揚げ、等使われている)詰める。当店はこの伝統的散らしずし(起こしずじ)ともいえる五目ずしをつけております。裏日本に多く、島根半島、能登の外浦などは有名である。しかし、島根半島でいうのはイカの胴に白飯を詰めて煮ただけで、すしとは縁がない。
筍印籠ずし
よくゆで、食べるばかりにした竹の子の底の方の節を残しておき、その中へ 酢飯を詰める。
白瓜の印籠ずし
白瓜の芯を抜き昆布の入った塩水に漬けておき、軟らくなったら30分かわかす。すし飯を作り、エビ、キクラゲ、アユの骨焼く身、錦糸玉子などを合わせて印籠に詰め、昆布で押す。