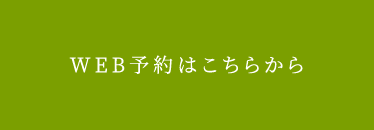鮨を知る
 UOTAKE SUSHI
UOTAKE SUSHI
日本のすしの歴史

2021年10月6日
すしのルーツ
起源は東南アジア
「すし」と称される料理は、酢をあてて酸味を呈するもの(早ずし)と、酢を使わずに自然発酵によって酸味を得るもの(発酵ずし)とに大別される。形式としては発酵ずしの方が圧倒的に古く、起源は海外に求められる。 渡来した発酵ずしが日本国内で改良された結果であり、ここに、「すしは日本料理」との評価を受ける由縁がある。
すし文化の先駆的研究者・篠田統は、すしのルーツを東南アジアの山地民の魚肉保存食だと考えた。
高地ゆえ入手困難な魚肉を、塩とデンプン質の中で長期保存のため漬物のように発酵させ、結果的に酸味がついた食品がすしの起源だというのである。
水田耕作と密接に関連
しかし後に、文化人類学者の石毛直道が、広範なフィールドワークを通じて、この種の食品が広く東南アジアに分布することを見出し、篠田がいうような山地民の保存食は、その中ではむしろ特殊な存在であることをつきとめた
石毛によれば、この種の食品が盛んに作られるのは東南アジアでも低地の稲作地帯で、そこでは水田耕作と密接に関連した自給的な漁業「水田漁業」が展開されている。
魚肉を米などのデンプン質の中で発酵させる技法は、篠田が主張するような山間部よりも水田地帯で稲作とともに成立したと考えるのが自然で、石毛は東北タイやミャンマーあたりの平野部をすしの発祥地候補として挙げた。
この地域は雨季と乾季が明瞭で、雨季には池沼状態になる水田において捕獲された魚を乾季まで保存しておくために、ふんだんに採れる米の中で魚肉を熟成発酵させることが行われている。
これがすしの原型だというのである。 現在のところ、学会では篠田説より石毛説の方が好んで採用されている。 「すし」と称される料理は、酢をあてて酸味を呈するもの(早ずし)と、酢を使わずに自然発酵によって酸味を得るもの(発酵ずし)とに大別される。形式としては発酵ずしの方が圧倒的に古く、起源は海外に求められる。
渡来した発酵ずしが日本国内で改良された結果であり、ここに、「すしは日本料理」との評価を受ける由縁がある
すし文化の先駆的研究者・篠田統は、すしのルーツを東南アジアの山地民の魚肉保存食だと考えた。高地ゆえ入手困難な魚肉を、塩とデンプン質の中で長期保存のため漬物のように発酵させ、結果的に酸味がついた食品がすしの起源だというのである。
鮨と鮓
鮨と鮓の文字の起源
この東南アジアの発酵食品が、北上して中国に伝わる。時期は明らかではないが、この食べ物に関する文献的初出は、三世紀に編まれた字典『説文解字』で、「塩と米とで醸した(魚の)漬物」を「鮓」と表記する旨が記されている。
よって、すしの原型はそれ以前に伝わっていたことになる。
同じ三世紀ごろの編で、『説文解字』よりやや遅れて編まれた字典『広雅』では、「鮓」と同義として「鮨」の文字を挙げる。しかし、紀元前5~3世紀の字典『爾雅』によれば、「鮨」は「魚のシオカラ」とある。
シオカラにはデンプン質を使用しないのが常であるから、この「鮨」と、飯をともなう「鮓」とは、元来が異なる食品であったことになる。にもかかわらず『広雅』は二つの文字を混同した。
文字の国である中国で、しかも辞書を編もうという学者がかかる過ちをしでかしたということは、三世紀の中国で、いかに「鮓」が非一般的な食品であったかを想像させる。
ここにも「鮓」が中国起源のものでない傍証がある。
鮨と鮓の文字の混用
『広雅』雅犯した「鮨」と「鮓」との混用は以後も改められることはなかったようで、わが国に文字が伝わった際も、その混乱はそのまま続いていたと思われる。
平安初期の編まれた法令注釈書『令義解』(天長10年〈833〉)でも「鮨は鮓のこと」と述べている。
中世期以降の本法文献でも、「鮨」と「鮓」は明確に使い分けたと判断できるものはなく、また「鮨」をシオカラの意味で用いた例も見当たらない。
「鮨」と「鮓」はいずれも「すし」を表す漢字として使用されており、それは現代日本においても同じである『広雅』に端を発する混用は今もって生きていると言わねばなるまい。br>
日本への伝来
鮨と鮓の文字がわが国最古の文字記録
「鮨」と「鮓」のもじは、わが国最古の文字記録資料に、すでに散見される。 たとえば、正倉院文書『尾張国正税帳』(天平6年〈734〉)には「白貝内鮨」、 『但馬国正税帳』(天平9年〈737〉には「雑鮨」の記録が、また、同じく天平年間のものと思われる平城京跡出土木簡には「若狭 多比鮓」、長屋王邸出土木簡には「筑前 鮒鮨」、二条大路出土木簡には「志摩 堅鰹鮨 近代鮨」「若狭 鯛鮓 鰒鮓」などの文字が見える。 また、養老2年(718)成立の『養老令』は、原文は残らないものの、平安期に著された注釈書『令義解』や『令集解』によって原文が復元できる。ここにも「鮓」の文字が見える。 さらに、その『養老令』の基となった『大宝令』(大宝元年〈701〉)にもこの文字があった可能性が指摘されている。 以上のような状況から、少なくとも奈良時代には「鮨」や「鮓」が盛んに作られていたことが想像される。 当時は、わが国が、律令制度をはじめとして中国(唐)の文化を積極的に導入した時期に当たる。
すしと稲作とは同一の伝播経路
文字記録に従うなら、奈良時代より前にさかのぼることは不可能だが、一方で、すしが米を使う料理である以上、その日本伝来は稲作と期を同じくすると考えることもできる。 稲作の伝来ルートは、目下、朝鮮半島経由でも琉球経由でもなく、揚子江下流平野から直接北九州に及んだと考える説が一般的になっている。それに雇用するかのごとく、朝鮮半島にも琉球諸島にも、古い時代のすしの痕跡は認められない。 つまりは、すしと稲作とは同一の伝播経路をたどったと想像され、両者同時期の日本伝来をも感じさせる。
日本上陸は縄文晩期
石毛の言うように、すしが稲作に付随する「水田漁業」文化の一現象であるとすれば、その可能性はさらに高くなる。であるならば、すしの日本上陸は縄文晩期、すなわち紀元前2~300年にまでさかのぼることになる。 もっとも、すしの伝来は一度限りのものではなく、稲作と同じく数世紀に渡って波状的に大陸から伝わったと考えるのが自然であろう。すしつくりの技法そのものは稲作とともに伝わっていたとしても、奈良時代における大陸文化の積極的導入は、わが国にすし作りをより普及させた遠因になったと考えるし、さらに時代が下がってから、朝鮮半島から新しいすし作りの技法が伝わった可能性もあると思っている。
古代日本のすし
米と塩と魚だけで作る
平安時代の法令施行細則書である『延喜式』(延長5年〈927〉完成)からは、 西日本各国からさまざまなすしが都に納められていたことがわかる。
当時のすしの製法は記録に残っていないが、六世紀半ばの中国で刊行された『斎民要術』の製法記事が参考になろう。材料については『延喜式』に記述がある。
すなわち、塩味をつけた魚と白米と塩である。中国におけるすしの変遷史をた どると米と塩と魚だけで作るはずのすしは、時代が下るにつれて、酒や香辛料などの添加物が加わるようになる。つまり『延喜式』が伝えるすしの材料は、きわめて古い時代のすしの要素を持っていることになる。
飯は食べず
また、外観や食べ方に関しては、平安期の説話集『今昔物語』(12世紀前半成立)などが貴重な資料になる。 たとえば、すしを商う女が商品たるべきすしの上に嘔吐したにもかかわらず、 それをこそげ落として商売を続けたという話があるが、この話から、すしは嘔吐物のも似た物体に覆われていた事や、相当な酸臭を放っていたことなどが想像され、かなり長時間にわたって発酵させられていたと考えられる。
魚の周囲はドロドロに発酵した米飯で覆うわれていたのだろう。しかも、その飯部分は食用に供することはなかったとも思われる。
同書には、すしを副食にして飯を食べたという話も所収されており、さらに、江戸時代(元禄17年〈1704〉)の写本ながら、平安末期の成立とされる『類聚雑要沙』(東京博物館蔵)の、「鮨鮎」の図(保元2年〈1157〉12月「内大臣殿廂大饗宴」の献立記録)には飯粒が描かれていない。
ここにも、すしの飯の部分は食べなかったことの傍証がある。
料理としての価値
現代、多くの人は発酵ずしをナマナレズシと呼ぶ。ナレとは「馴れ」すなわち発酵・熟成のことであるが、飯を食べないこの形態をホンナレと呼ぶことがある。
なを、鮨の原型が東南アジアの魚肉保存法にあることはすでに述べたとうりであるが、この時代のすしが、単なる魚肉保存の手段という消極的な意味合いしか持っていなかったとは考えずらい。
たしかにすしという調理加工技術は魚肉の腐敗を抑制し、長期保存に有用であるが、『延喜式』によれば、わずか1~2日しか旅程を要しない河内・伊賀・吉野などの諸国からもすしが都に貢納されている。これくらいならわざわざ飯漬けにしなくても塩漬け魚で十分であるし、現実に、すしの材料用としての塩蔵魚が河内・近江などから運ばれている。
塩漬け魚で保存
すしと塩漬けを比較した場合、酸味とから味混ざるすしよりも、から味だけしかつかない塩漬けの方が素材の持ち味を殺す度合いが少なく、魚肉保存手段としては優れていると言わざるを得ない。
それでもあえてすしを収めさせた、および、わざわざ塩漬け魚を都ですしに漬けたということは、すしは単なる貯蔵手段でなく、塩漬け魚とは異なった風味、すなわち、そこで醸し出される酸味を楽しむための、ひとつの料理としての価値を見出されていたからであろう。
ナマナレの発生
すしが「ご飯料理」
鎌倉期のすしに関する文献はすこぶる少ない。 続く室町時代になると、資料の残存度が向上し、しかも個人の日記類も多くなるため、すしの様子も比較的わかりやすくなる。
この時代の特徴は、まず、ナマナレの発生を挙げなければならない。 ナマナレはホンナレに対する語である。ホンナレがしっかり熟成発酵させて飯をこそげ落として食べるのに対して、ナマナレは発酵の早い段階で止め飯も一緒に食べる。
すしが「ご飯料理」になるのはこの時代からである。これは、すしの歴史の中で画期的なできごとである。
ナマナレは、節米意識
この時期、平安期の荘園開発による耕地拡大と鎌倉期の農法改革が効を奏して、米の増産に成功した。
憶測するに、米を大量に使用するすし、とりわけ飯を捨ててしまうホンナレはかなり贅沢料理であり、それなりの階層の者の口にしか入らなかったことであろう。
それが、米の増産にともなう一般普及とともに、それまで縁のなかった階層にまで紹介されたのではあるまいか。とはいえ、彼らにとって米が貴重品であることに変わりがなく、飯を捨ててしまうホンナレの食法には抵抗があったことだろう。
ナマナレは、節米意識の中から生み出されたと思われる。
賞味期間の短縮
飯を食するためには、飯がペースト状になるまで発酵させると都合が悪い。 さりとて、すしは酸味を楽しむものであるから、酸っぱくならないと具合が悪い。 両者の折り合いがつくギリギリのところを見計らってナマナレは食べられる。 ホンナレの時代には、すしはあるていどの常備性を持っており、その意味では貯蔵食的な意味合いも残っていたわけでだがナマナレにしたことで、賞味期間は短くなってしまった。
ここに、すしはもはや長期保存の意図を欠落させたと言ってよい。
これまた、すしの歴史の中では特筆されるべき出来事である。
新しいすしが誕生
室町後期は戦乱の世となり下克上に代表されるような前例打破の哲学が台頭した。
さらには南蛮貿易の開幕で、西洋文物の流入もあった。めまぐるしく移り変わる世情、横行する実利主義、そしてそれらを是認せざるを得ないといった文化的背景に中で、これまでの常識では考えられなかった新しいすしが誕生したのは、ある意味で、必然かもしれない。
ホンナレは現代の造語であるが、ナマナレ(もしくはナマナリ)は当時のことばで、『蜷川親元日記』(文明5~18年〈1473~86〉)などに見える。ナレがナマナマしいという意味であろう。 また、「飯ずし(いいずし)」とも呼ばれたが、「飯ずし(いずし)」とは別物である。
発酵を浅くすることで、ホンナレではやわらかくなったであろう小骨が、すしの中の固いままで残る可能性がある。 実際、『医学天正記』(1580ころ)に載っている「フナずしの小骨が喉に刺さった」という症例はホンナレでは考えられない珍事である。
このため、ナマナレには骨のやわらかい幼魚を漬けるようになったのか、『殿中申次記』(永正13年〈1516)や後世の『貞丈雑記』(宝暦年間〈1751~64〉)では、ナマナレと小ブナのすしだと解説する。一面的には言い当てているかもしれぬが、一般論としては誤記である。
早ずしの誕生
発酵期間の短縮化
発酵期間の短縮により調整時間を飛躍的に短くしたナマナレであるが、次なる課題は、さらにその期間を縮めることにあった。
『料理物語』の「一夜ずし」はまた、無塩のアユを使うようにも勧めてい。これも、塩気が足りないと発酵が早く進むという経験にもとづくものであろ。一応は理にかなっているものの、以後は、むしろ魚の塩気はしっかりきかせる傾向に向かう。 味覚的な理由と腐敗防止のためだと想像される。塩が薄いと魚は腐りやすい。
結局、従前の材料構成では発酵期間の短縮化は限界に達したと言わざるを得ず、次段階として、発酵促進剤の混和をみるこのあたりの工夫は『料理物語』以後の料理書、たとえば『料理塩梅集』(寛文8年〈1668〉)や『合類日用料理沙』(元禄2年〈1689〉)など江戸初期の文献に明らかである。
発酵促進剤
ひとつには、糀の混和がある。これは、今日の東北・北陸地方に広く見られる発酵ずし(北海道・青森の飯ずし、秋田のハタハタずし、山形の粥ずし、富山・石川のカブラずし、福井のニシンずしなど)にも見られる技法で、糀の作用で発酵は促進される。
他方では、酒を混和する方法もあった。酒を放置しておくと酸っぱくなることはよく知られている。『料理網目調味沙』(享保15年〈1730〉)で、魚を浸すのに、わざわざ「古い酒」としていしているのは、その方がより早く酸っぱくなるからであろう。また、酒をしぼった粕は、後に粕酢と呼ばれる酢の原料にもなるくらいであるから、それ自体、酸味の素である。酒粕を飯に混ぜて魚身に詰めることは、『合類日用料理沙』にも記載がある。
今ひとつの方法は、酢を混ぜることである。こうなると、発酵を促進させて酢っぽくなるのを待つ必要などはない。もちろん当時は、酢を使ったとしても「一晩は寝かす」(明和8年〈1771〉)『卓袱懐石趣向帳』、「成形させたすしの上からふりかける」(享和2年〈1802〉『名飯部類』)という具合で、現今の酢の使い方とはいささか異なるものであったが、作ったすぐから酸っぱくなっていることには変わりがない。
長期保存の意味合いは完全になくなり、それまでの概念とはまったく異なるすしの誕生であった。
一部には、発酵促進剤を使った改良型のナマナレを早ずしと称することもあるが、一般には、酢を使った、最初から酸味のついたものを早ずしと呼ぶ。
早ずしの台頭と発酵ずしのその後
酢を使う早ずしの誕生
このふたつの形態は、わが国にすしがもたされたところから分化していたと考えられ、つまり、わが国のすしは、姿漬けと切り身漬けの二本柱で発達してきたと言える。ところが、酢を使う早ずしの誕生後、約百年が経つと、すしの形態は一変する。 この間の一世紀は、すしの主流が発酵ずしから早ずしに置き換わるための期間であった。当初は邪道扱いされた早ずしは、18世紀も中葉になると多くの人の知るところとなり、受け入れられた。 加えて、迎えた田沼時代と大御所時代は、途中に寛政の改革という質素倹約期をはさむものの、江戸文化の爛熟期である。 食に対する関心も高まった。作るのに何日も要しない上に、酢と飯と魚さえあれば「すし」と呼べたことが追い風になったのであろう、すしには多様な形態が生み出された。素材面でも、たとえば飯の代わりにオカラや甘藷を利用するなど、ユニークなアレンジもなされた。
発酵ずしの衰退
それらが江戸の市井で起こったのは、一連の改変行為が庶民の自由な発想の結実だったことも示している。ともあれ、19世紀初頭には、すしの形態は、現代と大差ないほどまで出そろっていた。
このような早ずしの台頭にともない、それまでのすしの王道であった発酵ずしは、近江のフナずしや出羽のハタハタずしのようにすでに特産品としての名声を得ていたものを除いては、次第に過去の遺物と化し、辺境鄙地の家庭料理くらいしか残らないほどまで転落してゆく。
しかしながら、幕末に至るまで、室町時代さながらの発酵ずしの製法を堅持した例もある。 将軍家・大名・公家などの階層でやりとりされた、贈答用のすしである。
将軍家に対する献上
諸大名から将軍家に対する各領国の名産品献上は、江戸初期の元和年間(1615~24)には、おおむね公式行事の体制を整えていた。献上品のなかにはすしもしばしば散見され、これを贈っていた藩は全国で十数藩を数える。 授受されるものの階層を考えれば、その調整には細心の注意が払われたことは言いをまたず、製造所や調理人、さらには材料の調達者や輸送管理者までもが厳しい管理体制の下に置かれたことは、尾張徳川家の献上アユずし史料に明らかである。 「将軍家御用」というレッテルで名声を高めつつ、やがて、これらはマニュアル化され、「前年のとうり」を大前提として受け継がれてゆく。典型的な役人の前例踏襲主義であり、それは庶民生活とは一切乖遊離したところで、倒幕まで続けられた。
早ずし誕生以前の製法が、連綿と保持されることになった。早ずしに慣れきった市井の庶民連中にはもはや省みられはしなかった。一部は、維新後、新たな権力に再び献上されもしたが、やはり長続きしなかった。当の権力階層からも、敬遠されていたのである。 こうして、献上ずしの多くは、かっての名声とは裏腹に、この機を持ってほぼ消滅した。
姿漬けすしの変容
早ずしの出現によって食べづらい姿ずし
尾頭つきの魚をすしにした場合、頭や尾、背骨などは固くて食べづらい。そこで、頭も尾も背骨もとって、いわゆる3枚おろしにして、そのおろし身で飯を抱き込ませるという発想が生じる。もとが姿ずしであるから、全体として魚の外観を思わせるような細身の仕上がりとなる。
姿ずしから棒ずしへの移行
これが棒ずしと称されるもので、さらに飯の部分が量的に勝ってくると、棒状の飯の上に魚身を貼り付けた松前ずしやアナゴずしのような形状になってくる。また、現今では「姿ずし」の商標を冠しつつも、現実には、頭を落とした開き身を貼りつけたサンマずしやアジずしが売られていることがあるが、これらは、姿ずしから棒ずしへの移行期の形態と位置づけられる。
棒ずしの派生形が巻きずし
簀の子の上に飯を広げ、魚身を乗せて巻きつけるという今日的な巻ずしは、安永5年(1776)の『新撰献立部類集』が初見えである。棒状になったものを小口から切って食するとあるから、まさに現代と同じである。ただし、「飯めしを広げる前に、簀の子の上に海苔または和紙またはフグの皮を敷き、和紙の場合は、これをはがして食べる」との旨が記してある。
魚と飯の位置関係逆転
『料理山海郷』の巻ずしはまさに魚そのものであるし、『新撰献立部類集』がいうフグの皮で巻いたすしも、仕上がりが一尾の魚を思わせる。海苔や和紙は、魚の皮の代用と見られよう。
姿ずしと違うのは魚とご飯の位置関係で、姿ずしでは魚身の内側に飯があるのに対して、巻きずしは魚身をご飯で包む。この逆転現象を、当時の人の遊びの心の表れ、一種の「見立て」の結果だと想像する。少なくても、必要に迫られて作られたものではなかろう。
巻く素材
後に、和紙のような「不可食品」は使用されなくなった反面、巻く素材も海苔以外にまで広がった。
たとえば、『名飯部類』(享和2年1802)にはワカメで巻いた「メ巻き」が紹介されているし、幕末には、卵焼きで巻いたものも登場する。さらに、芯となる具材も、当初は魚身であったのが、いわゆる精進物にも目を向けられ、嘉永2年(1849)の随筆『守貞漫稿』では、「海苔巻ずしの中身はカンピョウのみ」と解説する。こうして、巻きずしのバリエーションは増えていった。
稲荷ずしの誕生
棒ずしの変形
嘉永2年(1849)の随筆『守貞漫稿』によれば天保年間末期(1840年ころ)に、 油揚げの小袋に五目ずしを詰め、「稲荷ずし」「篠田ずし」と称して売る者があっ たという。このすしは名古屋にはもっと前からあったもので、江戸でも店舗売りは それ以前からあった。価格は「最も賤価」だった。
稲荷ずしを切り売り
嘉永5年(1852)の『近世商売尽狂歌合』に書き添えられた売り口上はは「一本 が16文、半分が8文、一切れが4文」とあるから。稲荷ずしは切り売りしていたことがあきらかである。売る商人の台の上には細長い稲荷ずしと包丁が置かれていた。
細長いすしを包丁で切り、ワサビ醤油で食べるという行為は、魚の姿ずしや棒ずしに通じるところがある。稲成ずしもまた、巻きずし同様、「見立て」に端を発した発明品で、油揚げは、魚の外皮の代用と見られなくもない。
切り身漬けのすしの変容
箱ずしへの移行
切り身漬けの発酵ずしは、酢がつ使われるようになり、今日的な箱ずしへと発展していく
「こけら」の意味
「こけら」とは、ひとつには木クズの意味がある。ご飯に混ぜるために薄切りした魚の身を木クズに見立てたのであろう。典型的な「切り身漬けのすし」であり、発酵ずしであることは言うまでもない。もうひとつ、瓦代わりの薄い板を指す意味がある。現在でも、箱ずしを作る際には「具材は、瓦板を並べるように、少しずつ隣に重ねながら置いてゆく」という大阪ずしの職人がおり、それゆえか、関西の箱ずしは「こけらずし」の異名を持つ。ことらはもちろん、酢を使った早ずしである。
こけらずし すしの発生上
当初の具材は生魚であったはずだが、後に、卵焼きや野菜類も併せて乗せるようになった。『守貞漫稿』にとれば文政から天保のころ(1839ころ)、大阪の心斉橋筋の「福本」なるすし屋が、従来の箱ずしよりも具材を充実させた。 それまではトリガイを使うのが常だったのを、タイ、・アワビ・卵焼きなどで豪華に厚くしたすしを売り始め、大好評を博したという。この豪華な箱ずしが、「こけらずし」と呼び分けられるのだとも伝えている。
抜き出して切り分ける
箱の中の芸術品とも呼ばれる大阪の箱ずしは、この時期をもって、一応の完成をみた。今日の大阪の箱ずしの押し箱は、枠と呼んでもよいくらいの大きさである。このサイズは今に始まったことではなく、幕末期には「四寸四方」という規格ができていた。けれども他地方においては、大量のすしを発酵させる従来のすし容器を踏襲して大型の押し箱を使用することもあったはずで、通常、箱ずしとは多人数分を一挙に作り、箱から抜き出して切り分けるという手法を採る。
「押し抜きずし」
「切る」という工程を回避するために、ひとつは箱を小型化することが考えられる。一口サイズに抜き出す、あるいは抜き出した後に包丁を要しない「押し抜きずし」は、その究極的な形態と言えよう。大阪のはきずしは、一人前ずつ作り出す程度に容器の小型化を果たした反面、最終的には「切る」という工程を残している点で、双方の中間的形態と位置づけられる。
「起こしずし」
一方、箱から抜き出して小さく切り分ける工程を省略するために、箱から抜き出さず、さじですくい取る方法も現れた。さじで起こすから「起こしずし」と呼ばれたこのやり方は、大阪の堂島では「すくいずし」と名づけられて商品化されたと『名飯部類』に載っている。
7. 混ぜずし 救い出されたすしは、もはや塊をなさず、ついには最初から押しをかけないすしの誕生に至る。これが、混ぜずし(ちらしずし・五目ずし)である。ここに、押しをまったくかけない、前代未聞のすしが誕生した。発酵ずしは言うに及ばず、早ずしもまた。 多かれ少なかれ押しの工程を有するゆえ、これはすしの歴史の中では画期的なできごとだと言える。
握りずしの誕生
握り早漬け
創始者と伝えられる華屋与兵衛の曽孫にあたる小泉清三郎らの記録によれば「握るすし」というのは与兵衛以前にもあった。
しかしそれは、小さく握った飯の上に魚を貼り付け、箱の中で笹の葉の仕切りはしてあったが、要は、箱ずしである。 このすしはたちまち大当たりで、店は大繁盛した。
すし商の二分化と握りずしの高級化
廉価なすし屋
江戸時代の資料には露天商やすし屋の屋台を描いたものは、多数ある。尻っぱしょりの股引姿で、たくさん積み重ねた箱を肩に、すしを売り歩く男の姿もある。これらのすし商に共通することは、いずれも廉価なすしを商ったであろうことで、早ずしの台頭とすしの多様化が市井の町人達によって支持されたことがあらためて知れる。とりわけ、江戸中期以後、男性の人口比重が高く、日雇い賃金労働者が多くなった江戸の街においては低廉な飲食業の興隆をみるが、すし商もその例外ではなかった。
高級なすし店
他方、固定店舗を構えたすし商もあった。けれども、多くは持ち帰りと出前専門の仕出し屋でいわゆる「食堂」機能を備えた店は数が少なかった。
文化の初めごろ、江戸深川の六間堀に「松がずし」ができて、世のすしの風は一変した。(文政13年1830『嬉遊笑覧』)。開業時には、すしの中に1朱銀を仕込んで客に配り、後は、金に糸目をつけずに贅沢な材料を吟味した。「玉子は金、飯は水晶」と比喩され値段が破格に高かったことは多くの文献が伝えるところである
庶民は羨望の対象
松がずしの動きに追随したのか、与兵衛ずしなど他のすし商も高級化に向かった。奢侈を禁じた天保の改革(1841~43)では、実に200人ものすし屋が処罰された。しかし、高級店舗が「名所」として挙げられ、川柳にまで詠まれているところから察すれば、そうした高級化路線は庶民感情に逆行するものではなく、逆に庶民はこれらのすし商羨望の対象と捉えていたと思われる。ゆえに、天保の改革以後、高級なすし商が廃退することなく、むしろ高級化はますます進んでいった。
握りすし屋の変容
露天屋台店
日没と同時に辻々で店が開いたものだった。姿ずしや箱ずしとは異なり少量ずつ製することができる握りずしは、露天屋台店での商売に好適だったのであろう。従来は「作り置き」だった商い方法も、売れのころを出さないよう、客の注文に応じて握るように改まっていった。 は酔客や悪所帰りの客を相手にしていたため、すし屋台は、男の場であった。客の側は立ったままで数個つまんで立ち去るのが常の光景である。江戸っ子はこれを粋と呼び、すし屋で満腹するのは野暮とさえ言われた。要するに、ショットバー感覚の気楽な軽食やが、露天のすし商であった。
料亭風のすし商
客を座敷に上げて酒を供し、別室で作ったすしを運び込んだ。当然、そのすしには職人の技巧が光るが、原則として、客と調理人が顔を合わせることはない。料理も「おまかせ」である。客は、酒とともにゆっくりと食事を堪能する。かっての大尽遊びに象徴されるごとく、これが許されたのは、ごく一部の富豪連中であった。それゆえ店側も、容易に大衆に迎合する必要がなく、調理技術を洗練させてゆけた。
屋台と店舗の融合
このように完全分離していたかに見えたふたつの商法であるが、大正あたりに、双方の融合が始まる。交通面と衛生面から、都市から屋台は追放される。ゆえに、屋台商人も店を構えることを余儀なくされる。他方で、注文に応じて目の前ですしを製してくれるやり方は、すでに大衆の人気となってきた。 固定店舗を構えるすし商もその流れには逆らえず、結果、屋台と店舗をドッキングさせたような店が生まれた。
食べ方の能書き
すしの注文順序やつまみ方、醤油のつけ方などが、うるさく言われるようにもなった。これらは基本的に握りずしに関するものであるが、もちろん、かっての屋台であれば取り沙汰されるはずはなかった。 また、高級料亭風のすし屋では、客は個室に通されるから、他の客の目を気にする必要もなかった。要するに、握りずしの食べ方は、異なるふたつの商法が融合した以後の産物だと考えられる。 以前であれば、個室の中で自分の好きな方法で食べていた旦那衆達は、屋台方式の進出にともない料理屋の中に設置されたカウンターで、他者と袖摺り合わせてすしを食べることになった。
小うるさい作法
旦那衆達は道楽半分もしくは、自ら特権意識の誇示のために、小うるさい作法を作って楽しんだものと想像される。
一般客には入りづらいすし屋に
低廉な露天売りがなくなって、店舗売りだけが残った以上、握りずしが高値で商われることはやむ得ないが、それにとどまらず、客と店が連帯して握りずしを必要以上の高級和食に仕立て上げてしまった。やがて、握りずし屋は、一般客には入りづらい空間の評価を得ることになる。
握りずしのの全国展開
全国制覇したすし店
最も新しく登場した形態ながら、ここまで全国制覇をなし遂げたには、いくつかの要因が考えられる。明治維新政府が、西欧文明への追従を急ぐあまり、「東京弁」を共通語を設定したことからもわかるように、東京の文化を標準とした。すしで言えば、握りずしがスタンダードな形態ということになる。こうした価値観は、近代化の波とともに、次第に全国民へと伝え込まれていった。 また、大正12年(1923)の関東大震災は焼け野原に、焼け出された人の何割かは地方へ移住した。その中に握りずし職人も含まれており、握るずしの調整技術の地方進出を促進することになった。
「飲食営業緊急措置令」
昭和22年(1947)戦後の食糧難により、飲食業の営業を事実上禁止したものであるが、東京のすし組合が、一合の米と引き替えに握りずしを10個渡すという行為を、「飲食業」ではなく「委託加工業」だと主張して当局に認めさせ、結果、すし商を「正当な商売」として続行させることができた。これに準じて各地の組合も同様許可を得、握りずしが、全国に定着することになる。
高度成長期と社会変革
戦後、食糧事情が好転し、高度成長期の到来で、各地の伝統文化は急速に衰退する。 女性の社会進出や核家族化、生活パターンの変化などの社会変革ともあいまって、家庭でのすし作りの機会も減り、すしは「購入品一辺倒」へと傾く。その受け皿になったのが、各地で根づいていた握りずし屋であった 4.廉価なすしの復権 オイルショック以後の低成長期になって、も、握りずしの人気はおさまらず、むしろ、廉価な持ち帰りずし屋や回転ずし屋の急成長で、握りずしは人々の日常生活へ深く入り込む結果となった。これはかって屋台で好評を博した気軽な握りずしの復権とも見ることができる。
松がずしに相通ずるすし店
高級化した握りずし屋も、高度成長期には、いわゆる社用族の接待などに支えられ、その存在を確固たる物にした。大衆価格の店とは違った方面に特化させ、客に特権意識を持たせるような雰囲気作りをしたことは、かの松がずしに相通ずるところがある。 低成長期にやや下火になった感もあるが、昭和末期のバブル期においては、高級品を志向する大衆の支持を受け、再び人気を博した。 こうして握りずしは全国規模で定着し、幕末同様。低廉な店と高級な店とが併存することとなった。