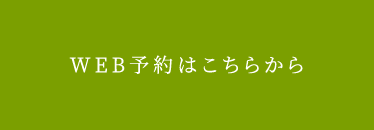鮨を知る
 UOTAKE SUSHI
UOTAKE SUSHI
地方のすし

2021年10月2日
北陸東海地方
アユ(岐阜県)
作り方
岐阜市内の6件を数える鵜匠家でのみ伝承されてる。使うアユは落ちアユで、9月末あたりから獲り溜めておく。腹を出し、真っ白になるくらい強く塩漬けにする。アユは雄アユが好まれ、メスは産卵後ゆえ身が細っているなどの理由であまり好まれな。11月の末、これを塩出しし、あらためて皮やヒレを取り除く。
ご飯は普通に炊いて、冷めたら、水気を取ったアユの腹に詰める。 桶にアユを並べ、一段並べ終わったら「フリメシ」と称し、水洗いしたご飯をパラパラとアユの上に散らし再びアユを並べる。八分目ほどになったらご飯を厚めに置き、竹皮を置いて落とし蓋と重石をする。重石の脇から桶の中に水を張ると、中身と外気が完全に遮断され密封される。こうして、年末まで発酵させる。
将軍家御用達 関ケ原の戦い(慶長5年<1600>)の後、徳川家康が岐阜に立ち寄り、このアユずしを食べて賞賛したという。これが契機となったか、岐阜のアユずしは将軍御用となり、以後、幕府が倒れるまでの長きにわたって献上が続いた。この地を治めたのは尾張徳川家で、尾張藩はその威信にかけてアユの捕獲から搬送に至るまで厳しく管理した。
天下一の逸品 アユを獲る日は、将軍がこれを食べる日から逆算して決められた。また、「御鮓所」「御鮓屋」などと称した調整役は世襲制を敷いた。その調整所から代官所に至る道は「御鮓街道」とも呼ばれるている。江戸までの道中は、老中の奉書が先触れにまわり、厳密なる日程で宿次されていった。
尾張家が御三家である上に、すしの献上が数量・回数ともに他の献上ずしより群を抜いて多かったために、美濃のアユずしは「天下一の逸品」の誉れを欲しいままにした。
洗練された鵜飼技術 このすしの特徴として、アユは「鵜アユ(鵜飼で獲れたアユ)」を使うという規定があった。このため尾張藩は鵜飼を保護し、鵜匠達には少なからぬ特権を与えていた。
結果、岐阜の鵜飼技術は他に比較にならぬほど、洗練されるに至る。 その後、幕府が倒れた時に後ろ盾をなくし、特権維持に不安を持ったことは言うまでもない。
彼ら新権力たる皇族への接近を試み、有栖川宮家にアユの献上をした。 アユずしもその中に含まれていたものの、やがて糀漬けへと変わる。
はるか昔の遺物
前例踏襲に次ぐ前例踏襲で、家康のころと同じ製法のすしであったのだろう。世間からすれば、はるか昔の遺物として映らなかったのである。「天下一の逸品」は、名声こそ残ったが、現実にはほとんど省みられることなく、地元の文化の表舞台から消えていった。
ホオ葉ずし(岐阜県)
特徴
美濃地方東部と飛騨地方中南部・郡上地方で作られる。
形態
握りずしで、すしをホオ葉でくるむのでこの名がある。ホオの新芽が大きくなる初夏から、葉が固くなる秋までの料理で、とりわけ初夏のころのものは、田植え時の弁当や間食として用いられた。
作り方
「乗せホオ葉ずし」は、すし飯をこぶし大に握って、やや平たくし、これをまずホオ葉の上、葉の中央から葉元(葉のつけ根)側半分に置く。その上に、酢締めのマス(またはサバ)の切り身・甘煮シイタケ・塩茹でしたフキやキヌサヤ・川魚の甘露煮・しぐれ煮錦糸卵・紅ショウガなどを彩りよく飾ってのせる。
さいごに、葉先半分をすしにかぶせる。これを盆や浅い桶などに並べ重ねて、全体に少し押しをかける。 「混ぜホオ葉ずし」は、あらかじめすし飯に酢締めマスのほぐし身・白ゴマ・刻みショウガなどの具を混ぜ合わせておく。これを俵型に握って、「乗せホオ葉ずし」と同様にホオ葉の半分側に置き、葉を二つ折りにしてすしをくるむ。その後、押しをかけるのも同じであるが、概してこちらの方が、具の内容が数少なく、やや質素な感が否めない。
葉っぱずし
特徴
福井県永平寺町界隈で作られる握りずし。葉で包んで仕上げるのでこの名前がある。 単に「葉ずし」と呼ばれることもあるし、中の具から「マスずし」と呼ばれることもある。
包むのは河畔に生えているアブラギリの葉で、地元では「すしの葉」と呼ばれる。9月の葉がやわらかくて喜ばれ、少し陰干しした葉で包んだすしが秋祭りの食卓に上がる。
すし、は手のひらサイズに握ったすしの飯の上に、酢締めの紅マスとショウガを乗せる。これをアブラギリの葉で包み、包んだものを箱でキッチリ押さえつける。酢を効かせ、かつしっかり押して葉で密封したすしは、そのまま1週間ほど待つという。
サバずし(福井県)
尾頭がついた姿のまま 若狭地方の正月料理として知られる一方で、夏場にも漬けることがある。 尾頭がついた姿のままで発酵させるナマナレだが、糀を使っているゆえ、改良型のナマナレである。夏に漬けるのは5~6月のサバで、塩漬けしてからご飯に漬け直し、秋祭り用にとる。
ヘシコサバを使う
このように塩サバを使うこともあるが、この地方に独特なのは,へシコト呼ばれる糠漬け(ぬかずけ)サバを使うことである。
ヘシコサバは、春の産卵前のを漬けたのが美味である。
作り方
糠漬けサバの糠を洗い流し、塩出してから皮を剥ぐ。ご飯は、冷めたら糀(こうじ)を混ぜ、背開きになっているサバに詰める。このサバを桶に並べ、一段終ったらまた・・・、という具合に繰り返す。
一杯になったらコロビ(アブラギリ)やバランの葉を置き、ワラの三つ編みを縁に巻いて,落とし蓋と重石を乗せる。夏なら10日、冬なら20日ほどで食べられる。桶の表面にシラトリ(白いカビ)が吹くと食べごろになっている。
ヘシコは発酵ずし=保存食 ヘシコは,それ自体保存食で1年以上も持つ。ところが,ヘシコのすしは, せいぜい食べごろは2週間程度である。すなわち,すしにすることで賞味期間を短くしているわけである。
これを保存食と呼ぶならば、それはあまりに愚劣な方法でしかない。 そうではなく,すしはヘシコとは異なった風味を楽しむ「料理」だと考えれば、この行為は容易に説明がつく。つまり、「発酵ずし=保存食」とは断定できないことを,このすしは物語るっているのである。
カブラずし(石川県)
加賀の郷土料理 金沢市を中心とする加賀の郷土料理として名高いが、かってはより広範な地域で作られていたらしい。現在でも,わずかながら、能登地方での伝承が見られる。野菜(カブ)と塩魚(ブリ)を米と糀で発酵させるイズシの代表格であるが、北海道・東北地方のイズシが魚主体であるのに対して、カブラずしはその名とおり,野菜の比重が多く,同じイズシ類でも東北のものとはやや趣を異にする。
作り方
カブを,やや厚めの輪切りにし,その半分くらいの厚さのところに,さらに切り目をおれて,から3日ほど薄塩でしんなりさせる。その後,カブに漬けた切り目のところに、薄切りした塩ブリをはさむ。一方、米と糀を合わせてぬる燗ほどの暖かさに保ち,固めの甘酒を作る。桶に甘酒状のものを塗りつけたカブを並べ,段重ねに詰めてゆく
重しをして2週間ほど発酵させると出来上がる。
箱ずし(石川県)
特徴
「加賀ずし」とも呼ばれる加賀地方の人寄せ料理で,祭りの集中する春秋にはとくによく作られる。
別名「御贄ずし」(おにえずし) 金沢市南郊の白山比咩神社(ひめじんじゃ)の五月祭礼は、別名「御贄祭り」。 「贄」とは神社への奉納物のことで,お下がりに魚を箱ずしに仕立てたものだという。やがて,祭礼時の箱ずしのことを「御贄ずし」と呼ぶようになった。 現在では金沢駅弁の商品名となったこともあって,その名が全国的に知られている。
作り方
箱のそこに笹の葉または薄板を敷き,すし飯を広げてならす。その上に,魚の臭みを取るためであろうか,塩もみした薄切りダイコンや刻みショウガ・ユズ皮などを置き,その上に魚を乗せる。魚は新鮮な旬の魚をおろしてそぎ切りし、酢締めにしたもので、春なら小ダイやサヨリ、秋ならシイラ・イワシ・アジなどが使われる。かっては、魚種がやや乏しくなる夏場には,フグのスジ(フグのおろし身の糠漬け)を買ってきて,具に使ったという。一段終えたら笹の葉か薄板で仕切りをし,また繰り返す。箱一杯になったら,落とし蓋をして重石をかける。翌日まで置くと,味がなじむ。
笹ずし(石川県)
特徴
石川県加賀地方、とりわけ金沢市近郊の郷土料理。祭礼など客寄せの時よく作られる。 華屋与兵衛が嫌ったすし 江戸の末期、江戸の華屋与兵衛は「握って魚身を貼ったすし飯を笹の葉で仕切りをして,箱に詰めて押さえつけたすし」を嫌って、手で握るすしを考案したとの伝説があるが,この笹ずしは,まさに華屋与兵衛が嫌ったというすし、すなわち古風な握りずしの特徴をもっている。
作り方
すし飯を手のひらサイズに握り,やや平たくして酢締めのマスの切り身を乗せる。笹の葉は2枚を一組として十文字に重ね,その中央に先のすしを乗せ、四方から包み込む。これを押し箱の中に並べて,落とし蓋をして重石を置き,半日から一日,味をなじませる。
ひねずし(石川県)
特徴
能登半島北部で作られる発酵ずし。一部で酢を使うが、糀などの発酵促進剤を使用せず、こうした形態は、北陸では非常にめずらしい。 夏祭り・秋祭り・正月などさまざまな機会のために作られ,漬ける魚も発酵期間も,地域や家庭によってさまざまである。
作り方
◆秋祭り用
内陸部では、春4月にサクラウグイのすしが漬けられる。これは秋祭り用である。サクラウグイは桜の花が咲くころに獲れるウグイで、魚体が赤みを帯びており、活きのよいウグイを使うとその赤みがすしになっても残っているという。ウグイはまず10日ほど塩漬けし,内臓やエラ・ヒレなど取ってさらに約10日間塩漬け。その後3枚におろして(小さいものはそのままで)、酢に漬ける(ただし,昔はあまり酢に浸さなかった)。これを冷めたご飯とともに,桶に段重ねに詰めてゆく。間には刻みニンジン・ナンバ〔赤唐辛子〕・サンショウ葉をふる。一杯になったら落としぶたをし,重石を置き、辛目の塩水を張っておく。
◆正月用
アジ・サケ・サバ・シマダイなどを用い、こちらには大根も入れる。おおむね、10月ころ漬ける。
◆夏祭り用
海岸部では、夏祭り用にアジのすしが作られる。アジは2~3月から塩漬けにしておき、5月にすし漬けをする。夏祭りは8月下旬だが、7月ごろに「味見」と称して食べ出すこともある。寒冷地は発酵促進剤を使用
北陸から東北地方の日本海側にはイズシ系の発酵ずしが広く分布している。イズシの特徴のひとつは発酵促進剤として糀を用いることで、そのことを、古式ナマナレの「寒冷地対応結果」と解釈する者がいる。つまり、ナマナレの普通の
作り方
では〔寒冷地ゆえ〕発酵しないので、促進剤の糀を混ぜるようになったというのである。
ひねずしは発酵促進剤を使用しない イ、北陸から東北地方の日本海側の地域のイズシは大半正月料理として冬場に作られる。冬場の東北・北陸が寒冷であることも事実である。けれども、ひねずしは、北陸地方の発酵ずしでありながら、発酵促進剤を用いない。他方で、より早く酢っぽくするために酢を使うという工夫をしている。このことは、ナマナレが寒冷地に適応してイズシになったと単純に解釈することに警鐘を与えるものである。
ロ、正月用のひねずしは、調整期を秋まで繰り上げることによって比較的寒くない時期から発酵を開始させ(多くのイズシは11月末~12月になって調整)、さらに酢を使うことで最初からある程度の酸味をつけている。
柿の葉ずし
加賀地方南部で見られる早ずし。柿の葉で包み込むのではなく、これを皿代わりにするもので、形態的には握りずしに属する。
作り方
すし飯を手のひらに納まるくらいの扁平な球状に握る。上に貼るのは酢締めした魚で、マスやシイラがよく使われる。その裏側にも干しエビや紺海苔(青く染めた海藻)を貼る。
これを柿の葉の上に置き、盆などに重ねてゆく。最後に上から皿などを伏せ、これを重石としてしばらく置く。また、すしの上下に柿の葉を貼り、箱の中で押しをかけることもある。
かぶらずし(富山県)
越中富山藩は加賀金沢藩と共通
越中富山藩は、寛永16年〔1639〕に加賀金沢藩から分藩した。そのため文化的には金沢藩と共通する点が多く、カブラずしもその一例だと思われる。製法も調整時季も加賀のそれとほぼ同じである。
越中富山藩と加賀金沢藩の違い
あえて違いを探すならば、富山のカブラずしはブリと並んでサバをもよく使うことと、添えるニンジンを花切りにしないことがまま見受けられること、さらに、カブを輪切りにせず、乱切りにして魚と混ぜることがある。
かってはサバはブリより低廉であったことを考え合わせれば、富山のカブラずしの方が、やや庶民的で技巧に欠ける感が否めない。
マスずし(富山県)
マスずし(富山県) 富山の土産物の筆頭に挙げられるほど有名であるが、その歴史は案外新しい。一部の業者がラベルに乗せている「享保年間に成立。将軍家献上。・・・・」裏付けに乏しい。
商品としてのマスのすしが盛んに文献に登場するのは明治以後である。明治末年には、今のようなマスずしが富山駅で駅弁として商品化され、全国的に販路を開くきっかけになった。
押せずし(富山県)
富山県呉東地方の箱ずし。主に結婚式などの祝事に作られ、引き出物として持ち帰らせたりもする。
具は焼きサバで、すし箱半分くらいの深さまでご飯を詰め、ほぐして甘酢に浸しておいた焼きサバの身を散らし、再び飯を重ねサンドウィッチ状にする。最上部にはタカサゴ(細い糸のような海藻で、青く着色してある)を散らしたり、浅草海苔を貼り付けたりする。その後、落とし蓋をして半日以上ギッチリ押し付ける。
切りだめずし(静岡県)
名称の由来 静岡県中伊豆町で顕著に見られるすし。同町内で最も盛んに作られる地区の名をとって、「原保ずし」(わらぼずし)とも呼ばれる。 「切りだめ」とは浅い木箱で、つき上げた餅を収めたり、切った餅を並べておいたりする。
西伊豆の松崎町でも、「ホイ盆(餅箱)で同様なものを作り、「おっつけ(「押しつけ」の意味か?)ずし」と称している。
作り方
この「切りだめ」にすし飯を敷いて軽く押さえ、そこにヘラで薄く筋目をつける。筋目は格子状で、長辺を6~8等分、短辺を4~5等分するくらいの大きさである。次に、このマス目に従い、甘く煮付けたシイタケ・ニンジン・ササゲやそぼろ・卵焼きなどの具を置いてゆく。
供し方
食卓へはこの「切りだめ」に入ったままの状態で出され、杓子を削って作ったヘラ(調整時に飯に筋目をつけたもの)が添えられる。 食べる側はこのヘラで、好みのマス目部分を切り出し、すくい起こして個々の皿に盛る。
特徴
このすしは、形態的には混ぜずしの類になるが、箱に詰めた飯に押圧を加える点で箱ずしの要素も併せ持つ。 また、最大の
特徴
は、箱に作ったすしを箱から出して切り分けるのではなく、木ヘラですくい起こす点にある。実はこの方法は、19世紀初頭の料理本に見られるものである。 箱ずしから混ぜずしへの変化 享和2年(1802)の『名飯部類』に、通常どうり箱ずしを作った後、すしを箱から抜き出さずに、さじや箸ですくい起こす「起こしずし」というものが紹介されている。大阪では「すくいずし」の名で商品化もされたというから、世に好評を博したのであろう。ともあれ、これが箱ずしから混ぜずしへの変化の第一歩だったことは疑うことはできない。 その意味では、この切りだめずしは、混ぜずしの発祥期における形態を持っていると言える。 ちらしずし 炊き込みご飯や混ぜご飯を見て、「ここに合わせ酢を混ぜれば、ちらしずしになる」と思われた方はいないだろうか。 実際にこれをやってみれば、とりあえずちらしずしの体裁と味は整うから、ちらしずしの発祥を炊き込みご飯や混ぜご飯に求める見方もある。いや、現実にはこうして生まれたちらしずしもあるだろう。 しかし、すしの歴史の流れを見る時、非常に面白い発生エピソードがある。原型は、箱ずしだという。 箱にご飯を詰め、上に具を貼って押し、それを抜き出して小切りにする。ご飯と具との位置が逆転することもあるが、箱ずしの作り方はだいたいこうだ。 ところが、無精な者もいたもので、この「箱から抜き出して、小さく切り分ける」という工程を省略してしまった。押しをかけた後にふたを開けて、そこにできあがっているすしを、匙(さじ)ですくい取るのである。匙で寿司を起こすから「起こしずし」と呼ばれたこのやり方は、大坂の堂島では「すくいずし」と名付けられて商品化されたという。この話は、享和二年(一八〇二)の『名飯部類』に載っている。 せっかく押しをかけて固めても、匙ですくいだされては、すしはバラバラになってしまう。さればいっそのこと、最初から押しつけなければよい。こうして、ちらしずしが生まれる。 すしは、箱ずしはもちろん、姿ずしも巻きずしも稲荷ずしも握りずしも、多かれ少なかれギュッと押しつける工程を持っている。ちらしずしだけが、唯一その例外。だから、このすしの「発明」は、すしの歴史の中では画期的とも言える。 箱の中にすしを作り、それを木ヘラですくい起こすという、まさにちらしずし発生直前の様子を思わせるすしを、現在、私はふたつ知っている。ひとつは静岡県中伊豆町の「切りだめずし」。盛んに作られる地区の名を取って「原保(わらぼ)ずし」とも呼ぶ。いまひとつは、兵庫県但馬地方の「まつぶたずし」。「まつぶた」とは「切りだめ」と同じく、すしを入れる浅い木箱のことだ。 画期的な発想は、細々とながら、受け継がれている。 ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。
げんなりずし(静岡県)
名前の由来 静岡県東伊豆町稲取地方に伝わるもので、形態的には押しぬきずしに属する。
名前の由来は、あまりの分量の多さに、食べ手が「げんなりする」ところから、という説と、祝い事だけに「ゲン〔縁起〕がよくなるように」と願って、という説がある。
用いる道具 一合桝ほどの大きさの容器にすし飯を詰めて固める。用いる道具には底板が無く、外枠と上から押さえつける落とし蓋で構成される。よって、道具は、「すし箱」というより「すし枠」「押し抜き型」と呼ぶのが妥当かもしれない。
作り方
一合桝ほどの大きさの容器にすし飯を詰めて固め(中には甘煮のニンジンなどを仕込む)上に具を貼ったものである。 具は、マグロ刺身・そぼろ・卵焼き・甘煮のシイタケで、そぼろは白いままのものと赤く色つけしたものの2種類を準備して、合計5種類の具とする。
すしは、この5種類の具をそれぞれ別々に貼りつける。したがって、具の異なるすしが5点できるわけで、これで1セットとなる。 マグロ刺身も卵焼きもシイタケもすしの上面を覆うような大きさに切ってあり、これを小切りにしておくことはない。魚屋でマグロを買う場合、「げんなりずしにする」と言えば、ちゃんとすし枠の大きさに合わせて切ってくれる。
用途
主に、結婚式や上棟式などの祝事に作られ、先の5つのすしがまとめて皿盛りにされる。折り詰めとなって引き出物に用いられることもある。
サンマずし(静岡県)
由来 伊豆の南部海岸地方で作られる。「姿ずし」と称して売られているものあるが、実際には頭を落としてあり、完全なる姿ずしではないことが多い。 周辺ではサンマのすしはめずらしく。一説には、紀州の漁民によって、風待ち港だった西伊豆の田子の地に伝えられたのだという。
確かに和歌山県や三重県の熊野灘沿岸ではサンマずしの習慣が顕著である。
作り方
サンマは腹開きにして内臓を取り、塩で締めた後、背骨をはずして酢締めにする。このサンマにすし飯を抱かせ、魚の姿状に戻し、巻すで成形する。生臭を消すため、飯に刻みショウガを混ぜたり、魚身の上に薄切りショウガをあしらったりすることがある。 現在はこの状態で供されるが、かってはこれをたくさん箱に詰め、落とし蓋をして一晩重石を置いた。結納の時などには、これを箱ごと媒酌く人に贈ったものだという。 下田市白浜の白浜神社の秋祭り〔10月下旬〕にもよく作られ、このころのサンマが、すしには一番よいとされる。
田子ずし(静岡県)
由来
静岡県西伊豆町の田子地区に伝わる箱ずし。田子は古くから漁港としてにぎわっていた。風よけの港で、江戸とか上方を結ぶ舟の避難港でもあった。 この地に箱ずしがあるのは、一説には関西の箱ずし文化が漁民によって伝えられたからだとも言われる。
作り方
海辺の街であるが、生ぐさは使わない。具は、シイタケ・カンピョウ・コンニャクなどを甘く煮たもので、いわば五目ずしの具と大差ない。キッチリ押さえてあるため2~3日は日持ちすが、日が経ったものはあぶって食べることもある。
特徴
このすしのユニークな点は、他の箱ずしのほとんどが、飯の上に具が乗るように作られるのに対し、ここでは具の上にさらに飯を乗せることであろう。 箱の中で、具の層の上下にすし飯の層を作り、結果、切り出したすしは、飯の間に具がはさまっている。まるでサンドウイッチのような状況を呈する。
箱の中に敷くのは山ミョウガの葉である。通常、ミョウガ葉は冬場に枯れてしまうが、伊豆の山ミョウガは、1年を通じて緑の葉を出しているという。 希少な存在
実はこうしたサンドウイッチ状にするのは、享和2年(1802)『名飯部類』の中に紹介されており、目新しい技法ではない。が、現在の箱ずしはいずれも飯の片側にしか具がついておらず、田子のすしは希少な存在と言わざるを得ない。
ヤマメずし(静岡県)
静岡県静岡市の最北。静岡駅から車で走ること2時間。南アルプスの山懐で、大井川最上流部に位置する静岡市田代地区では、毎年8月に諏訪神社の祭礼、通称「ヤマメ祭り」がおこなわれる。ここで奉納される神饌のひとつを一部の学者が「やまめずし」と名づけた。これを、日本では唯一粟飯を使った姿ずしとして注目したのである。
祭りの幕開けは8月20日始まる。当番に当たった者はこの日、まだ夜も明けきらぬ早朝から、田代の本村からさらに大井川をさかのぼった明神谷でヤマメ釣りをおこなう。神饌となるヤマメはここで捕る決まりとなっており、そのため明神谷は、ふだんは禁漁になっている。
めいめいに別れ、奥の谷まで入り込んでヤマメを釣っていた男達は、正午近くになるとカヤゴヤと称するやや開けた川原に集まってくる。ここで、長さ2メートルほどの細い丸太3本を組んで立て(これをカワクラという)、その中央に、釣ってきたばかりのヤマメを腹出しして吊るす。そして正午丁度に一同がカワクラの前に座し、長老もしくは氏子総代が大祓の祝詞を奉上する。この儀式が終わるとちっとした直来があり、ザコ(小魚)のぶつ切りやハラワタの味噌あえを肴にして酒がふるまわれる。
その後、ヤマメはカワクラから降ろされ、口と腹にイタドリの葉詰め、ツガの樹皮とシナの紐で梱包されて田代本村にある宮司宅まで届けられる。棒の中央につるしさげられたこのヤマメは、二人の男の手のよって交代で運ばれ、ヤマメの包みがけっして地に着けられることはない。
作り方
祭礼日は8月26日、27日で、その1週間ほど前に、ヤマメを釣っておく。 アワを炊き、冷めたら塩味をつける。ヤマメはアギ(エラの裏の赤い部分)を取り、腹にアワを詰め、桶に並べる。一段並べ終ったらアワをふり、またヤマメを並べる。この時、ヤマメは一定方向を向けておく。最後にふたを置くが、重石はしない。
切りずし(愛知県)
道具の名称 すし箱を段重ねにして枠にはめ、枠にクサビを打ち込んでまとめてすし箱を押さえつける道具がある。一部で「ヤジメ」と称されるこの道具は、通常「すし箱」もしくは「箱ずし」とよばれ、その分布は、ほぼ濃尾平野と一致する。 通常、箱は5つを1セットとし、これを収めるような枠がある。ひとつの箱には約2合のすし飯が詰まる。 大家になるとこのセットをいくつも持っており、冠婚葬祭時で客寄せをした時などは、すしを箱ごと客に持ち帰らせる。この箱は、持ち帰った側が持ち主の家を招いた時に、同様にすしを詰めて持ち帰られてゆくことになる。 このため、箱には家紋や持ち主名を焼き印しておくのが常であった。
作り方
具は、ニンジン・シイタケ・角麩・卵焼き・キヌサヤ・カマボコ・しぐれ煮〔アサリやシジミの甘露煮〕・ハエ〔子ブナ〕などで、時代やや下がってから、生ぐさ物〔酢サバの切り身)が入るようにもなった。また、知多半島では焼きアナゴを入れる。これらの具は適宜準備し、すし飯の上に数種、筋状に並べてゆく。 最近は、具のほうは昔ながらのニンジン・シイタケなどばかりではなく、酢サバの切り身を交えたり、酢サバの半身を一面に貼り付けたりして、生ぐさ物がずいぶん使われるようになった。
並べ方
箱の縁に対して斜めになるように置くことがまま見られる。これは、後で小切りにした時、具の組み合わせが多様になるようにとの配慮からである。 寄せの行事の衰退 昨今では、客寄せの習慣も家庭ですしを作る習慣も衰退し、また、家族の人数も減ったことから、段重ねにする箱ずし道具は使われることも少なくなったが、かってはこの道具が見られなかった周辺山間部では、逆に注目されている。かかるところではまだ客寄せの習慣が残っているからであろうか、ともあれ、新しいすし箱を購入する家が現実にあり、分布域はむしろ広がっている。 道具の名称すし箱を段重ねにして枠にはめ、枠にクサビを打ち込んでまとめてすし箱を押さえつける道具がある。一部で「ヤジメ」と称されるこの道具は、通常「すし箱」もしくは「箱ずし」とよばれ、その分布は、ほぼ濃尾平野と一致する。
段重ねの箱
常、箱は5つを1セットとし、これを収めるような枠がある。ひとつの箱には約2合のすし飯が詰まる。
大家になるとこのセットをいくつも持っており、冠婚葬祭時で客寄せをした時などは、すしを箱ごと客に持ち帰らせる。この箱は、持ち帰った側が持ち主の家を招いた時に、同様にすしを詰めて持ち帰られてゆくことになる。
このため、箱には家紋や持ち主名を焼き印しておくのが常であった。
作り方
具は、ニンジン・シイタケ・角麩・卵焼き・キヌサヤ・カマボコ・しぐれ煮〔アサリやシジミの甘露煮〕・ハエ〔子ブナ〕などで、時代やや下がってから、生ぐさ物〔酢サバの切り身)が入るようにもなった。また、知多半島では焼きアナゴを入れる。これらの具は適宜準備し、すし飯の上に数種、筋状に並べてゆく。
最近は、具のほうは昔ながらのニンジン・シイタケなどばかりではなく、酢サバの切り身を交えたり、酢サバの半身を一面に貼り付けたりして、生ぐさ物がずいぶん使われるようになった。
並べ方
箱の縁に対して斜めになるように置くことがまま見られる。これは、後で小切りにした時、具の組み合わせが多様になるようにとの配慮からである。
客寄せの行事の衰退
昨今では、客寄せの習慣も家庭ですしを作る習慣も衰退し、また、家族の人数も減ったことから、段重ねにする箱ずし道具は使われることも少なくなったが、かってはこの道具が見られなかった周辺山間部では、逆に注目されている。かかるところではまだ客寄せの習慣が残っているからであろうか、ともあれ、新しいすし箱を購入する家が現実にあり、分布域はむしろ広がっている。