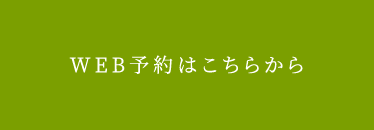鮨を知る
 UOTAKE SUSHI
UOTAKE SUSHI
古代のすし

2021年10月3日
奈良・平安・鎌倉 ミサゴずしの伝承
「日本書紀」景行紀に天皇の治世第53(西暦77)年東国に幸したとき、淡(安房)の海峡を上総へと渡ろうとすると、ミサゴの鳴く声がした。どんな形の鳥だろうかと追って行くと途中で海の中に白蛤があるのが見つかった。磐鹿六雁がそくざにその白蛤をなますに作って進献したので、天皇は喜び、六雁に膳大伴部を賜わったとある。
後世になると、このミサゴをば、すしの発明者とする。この鳥が海中の魚を取ると巖の上の自分の巣にためておく(念の入ったのはその魚に自分の尿をかけておくとまでいわれる)と、これに海の塩水がかかり、いつしか馴れてすしが出来るというのだ。
石田未得の「吾吟我集」(慶安2年)に ◆石かれい石もちなどと重ねつつ みさごの鮓のおもしにやする と見えるから、この伝説は江戸初期までさかのぼる。 結局、室町末か江戸初期からの和製の伝承だと思う。 この考えは江戸期の都人士に大いにもて
はやされた。しかし、どうもミサゴずしの話は都人のきじゅ机の上での創作のように思える。 別の伝承として、淡路に老夫婦がいて、いつも自分達の残飯をミサゴにほどこしていた。
この残飯と、ミサゴが取って来た魚と、海の塩水とですしができたのだという。 これなら理屈は一応通る。
雑穀のすし=ヤマメずし
静岡県静岡市の最北。静岡駅から車で走ること2時間。南アルプスの山懐で、大井川最上流部に位置する静岡市田代地区では、毎年8月に諏訪神社の祭礼、通称「ヤマメ祭り」がおこなわれる。ここで奉納される神饌のひとつを一部の学者が「やまめずし」と名づけた。これを、日本では唯一粟飯を使った姿ずしとして注目したのである。
祭りの幕開けは8月20日始まる。当番に当たった者はこの日、まだ夜も明けきらぬ早朝から、田代の本村からさらに大井川をさかのぼった明神谷でヤマメ釣りをおこなう。神饌となるヤマメはここで捕る決まりとなっており、そのため明神谷は、ふだんは禁漁になっている。
めいめいに別れ、奥の谷まで入り込んでヤマメを釣っていた男達は、正午近くになるとカヤゴヤと称するやや開けた川原に集まってくる。ここで、長さ2メートルほどの細い丸太3本を組んで立て(これをカワクラという)、その中央に、釣ってきたばかりのヤマメを腹出しして吊るす。そして正午丁度に一同がカワクラの前に座し、長老もしくは氏子総代が大祓の祝詞を奉上する。この儀式が終わるとちっとした直来があり、ザコ(小魚)のぶつ切りやハラワタの味噌あえを肴にして酒がふるまわれる。
その後、ヤマメはカワクラから降ろされ、口と腹にイタドリの葉詰め、ツガの樹皮とシナの紐で梱包されて田代本村にある宮司宅まで届けられる。棒の中央につるしさげられたこのヤマメは、二人の男の手のよって交代で運ばれ、ヤマメの包みがけっして地に着けられることはない。
室町から安土へ 生成の発生
生成の発生
1350年頃の一種の百科辞書に江鮒のすしの所見がある。江鮒のすしは後年大阪福島の雀ずしとして名物となり、その伝統が今日の小鯛雀ずしへと続く。
京都吉田神社の神職鈴鹿家の家記にも時折の献立が見え、すしも随時顔を見せる。すなわち、鮒ずし、宇治丸(鰻ずし)、柿ずし(コケラずし)、アユずしなどで、延元元(1336)年から室町初期の応永6(1399)年にわたっている。
コケラずしは今日の押しずしの原型である。 京都には東の時代の日記類が丹念に書きとめられている。「御湯殿の上の日記」天子の「御湯殿」(休息所)の奉仕し、いわば秘書役をつとめる高級女官たちが書きついでいった公式記録で、刊行されたのは文明9(1477)年~江戸初期の貞享4(1687)年まで二百余年分。
毎日の天気に始まり、宮中行事、天子への伺候客、時季時季の献上品などが書かているので、上の方の食生活の一部が推定できる。これらに見えるすしの原料はアユ、フナが普通だ。当時の鮒ずしの漬け込みは今日のように夏の土用ではなく。むしろ寒中が主で場合によれば時を選ばなかっただろうか。
武家方記録で特に重要なのが「蜷川親元日記」である。彼は室町幕府きっての権臣でことに財政方面を握っていた伊勢家の執事である。彼の日記にはその伊勢氏の秘書役として到来物が詳しく書きとめてあり、文明5(1473)年~18年間の間に59回のすしを記録している。
この59回の記録の中で注意を要するのは、生成(なまなれ)が出ていること。 アユずしの産地は公家と違い山国や和知の代わりに長良川や木曽川のものが多く、武家と公家との勢力範囲の相違がはっきりする。
応仁、文明の大戦を堺に、世は戦国の乱世へととうとうと流れていく。その間京都には東山文化の色香を何とかつなぎとめようと努力がなされており、その成果の一部はすしにも関係なくはない。
戦国時代とすしの大変化
以上これらを要約すると、すしはこの十五、六世紀、室町から戦国にかけて、急激に転回している。 第一に、材料が増えた。従来の鮒、アユ、アメノウオのほかに鯉、鰻、鱒、イサザなどの川魚、鯛、鰯、アジ、ハモなどの海魚、野菜にしても竹の子、茄子、茗荷など非常に広くなる。
第二が生成の発生である。従来のように長期間漬け込んで十分馴れさせるのではなく、比較的に短時間にあげ、飯は酸くとも魚がまだなまなましいうちに食べる。とっいっても重石は相当きかせるので、織田信長が皇居造営に際し、滋賀県から人夫を多数集めて石をはこばせたおり、京童は、
◆生成のすしにも似たる近江衆 石を重しと持たぬ日はなし と一首ものした。この歌は同時に当時の京童が、すしといえば生成を連想したことをも暗示する。
第三に、飯鮓。生成で酸めしに慣れた大衆は、もともと飯好きの日本人だけあって、さらに飯の部分を強調させた飯ずし、コケラずしに進むのは時間の問題だった。だいたい、日本の植物史を考える時、われわれの食生活が大きく転換した最初が、この室町から安土・桃山期だと考える。炊飯方法はこのころでは蒸すのから煮るに変わったし、朝夕二度の食事は三食に増加する。すしにしても、今までの純副食物なる馴れずしから生成、飯ずしなどという補食的なものに変化した。
この時代には、家柄中心の旧体制は完全にくつがえされ、慣習や規律は無視され、実力さえあればおのれの好きな方向へ遠慮なく突進できる。古風な仁は下克上だと怒るが、ある意味では日本史で一番活気があった時代ともいえる。そこで、居、食、住の生活自体も、刻々変わる世情に応じて適応、進展をしてきたわけだ。
おまけに、日明貿易がある。南蛮貿易が始まる。従来日本に見られなかった食べ物や料理法が輸入された。南瓜、西瓜、唐辛子、饅頭、羊羹、砂糖、醤油、けんちん、天ぷらなど、その数を知らない。そこで、これに乗じて料理法一般、その一例としてすしに大きな変化があって当然のことと思われる。
元禄のこと 早ずしが生まれるまで
早ずしが生まれるまで
家康が江戸に幕府を移したからといって、日本の文化の中心も江戸に移ったということにはならない。 五代将軍綱吉、年号にして貞享、元禄、宝永といったところまでは、その中心はあくまで上方であった。
ということは、すしについていえば、戦国から安土時代にかけて大きく変動したその結果そのまま温存し続けていたので、この意味で江戸初期のすしは室町以来の連続であった。
新時代の新しいすし-早ずし-は新興都市江戸で生まれた。 京都誓願寺の安楽庵策伝が所司代板倉重宗のために編んだ笑話集「醍睡笑」(寛永5年1628)はすしの説話も数々集録されており、当時のすしの面影がわかって面白い。たとえば
◆破戒坊主がアユずしを剃刀となつけてひそかにたしなんでいた話。
◆小僧がすしづめになって寝ているのを老僧がひやかしたら「このように腹に 飯の入ってないすしは知らぬ」と答えた話。
◆川を徒渉して、泳ぐ魚をアユかと問うたら「アユにしては飯つぶが付いてない」と答えた話。
◆僧と相撲として敗けた男が「こんなにすし臭い坊主は初めてだ」といった話。
◆雷のすしを食べたら「雲臭かった」という話。
すしが京の町ではアユが主流であり、それが生成で腹に飯が詰め込んであった。 また僧院でも内密にすしが漬けられていたことなどが分かろう。
この時代の俳諧狂歌を見てみると、「古今夷曲集」(寛文6年1666年)には
◆子供をば鮨にするほど持ったれどいひがなければひ干しぞする
◆仏にはまだなまりの魚の鮨菩薩界までおしかかりたや
◆鮎くての後の心にくらぶればむかしは鮨もおもはざりけり
◆魚篇に春加ははれる鮨だにもすきなお口に飽かれやはする
◆近江鮒宇治丸鮎の鮨もあれど おされぬ味は鰆なりけり
◆数おほふ江鮒のうろこ福島の人は仕馴れてよいすずめ鮨
◆青たでもそへてはなさん羽なくて 飛ぶほどうま雀ずしとは
◆秋風のふく島人のをどる(踊)とてすずめ鮨ほどあつまりにけり
「後撰夷曲集」(寛文12年1672)では
◆此魚は都に馴れし鮨ながら 世にうじ丸と人はいふなり
◆口のうちにはおと(羽音)の高くきこゆるは喉を飛びこす雀鮨かも
◆ちょこちょことおどれ(踊)どへらぬ我腹は飯の過ぎたる雀鮨かも
◆其味もよしや難波の雀ずし喉のあたりを飛ぶやうにあれ
早いえることは一様に馴れずし、ことに生成であって、宇治丸のごときも産地でではなく消費地で漬けていること。福島の雀ずしのほか、サワラのすしが特に人気があることなどである。
福島の踊りではないが、祭礼にすしは今日同様に付き物だったと見えて、「若えびす」(元禄
◆ちかうなるまつりの鮓はつきゃったかがある。
蕉門の俳諧付合を見ると 「熱田三歌仙」(貞享年1684には
◆清水をすくふ馬柄杓に月
◆面白き野辺に鮓売る草の上 東籐
◆宿の土産に撫子をほる 士山 「猿簔」(元禄4年 1690では
◆うそつきに自慢いはせて遊ぶらん 野水
◆又も大事の鮓をとり出す 去来
◆堤より田の青やぎていさぎよき 凡兆「続猿簔」(元禄年1694
◆通りのなさに店たつる秋 支考
◆盆じまひ一荷で値ぎる鮨の魚 芭蕉
◆昼寝のくせをなほしかねけり 惟然
「となみ山」(元禄7年1694)
◆点かけてやる相役の文 浪化
◆此の宿をわめいて通る鮎の鮓 浪化
◆青田うねりて夕立のかぜ 芭蕉
節は夏。漬けておいて時々上から起こして食べているのだ。 芭蕉の弟子のうちにも江戸の其角はよくすしの句をつくっているが、例によって難解の句が多い。
◆朔日に七里は出たり名古屋鮓
◆石の枕に鮓やありける今の茶屋
◆夕立や傘はやぶれて鮓の蓋
◆明石より神鳴はれて鮓の蓋
◆貫之の鮎の鮓くふわかれ哉
◆飯鮓鱧なつかしき都かな
いえることは一様に馴れずし、ことに生成であって、宇治丸のごときも産地でではなく消費地で漬けていること。福島の雀ずしのほか、サワラのすしが特に人気があることなどである。
福島の踊りではないが、祭礼にすしは今日同様に付き物だったと見えて、
「若えびす」(元禄15年1702)の付合に
◆ちかうなる まつりの鮓はつきゃったか がある。
蕉門の俳諧付合を見ると 「熱田三歌仙」(貞享3年1684)には
◆清水をすくふ馬柄杓に月 閑水
◆面白き野辺に鮓売る草の上 東籐
◆宿の土産に撫子をほる 士山
「猿簔」(元禄4年1690)では
◆うそつきに自慢いはせて遊ぶらん 野水
◆又も大事の鮓をとり出す 去来
◆堤より田の青やぎていさぎよき
凡兆 「続猿簔」(元禄7年1694)
◆通りのなさに店たつる秋 支考
◆盆じまひ一荷で値ぎる鮨の魚 芭蕉
◆昼寝のくせをなほしかねけり
惟然 「となみ山」(元禄7年1694)
◆点かけてやる相役の文 浪化
◆此の宿をわめいて通る鮎の鮓 浪化
◆青田うねりて夕立のかぜ 芭蕉
季節は夏。漬けておいて時々上から起こして食べているのだ。 芭蕉の弟子のうちにも江戸の其角はよくすしの句をつくっているが、例によって難解の句が多い。
◆朔日に七里は出たり名古屋鮓
◆石の枕に鮓やありける今の茶屋
◆夕立や傘はやぶれて鮓の蓋
◆明石より神鳴はれて鮓の蓋
◆貫之の鮎の鮓くふわかれ哉
◆飯鮓鱧なつかしき都かな
初句は、六月朔日に尾州侯献上のアユずしが、「七里の者」(七里ごと江戸まで配置してある飛脚で、御三家、出雲侯などだけに特に許されたもの)の手によって江戸へ運ばれること。
第二句は田舎風景
第三、四句は永代橋で夕立にあったときの作。
当時古傘の紙をすし桶の表に目張りに用いた。
第五、六句は送別の句である。
このころ学者としてすしを取り扱ったもののうち、
主なものは 黒川道祐 「雍州府志」(貞享元年1683)
黒川道祐 「日次紀事」 (貞享元年1683)
貝原益軒 「大倭本草」(宝永3年1708)
寺島良安 「和漢三才図会」(正徳3年1713)
貝原益軒は人も知る九州博多武士。旅行家で実地に方々見てはいるが、これもまた京大阪については時におかしい点が見える。(その代わり、九州に関しては他人の追随を許さないが。)
この点、京都ずまいの黒川道祐や大阪人の寺島良安の書いた上方の記事は安心して読めるが。
井原西鶴の「一代男」(天和2年1682) 滋賀県大津の柴屋町の遊郭を述べて
◆立よる者は馬かた、丸太舟の水主共、浦辺の猟師、相撲取、鮨屋の息子、 小間屋の若者、恋も遠慮もむしゃうやみ・・・・・ と、すし屋をあまり尊敬していない。古い時代のこととて漁夫同様の殺生商売だか都会人に嫌われたのだろう。
元禄のこと 生成すしの漬け方
生成すしの漬け方
これらの本に見えるすしの原料は 海魚→ 鯛、タチウオ、鰯、ハタハタ、マナカツオ、サバ、ツガヤ、コノシロ、ボラ 川魚→ コチ、アユ、イナ、鰻、ハス、サケ、サイ(=イダ)
貝類→ タコ、イカ、アワビ、アカガイ 野菜→ 茄子、シソ、竹の子、松茸、キクラゲ すしの漬け方を紹介すると
「生成」
真新しい魚のうろこや腸を去り、塩をふって暫時押すか、または塩水に 一夜漬け、水を切りふきんでよくふいておく。白粳米(うるち)を炊き、冷えたら桶に魚と交互に詰める。魚同志がふれないようにする。蓋をして重石をする。ニ、三日で水が上がり、また一両日で馴れる。なまぐさからず、からからず、堅からず、酸からざるを上乗とする。
「飯鮓」
精白米を三寸×一寸×一寸くらいの物相に盛り、乾魚一片を貼って硬く押す。 これをすし桶に盛り、さらに飯を入れて押してすしとする。夏がよい。馴れたら冷酒と生蓼葉(たで)をかけて食べる。
四季のすしの分類
「江戸料理集」(延宝2年1674)
春→鮒(子持ち)、鯛(切漬)、サケ(切漬)、オボコ(ボラの小さいもの)、小アユ、子ごもり、粕漬、
夏→アユ、オボロ、子アジ、刺サバ、タイ、飯ずし
秋→アユ、鮒、サケ、鯛、酢漬類
冬→鮒、サケ(切漬)、伊勢海老、鯛(切漬)、粕漬の類
「合類日用料理指南抄」(元禄2年1689)には鮒(馴れずし、早漬け)、鰻、サケ(仙台流、子籠、長期保存法)アユ、白魚、鯛などの漬けかたが出ている。
鮒ずし
寒に漬ける。えらとり、そこからワタをぬき、頭を打ちひじき、塩を十分あて、一方黒米を硬目に炊き、よく冷やし、食い塩ほどにし、飯沢山に漬ける。はじめは重石を強く、二十日したら常の加減にやや軽くする。七十日くらいで馴れる。蓋の上に塩水をはっておくこと。翌年秋冬までもち、骨も柔らかい。
鮒早ずし
酒1升に塩3合入れて煎じ、酢1合加える(四,五日おくのに入れない)。飯を冷やし、右の酒で食い塩より辛めに合わす。鮒は二時間ほど塩をし、さっと洗い、右の飯で漬ける。初め四時間は軽い重石、だんだんと押して強くする。二日ほどでよく馴れ、四,五日置いてもよろしい。
鰻ずし
鰻をよく洗って水を切り、三つ四つほどに切り、右の酒塩に辛目に混ぜて浸し、翌日漬ける。押しは中くらい
白魚ずし
魚を一日一夜塩をし、その塩水で洗い、水を切り、硬めの飯と混ぜ、出来 るだけ強い押しをする。長くはもたない。
「和漢精進料理抄」(元禄10年1697) 漬け方が今日の松茸ずしとはだいぶ違う。
松茸ずし
新しい松茸をよく洗い、切ってさっと湯をくぐらせ、硬めに炊いた白米飯を適宜塩加減し、新桶に飯、一日置いて次日食べる。
松本善甫(まつもとよしいち) について
松本善甫が酢を使って即席ずしを作り出したという説は、明治11年(1878)に81 歳で死んだ況斎岡本保考の随筆「難波江」の中で、「我が友狩谷棭斎」から聞いたとして載っている。時は延宝(1673~1680)のころという。
ところで、この「我が友狩谷棭斎」は、実は、況斎に長ずること23歳、天保6年(1835)に61歳で死んでいる。つまり、安永4年(1775)の生まれだから、況斎がこの話を30歳の時に聞いたとしても、善甫の発明から150年はたっている勘定になる。
おまけに、数多い棭斎の著作のどれ一つにも善甫のことは出ていないので、善甫がはじめて早ずし出し、時の人が従来のような生成で注文すると何日何時に又来いというので「おじゃれずし」、善甫のそれは客が待っている間に作るので「待ちゃれずし」と呼んだという伝承は、面白いには面白いが信憑性には欠けているものとされている。
しかしながら、先の「合類日用料理抄」の鮒ずしの例でもわかる通り、すしに酢を当てることは元禄には普通であったところを見ると、その少し前の延宝ころからそのような形があらわれてきたとしても、時代的に不思議ではない。
松本善甫、本人は御典医であり、しかも今日の順天堂病院の先祖にあたるが、代々れっきとした医者であったのではない。元来が会津の士で、争いで人を切り、亡命して江戸へ出た器用な男で、身すぎ世すぎに医書を何冊かかじっただけで開業したところ、運良く当たって大評判、ついに幕府の御殿医に召し出された。
江戸前の握り鮨は誰が考案したのは約200年前の文化・文政年間に開業した「與兵衛ずし」の主人華屋与兵衛と堺屋松五郎の「松がの鮓」採り入れ広めたという説があります。
又、延宝年間(1673~1695)に町医者の松本善甫(まつもとよしいち) (生年未詳~1695)考案したと言う説。 松本善甫(まつもとよしいち)が考案の早鮓は箱や重石に詰めて押すといった従来の方式を改め、手で握る「握り早漬け」の方法ですぐ作れたので「待ちゃれず」と言われた。今日の江戸前の鮨「待ちゃれず」が嚆矢(物事の始まり)ともされ、松本善甫が御殿医になる十数年前のことである。
松本善甫、本人は御典医であり、しかも今日の順天堂病院の先祖にあたるが、代々れっきとした医者であったのではない。元来が会津天満宮の神官で、争いで人を切り、名を変えてを逃れて江戸へ出た。
松本善甫なる者器用な男で、身すぎ世すぎに医書を何冊かかじっただけで開業したところ、運良く当たって大評判になり、繁盛する、ついに元禄5年(1692)幕府に召し出され、常憲院殿(第5代将軍綱吉1680~1709)に下級武士として仕えへ、禄高二百俵十人扶持(現在の年収に換算すると650万円で男女10人が生活する)を支給され、翌年の元禄6年(1693)には、ついに幕府の御殿医に召し出された。
「寛政重修諸家譜」によると 善甫曾て口科の医を善するにより、元禄5年11月23日召されて常憲院殿(綱吉)につかへ6年奥医となり、ついに二百俵十人扶持を食んだという。
彼が「待ちゃれずし」を作ったのは、御殿医になる十数年前のことである。
京阪では前から早ずしに酢を使っていたが、何といって保守的な所なので、馴れずし、生成におされていたが、それを新開地の万事に気ぜわしい江戸に持ち込んだら土地柄にマッチして大繁盛した。その仲立ちをしたのが松本善甫だった。ということかもしれない。
松本の家は五代目。安永のころ、開祖と同じく肝癪持ちがいて一を斬り、一旦改易になったが、後代百表で召しもどされ、明治の順天堂につながるという。
従来、このいわゆる善甫の改革を、時間をかけて自然発酵させて乳酸を作る代わりに、日常おなじみの酢酸を使って時間を速め、近代的にしただけではないか、とあまり重く見なされていないのは、調理学の立場から見るとはなはだ心得がたい。
乳酸が酢酸に変わったのは以前から調味のために酒をふることが行なわれた。
デンプンが乳酸に変わっていくのと平行して、この酒精が酢酸に酸化される。かくして江戸初期の生成の多くは酢酸臭を混じえており、これが食酢による早ずし化を容しめる一因となったはずだ。
田沼時代前後
贅沢すし
上方文化、そして町人文化が、元禄の全盛期を境に宝永、正徳と急激に下り坂になる。 一方、寛文ころから徐々に始まった江戸中心の武家文化の推進はその宝永、正徳ごろからようやく軌道にのり、移行はほぼ享保期、八代将軍吉宗のもとに完成する。
実際、享保、元文という時代は非常に塩っぽい時代だった。倹約令につぐ倹約令に追い打ちをかけるようなたびたびの饑饉、凶作とくる。凶作だから倹約令が出たのではない。
倹約令の方がまず世の景気を押さえたところにこの時代の特長がある。町人の自由はまったく押さえられ、しかも支配層の文化はまだ野暮ったい。
「料理網目調味抄」(享保十三年1728)に見るすし
材料
コケラずし 鯛、マナカツオ、サバ、アジ、鰹、サワラ、鰯、ブリ、ニベ、ボラ 、 鯉、鱒、鰻、シビラ 丸ずし, 鮒,アユ、ワタカ、ハス、モロコ、ハエ、オイカワ(みな川魚)
「料理山海郷」(寛延二年1749)この期のものとしては注目を要する。
イ、鰯ずしはいったん酢に漬けてから粕におろす。
ロ、巻きずしとは川鱒の切り身で、おろし大根を巻く、サケの早ずしではすしとすしの境に昆布を置くなど変わった技法が出ているからだ。後年、明治になって大阪南の「松前ずし」がサバの棒ずしを昆布で巻いていたから、サバすしといえば必ず昆布で巻くほどの大流行をきたし、ために特許訴訟までもちあがったことだが、本書ですしと昆布の関係が案外古いことがわかった。
料理書以外で、文芸作品ですしの記載がある。
なかでも、すしの道で有名なのは竹田出雲の「義経千本桜」(延享4年1742)鮨屋の段で、
◆春は来ね共花咲かす 娘漬た鮓ならば なれがよかろと 買に来る 風味も 芳野下市に 売り弘めたる釣瓶鮓 御鮓所の弥左衛門 留守の内にも商売に抜目もない(内)儀が早漬に 娘お里が片綿襷 裙に前垂ほやほやと 愛に愛もつ鮎の鮓 押さえてしめてなれさする 味い盛の振袖が釣瓶鮓とはものらし
いとあるのは、演劇的にもさることながら、釣瓶ずしが原則として馴れれずし(生成)であり、しかも早漬もあったことを物語っている点に注目したい。
田沼意次の天明期
享保、元文以来の沈滞した世間がパッと明るくなるのは、有名な田沼意次のイン フレ政策のおかげである。宝暦、明和、安永、天明と歴史上にいわゆる田沼時代なるものを画した。
田沼意次の出世コースを眺めると、
宝暦1年(1751)側衆
宝暦8年(1758)遠州相良藩主
明和4年(1767)側用人
明和6年(1769)老中格
天明4年(1784) 子息意知刺殺さる
天明6年(1786) 老中罷免
以後、意次は失意のうちに世を去るのだが、この35年間に世につちかわれた奢侈淫靡な生活態勢は、白河侯松平定信のデフレ政策(世に寛政の政治の冶というが)についていけない。
◆白河の清き流れにすみかねて
元の濁りの田沼こいしき という抵抗精神(?)はついに楽翁を失脚せいしめ、続く享和、文化、文政と江戸期最後の爛熟期を作る。 今この動きをすし史の面から追っていこう。
宝暦十(1760)年の「献立筌」に早ずしの異名がすしもどきだ。という暗示的な事がある。 松本善甫以来百年たっても、酢を使うすしがこれだけ流行していても、なを早ずしはすしの道から邪道扱いされていた証拠となるのだ。
「会席しっぽく趣向帳」(明和8年1771)には飯ずし、オボコ(ボラの子)ずし、鯛、イナ、アユ、車海老などの当座ずしが出ている。当座ずしというのは
当座ずし 随分よき白米にて少しこわめに飯を炊き、よくさまし、焼き塩をよき ほどに散らし、酢を少し茶せんにて打ち、肴を酢に漬けておき、それを並べ 押しを置ば一夜出来るというので当座といっても即席のことではない。
一応京のサバずし風にも見えるが、さらに付合には、例えば鯛では竹の子、 ククラゲ、エビ、蓼(たで)などとなっているので、むしろ大阪風の押しずしに近い。田沼時代が最高潮に達したの天明期には料理書もいろいろ一時に出版されている。
「豆腐百珍続編」(天明三年1783)に見える卯の花ずしは卯の花ずし
浅草のりに酢を少しうち、飯の代わりにキラズを入れて巻く、キラズの味は胡麻油、酒塩、つなぎは玉子。具にむしり鯛、キクラゲ、針栗、山椒など。といった贅沢な代物である。
「鯛百珍料理秘密箱」(天明5年1785)には各地のすしが出ている。 例をあげれば
ちくらずし(大阪風)
ごく新しい鯛を三枚におろし、皮と血合いとを取り、捨て作りにし、軽く酢を合わせ、飯に混ぜ(ほかの具と一緒に)漬ける。冬漬の大根漬の小口切を混ぜれば香の物ずしという。重石はきつい方が好い。
桂ずし(堺風)右と同様の鯛の作りと塩味にした飯とを酒蘘に入れ、酒を絞る男性に何回もうちつけて馴らす。堺のある酒屋がこしき仕舞にやるが、元来は 舟中で船頭がやるやり方だ。
おまんずし
塩した小鯛の腹に、酒、醤油でから炒りしたキラズを(冷えてから)詰め、重石 する。なま小鯛に塩してもよい。 江戸自慢のおまんずしが卯の花ずしだったとは少々がっかりだ。小鯛の卯の花ずしは今日越後瀬波で作っている。石見地方で鰯やコノシロの卯の花ずしをおまんと呼ぶ語源もわかった。
「大根料理秘密箱」(天明5年1785)に見える大根ずしの作り方は、 大根ずし 上皮をむき、粗い卸し金で卸し、水を絞り、具をきざみ、酢酒、塩で味をつけ、大根とまぶして押す。具は魚は酢の物、椎茸、キクラゲは味付けにする。
大根のコケラずしもあるが、漬物を薄く切って塩出しして貼るだけだ。「たこのすしにこれを合わせば風味一だんのものなり」と注している。
手柄岡持(本名平沢平格)は、「後は昔物語」(1803年)の中で、この頃の思いで話として「おまんずしは宝暦初めごろからのもので、京橋中橋「おまん」が紅という童話から名づけたらし。
そのころは当座ずしを売ることはまれで、丸い桶に傘紙の蓋をして,いくつも重ね、コハダのすし鯛のすしと売り歩いていたが、いずれも数日漬け込んだのばかりだった。」と書いていた。
「わすれのこり」(天保13年1758)で茂蔦は
◆「早春のころは、一夜明ければ小はたの鮨うり、玉子うり引きも切らず売り来りしが」 と、このころをなつかしんでいる。
江戸のすし屋
貞享4年(1687)には舟町横町に2軒あっただけだというが、天明7年(1787)にはきんとんずし、にしきずし、折りずし、江戸前地引きずし等々があったそうだ。
芝神明の祭礼にはすしがつきものだった。 「江戸町中喰物重宝記」にはすし屋が21軒出ている。 宇田川町の「亀屋」は大阪ずしが看板だ。釣瓶ずしを主にする「吉野家」といううのも4軒あり、しかもそのうち2軒は吉野下市の出店で、1軒は「弥助」と称している。また、「美濃屋」が2軒ある。長良川のアユずしだろうか。
「あずまずし」「若葉ずし」「初音ずし」「翁ずし」などいう近代的な屋号もあるが、有名なへっつい河岸の「笹屋」の毛抜きずしも見え、それにならった笹巻きずしも4軒ある。
お満ずしは例の通4丁目の「紀伊国屋」のほかに「お満ずし」を標榜したのが2軒見える。お満は本来そこの女房が女形の瀬川菊之丞に似ているので有名だった。「紀伊国屋」のはずだが、それがすしの一種のように取り扱われているのは、それ自体特長をもっていたこと(卯の花ずし)の証拠だろう。
歌麿の「絵本江戸爵」(天明6年1786)にこれに関連した狂歌が2つ載っている。
◆夜や冷えし人にやなれし通り町 ゆき合いの間も鮓や売るらん
◆夕はてにおまんをほめて通り町 めておしあふ見勢のすし売
この狂歌からおまんずしが詰めて押して馴れさせたもので、通り町にあったことがわかる。 越智為久は60余歳になって安永、天明の交を追憶し、当時の流行物の歌を紹介している。
◆三寸紋五寸模様に日傘 こはだの鮓に花が三文 衣服の紋や模様が大きくなったり、だれもかれもが日傘をさすと共に、コハダのすしが流行したことに注目したい。
もっともコハダのすしの流行は、このころに始まったものではなく、
風来山人平賀源内は
「根南志具佐」(宝暦13年1763)で両国橋の風物を叙して
◆灯籠売は世帯の闇を照し、コハダの鮓は諸人の酔いを催す と書いている。 風来山人平賀源内の句
「風流志道軒伝」(宝暦13年1763)で平賀源内はさらに当時の坊主共の醜態をあざけって
◆柔和にんにく葱ざふすい(雑炊)、むき玉子松魚(かつお)の雉焼(きじやき)
厭離江戸前大かば(蒲)焼、鯵(阿字)本不生の早鮓を、じんばら腹のはる程に取り込み、八功徳水(清酒)のあつかん(熱燗)を引っかけ、雑修自力の心をふり捨て、只一心に心に女郎狂ひと手きびしい。
雑俳では「武蔵川」にすしの句が多い。
◆鮓桶のきのふにけふは投出され (寛延1年1748)
◆一夜鮓宮と桑名の人ごころ (寛延3年1750)
◆一夜鮓妾がつけてもらはれる (宝暦3年1753)
◆唯あれば少しうらみの鮓の蓼 (宝暦7年1761)
◆祝ひ日の気を引立る酢の匂ひ (明和8年1771)
「青木賊」(天明3年1783)の付合には
◆不埒(ふらち)なり御光の陰に鮓の桶
すしの名句は蕪村
なんといってもすしの名句は蕪村にとどめをさす。 「五車反古」(天明3年1783)に
◆胡蘿蔔(にんじん)の花は咲かずもありぬべし 田福
◆下福島の鮓なるる比 蕪村 本領は何といっても発句で
◆馴れ過ぎた鮓をあるじの遺恨哉 (宝暦中)
◆鮓桶をこれへと樹下の床几かな (宝暦中)
◆鮓つけて誰待としもなき身哉 (明和8年1771)
◆蓼の葉此君と申せ雀鮓 (安永6年1771)
◆鮒ずしや彦根の城に雲かかる (安永6年1771)
◆鮓おしてしばし淋しきこころかな (安永6年1771)
◆鮓を圧す我酒醸す隣あり (安永6年1771)
◆鮓をおす石上に詩を題すべく (安永6年1771)
◆すし桶を洗へば浅き遊魚かな (安永6年1771)
◆真しらげのよね一升や鮓のめし (安永6年1771)
◆夢さめてあはやとひらく一夜鮓 (安永末)
蕪村はよほどすし好きの仁だったらしい。このすしがほとんど生成だったのは彼が上方人で、主に上方に住んでいたからでもあろうか。 ります。
近世のすし
握りずし以後
渋い松平定信も寛政5年に失脚すると、田沼時代にいったん染みついた贅沢風は次第にその力をもりかえし,幕末掉尾の繁盛なる大御所時代の入る。 このころはすし屋がすっかり専門化しており、普通の料理人はあまりすしに手をつけなくなったためすしの話の本が意外と少ない。
この中には諸国の名産としてアユずし、鮒ずし、松百ずしの三者をあげるだけだし、作り方にしても、 早ずし アジ、モロアジ、コハダ、サッパ、小鯛、マス、アワビ、エビ、海苔巻
一夜ずし
アユ、サバ コケラずし サバ 飯なしずし 小鯛 とあって、馴れずし系はまったく姿を消している。
浪花の杉野権兵衛が「鮓飯秘伝抄」(享和2年1802)を出した。さすが上方の本場で書かれているだけあって,料理ずしが詳細に描かれている。しかも、所収33種のすしのうちで鮒鮓、淡海鮒鮓、吉野釣瓶鮓の三者は「まだ作り方も聞かないし食べたこともない」とはっきり書いていることは、一には著者がいかに良心的に筆をとったかがわかるし、一にはさすが保守的な上方でも純馴れずしはもはや当世とは縁がきれていたことを示す。
作り方を若干あげてみよう。 コケラずし 上等は鯛、アワビ、松菜。中、下等は赤貝、薄焼玉子、キクラゲ、栗、 竹の子、椎茸、三つ葉を貼る。飯は白米一升に水一升、塩五勺の割にする。冷えたらすし箱に詰め、酢をふる。蓼、山椒、生姜を薬味に する小倉ずし、千倉ずし、わかさずし、淀川ずしなどのは多くは中下 のコケラずしである。
起こしずし
右の具を飯と混ぜて押す。堂島あたりの相場師は縁起をかついです くいずしという。すくい起こして食べる。
巻きずし
具に鯛、アワビ、椎茸、三つ葉などを使う。
桜ずし
タコの足の稀醤油煮を用いる。芽紫蘇、木の芽をそえ、お起こしずし にする。コケラには向かない。 暖めずし 飯の熱いうちにコケラに漬ける。長くおくと腐る(暖かいが、今日の蒸しずしとは全然違うのに注意)
サバずし
北サバ(若狭、丹後より)か熊野サバを塩出しし、骨皮をとり、酢飯を 腹に詰め飯と魚を交互に詰めて押し、飯の酸味が魚に移ったらとり 出し、外側の飯粒をのけ、腹の飯は共に食べる。
今井ずしはこれと同 じである。朝に漬け夕方食べる。
薩摩ずし
アジ、ムロの丸ずしばかりだったが、近年はコケラにも漬ける。右の サバずしと同様に魚と飯を交互に詰め、強く重石して一日置く。酢の 代わりに酒を用いる。
上方で馴れずしがはやらないのだから、江戸ではなおさらの話である。
弐亭三馬は「弐亭日記」(文化8年1811)の中ですし屋のいんさつ引札を書いて
◆柳ずし五昼夜も漬けやのは土手節がはやったころ、吉原通いを馬でしていた
野暮な時代の話で、現在は
◆山谷舟の三挺だて の早漬だといっている。
鳥貝と東海道中膝栗毛
上方で鳥貝のすしが喜ばれたことは、「東海道中膝栗毛」京都の条(文化4年1807)に
◆中には上方に流行る鳥貝の鮨なり・・・・・
◆北八「何だ、コレヤばかの刺身を鮨に付けたのだな」
◆鮨屋「御評判の千倉鮨、鯖か鯖か鳥貝や鳥貝や」
◆北八「アレ弥次さん見なせへ、あの鮨は京で喰ったが とんだ好かった 一つ やらかそふ」 と、江戸者の口にも合ったことがわかる。
「摂陽奇観」(文政2年1819)に「万安売り御代賑いろは歌教訓鑑」というのを収録しているが、その中に ◆り(利)をすこしとりかい(鳥貝、取)のすし(鮓)さばのすし(鮓)
あさくさのり(浅草海苔)もやすしまきずし(巻鮓) とあり、海苔巻、サバずしと並んで鳥貝ずじが大衆的だったことがわかる。
江戸末期のすし
元来コノシロが下司魚だから、せいぜい粋にはなれても上品な代物には数えられなかった。ふつうはオカラずしで、駕籠かきや人足どもの腹ふさぎというところだ。
蜀山人は和製唐紙にきごうをもとめられたとき
◆和唐紙に物書くことは御免酒にコハダのすしや豆腐つみ入れ と断っている。
御免酒は千代田城下下馬先で供侍の陸尺どもに特に許された金魚酒で、コハダのすしもその程度に見なされていたのだ。
田沼時代は何のかのといっても勝手な真似をしていたのは老中どまりだったが、化政期の贅沢は大御所様(12代徳川家慶)が先頭だから、下々への普及も速い。
喜多村信節はその「嬉遊笑覧」(文政13年1829)において
◆文化のはじめのころ深川六軒ぼりに松がすし出きて世上すしの風一変し と、江戸前ずしの転換期を19世紀初頭に求めている。 この松のすしはそれほど有名な贅沢ずしだったので、川柳、狂歌、狂詩にもしば
しば読みこまれている。
◆松カ鮓一分ぺろりと猫がくひ(文政)
◆算盤づくならよしなんし松ケ鮓(文政)
◆荒神様へおみやげの松ケ鮓(天保)
◆本所一番阿他家安宅の鮓 高名当時並ぶべきなし
権家の進物三重の折 玉子は金の如く魚は水晶(天保7年1836)
◆伊豆わさび隠しに入れて人までも 泣かす安宅の丸漬けのすし 金一分は、文政中ごろの相場でだいたい銭一貫六百目、酒にして一斗余の値段だ。第三句は深川帰りに女房への賄賂と見ていいだろう。最後の歌でもわかるように、姿ずしか押しずしであって、握りではなかった。
また、高価なワサビを日常使用するようになったことも注目を要する。それまでの魚類の生臭を消すには辛子が普通に用いられ、蓼、生姜、山椒などもしばしば用いられていた。
古く元禄のころ、江島事件で三宅島に流罪にされた色男生島新五郎の
◆初かつを辛子がなくて涙かな の句は有名だ。
華屋与兵衛
この「松ケすし」と本所「華屋与兵衛」とは天保中、水野越前守の倹約令に引っかかり手錠をくらっている。「与兵衛」も文化5年開業というから、だいたい「松ケすし」と同じころのもの。
◆押しのきく人は松公と与兵衛なり(文政) とほめられているので、押しずしが主だったことがわかる。 文政5,6年ころ、この「与兵衛」が握りずしを発明したという。前々からいろんな人が考案し、工夫していたものを、今の形のスマートなものにしたので、彼の独創ではなかろう。いわば早ずしにおける松本善甫だという人もあるが、確かにそうらしい。
握り飯は屯食という名で平安朝以来行われているし、その握り飯に魚鮓をのせることは広西省の土人がこの百年も前からやっていることだ。だが、酢をきかせた握り飯に生魚をのせるのは、ある意味で革命的だともいえよう。
「与兵衛」が大正12年の大震災まではマグロのような下司魚を握らなかった。そのマグロが今日常人の口に入りにくい。世の嗜好の変化は恐ろしいものだ。
◆鯛ひらめいつも風味は与兵衛ずし 買手は店に待って折詰
◆こみあいて待ちくたびれる与兵衛すし 客ももろとも手を握りけり
◆流行の鮓屋町々に在り 此頃新たに開く両国の東 路次の奥にて名は与兵 衛客来り争い座す二間の中 歴史の古いおまんすしも栄えていた。
◆鳥飼も鮓もおまんはわるくなし(鳥飼は有名な菓子屋)
◆餅屋と聞けばおまんは鮓屋也
◆何れの歳か初めて聞く鮓屋の店 連綿数代市中に鳴る 海苔玉子塩梅妙なり知らぬこれ女房お満の情 このほか、へっつい河岸の「毛抜」、瓦町の「蛇の目」、新吉原の「通ひ鮓」、また「翁ずし」などは、当時の流行店だったそうだ。 コハダのすし 江戸末期のコハダのずしの盛行は一部旧弊の人たちの眉をひそめさせた。コハダはコノシロの一年子だし、コノシロは此城に通じているとして武家は決して食べなかったし、焼くにおいが人屍を焼くのと同じだというので、縁起をかついで嫌う人も多かった。 注)下野の室の八島の富人が、国司に思いをかけられたわが娘を恋人と一緒に逃がしてやり、棺にコノシロ=ツナシを詰め、娘の屍
と称し、これを焼いて上司の眼をごまかした。それでツナシを子の代というのだという説話もある。 たとえば小川顕道(文化11年1814)は、 ◆河豚このしろ我等若年の頃は我家は決して食せざりしもの也・・・・・このしろは今世 も士人以上は喰はざれども、魚鮓にして士人も婦人も賞翫(しょうがん)すと呆れている。 江戸は江戸風握りのみ 「東本願寺御膳所日記」のうち慶応から明治にかけての献立は、かの田沼時代のそれに比しはるかに質素になっているが、すしは大分ふており、この辺にも時代相がうかがわれる。
3冊、一年半の間に顔を見せるすしの種類は、すし(4件)、早ずし(9件)、切りずじ(3件)、箱ずし(2件)、散らしずし(4件)、海苔巻(4件)、握りずし(12件)、鯛ずし(1件)、ハモずじ(8件)、鮒ずし(2件)、サバずし(1件)、かますずし(1件)、卯の花漬(20件)である。
握りのふえていることが目に付く。単にすしとあるものは材料に松茸、蒲鉾、玉子糸湯葉、竹の子、椎茸などが並ぶから、実質的には早漬の散らしずしだろう。
早ずしには椎茸以下の具のほか、生臭として鯛、ハモ、蒲鉾、赤貝、時には縮緬ジャコも入るので、散らしか、それよりもコケラずしかもしれない。 切りずしは鯛、玉子、赤貝などで、結局箱ずしと同一ものだろう。箱ずしも鯛が主。握りも1回の鱒を除いて残りは鯛。サバずしは稲荷祭りだけ卯の花漬は鰻(2回)鱒(8回)、残り(10回)は鯛である。さすがは本願寺で古川に水は絶えなかった。
江戸期最後の市民生活を考えるのに最も重要なのは、 喜田川守貞の「守貞漫稿」(近世風俗史ともいう)(嘉永2年1849)である。 多くの江戸の著者と異なり上方のことをよく知っており,始終江戸のそれと比較し壺をはずれない判断を下している。
守貞によると、江戸で箱ずしがすたれ出したのは5、60年、以来の話で、一方大坂に江戸風握りずしが出来たのは文政末(1830年)の戒橋畔「松ケすし」からだ。箱ずしの玉子が厚焼きになったのは天保初年(1830~)心斎橋の「福本」からだ。江戸すしが入るまでは大阪で上等ずしは散らしで、押しずしは並であった。
江戸では五目ずしと握りずしは同等に扱われた。 稲荷ずしは、古くから名古屋にあり、江戸での振り売りは天保末(1845ころ)から始まる。 稲荷ずしの飯にはキクラゲ、干瓢などが刻んで混ぜてある。今日の関東では白飯か、せいぜい麻の実を入れる程度、 具をたくさん入れるのは関西風である。さらに、すし売りの衣装その他いろいろ面白い記事がある。
大阪の狂言作者 西沢一鳳は「皇都午睡」(嘉永中、1850ころ)において、江戸滞在中の印象のうち、当時の江戸のすしは握りばかりであること、特に「松ヶすし」や「与兵衛」のは念入りであること、へっつい岸の笹巻きを毛抜き寿司というのは(毛抜きのように)よく食う意味だ、 などと述べている。業界誌「寿」(昭和27年3月)に、明治初年の東京のすし屋番付の写真が出ている。観進元に「松之鮨」(神田川)行司「毛抜鮓」(河岸)、「与兵衛鮓」(東両国)など古いすし屋の名が見える。前頭筆頭に「小吉田鮓」(連雀町)がみえる。桶ずしの出店だろうか。今はどうなっているのだろうか。以上、すしはこの200年ばかり急激にかつ絶え間なく進展をしてきた。
それが今次の敗戦により国民の食生活全般に非常な変革を見た現在、この情勢に応じてさらに変化、発達をするかも知らず、またそのことがのぞましい。如何にして如何ように変えていくのが一番自然であるか、一番望ましいかということは人々それぞれの考えがあろうが、いずれにせよ、そのためには、過去の歴史においてその社会情勢に従って、すしが如何ように変わってきたかを調べるすし史が第一の参考になるのではなかろうか。